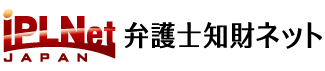営業秘密官民フォーラムメールマガジン掲載コラム 第21 回
判例解説―元従業員が秘密保持義務に違反したとして損害賠償請求がなされた事例
(東京地判平成29年10月25日裁判所HP)
弁護士知財ネット中国地域会
弁護士 妹尾直人
PDF版ダウンロード:[営業秘密官民フォーラムメールマガジン掲載コラム] 第21回 判例解説―元従業員が秘密保持義務に違反したとして損害賠償請求がなされた事例 (東京地判平成29年10月25日裁判所HP)
周知のとおり、経済産業省の営業秘密管理指針が、平成27年1月28日、全面改訂されました。この全面改定は、「知的財産推進計画2014」(平成26年7月知的財産戦略本部決定)で、一部の裁判例等において営業秘密の秘密管理性の認定が厳しいとの指摘や認定の予見可能性を高めるべきとの指摘があったことを受けてなされたものであり、中小企業における営業秘密の管理体制にも配慮し、不正競争防止法によって差止め等の法的保護を受けるために必要となる最低限の水準の対策を示すものとされています。
本コラムでは、上記の営業秘密管理指針全面改定後に出された東京地判平成29年10月25日(平成28年(ワ)第7143号)裁判所HPの紹介を通じて、企業が学ぶべきポイントをご説明します。
1 事案の概要
(1) 当事者
Xは、食品の商品企画・開発及び販売等を業とする会社である。
Yは、平成24年11月1日から同27年6月30日まで、Xに在籍していた従業員である。
(2) 秘密保持に関する合意
Yは、Xとの間で、①Xに在籍中・退職後にかかわらず、業務上知り得た機密事項(㋐Xの経営上、営業上、技術上の情報の一切、㋑Xの顧客、取引先に関する情報の一切、㋒Xが顧客、取引先と行う取引条件など取引に関する情報の一切、㋓その他、Xが機密事項として指定する情報の一切)につき、第三者に対する開示・漏えい、目的外使用、これを用いた営業・販売行為を行わない、②この違反によりXが損害を被った場合には、その損害を賠償するとの条項(本件秘密保持条項)を含む平成24年12月1日付け誓約書兼同意書及び同25年3月5日付け誓約書兼同意書を作成した。
(3) 会社の規模
YがXを退職した平成27年6月30日当時、Xには、Yを含め8名程度の役員及び従業員がおり、Yは、X在任中、主に営業を担当していた。
(4) 機密事項の管理状況
Xが同社の機密事項とする①「ずわいがに製品規格書」(本件規格書)、②「製造作業工程表」(本件工程表)、③「2014年度 長生水産 バルク品 原価計算 最終」(本件原価計算書)に関するデータは、Xの役員及び従業員が各自のコンピュータからアクセスできるサーバに保管されていた。また、④「2014/4~8主要得意先・販売粗利管理表」(本件得意先・粗利管理表)については、社内の定例会の際に、資料として従業員に配布されていた。
(5) 請求内容
Xは、Yが、Xとの間の秘密保持に関する合意に違反し、X在職中に転職先に対してXの取引先等の機密情報を開示し、また、転職後に当該機密情報を使用して営業等を行ったなどとして、債務不履行責任又は不法行為責任に基づき、Y及び転職先等に対し、損害賠償を請求した。
2 判示事項(要旨)
(1) 本件秘密保持条項の有効性について
使用者は、その業務遂行にとって重要な営業秘密等の情報が外部に漏えい又は開示されないようにするため、必要な保護手段を講じることができるが、被用者との間で被用者が在職中に知り得た営業秘密等の情報を退職後に外部に開示又は漏えい等しない旨の合意をすることは、被用者の退職後の行動に一定の制約を課すものであることに照らすと、こうした合意は、その内容が合理的で、被用者の退職後の行動を過度に制約するものでない限り有効と解されるべきである。
本件秘密保持条項において開示又は漏えいが禁止されている情報は、「業務上知り得た機密事項」であり、①経営上、営業上、技術上の情報一切、②取引先に関する情報の一切、③取引条件など取引に関する情報の一切、④機密事項として指定する情報の一切、がその内容であると規定されている。本件秘密保持条項の対象が「機密事項」であり、また、包括的な規定である④において使用者が機密事項として「指定する」ことが前提とされていることに照らすと、当該機密事項については、公然と知られていないこと、Xの業務遂行にとって一定の有用性を有すること、Xにおいて従業員が秘密と明確に認識し得る形で管理されていることを要すると解すべきであり、これを前提とする限りにおいて、本件秘密保持条項は有効というべきである。
(2) 本件秘密保持義務の対象となる機密情報への該当性について
①本件規格書、②本件工程表及び③本件原価計算書については、Xの役員及び従業員がこれらの情報を閲覧、印刷及び複製できる状態にあった。
④本件得意先・粗利管理表について、Xは、X代表者のパソコン内に入れられており、他の従業員はアクセスできない状態であったので、秘密として管理されていた旨主張するが、従業員全てがアクセスすることができないような形で、本件得意先・粗利管理表が保管されていたことを客観的に示す証拠はないから、Xの上記主張は採用できない。また、Xは、本件得意先・粗利管理表を印刷したものを定例会議の際の資料として配布していた際には、「社外持出し禁」と表示した書面も併せて配布した旨主張するが、定例会議が開催された際に本件得意先・粗利管理表が「社外持出し禁」などの表示が付された書面と共に従業員に配布されていたことを裏付ける証拠はないから、Xの上記主張は採用できない。
以上によれば、①本件規格書、②本件工程表、③本件原価計算書及び④本件得意先・粗利管理表は、いずれも、Xにおいて、その従業員が秘密と明確に認識し得る形で管理されていたということはできない。
これに対し、Xは、Xのような小規模な会社においては、その事業遂行のために取引に関する情報を共有する必要があるから、従業員全てが機密情報に接することができたとしても、秘密管理性が失われるわけではないと主張する。しかし、Xにおける上記管理状況によれば、Xの会社の規模を考慮しても、上記①ないし④の情報が秘密として管理されていたということはできない。
また、Xは、従業員全員から入社時において業務上知り得た情報を漏えい、開示しない旨の誓約書兼同意書を徴求していた上、X代表者は、会議の際などに上記①ないし④の情報を漏えい、開示してはならないことを従業員に伝えていたと主張する。しかし、従業員全員から秘密保持を背約する書面の提出を求めていたとの事実は、上記①ないし④の情報が秘密として管理されていなかったとの上記認定を左右するものではなく、また、X代表者が定例会議等の際に上記①ないし④の情報を漏えい、開示してはならないと従業員に伝えていたとの主張を客観的に裏付けるに足る証拠はない。
3 本判決のポイント
(1) 本件秘密保持条項の有効性について
前記のとおり、本判決は、①秘密保持条項は、その内容が合理的で、被用者の退職後の行動を過度に制約するものでない限り有効とした上で、②具体的には、不正競争防止法2条6項の「営業秘密」の3要件、すなわち、㋐非公知性、㋑有用性、㋒秘密管理性を前提とする限りにおいて、有効と判示しており、本件秘密保持条項を不正競争防止法の「営業秘密」の規律に沿う形で限定解釈をしたものと見ることもできます。
この点、経済産業省の営業秘密管理指針は、「営業秘密に該当しない情報については、不正競争防止法による保護を受けることはできないものの、民法その他による法的保護を一切受けることができないわけではない。すなわち、当該情報の取扱いについて私人間の契約において別途の規律を設けた場合には、当該契約に基づく差止め等の措置を請求することが可能であり、その際、法における営業秘密に該当するか否かは基本的に関係ないと考えられる」としていますが(同指針3頁)、本件秘密保持条項が「機密」という表現を用いていること、労働者が使用者より弱い立場にあり、離職後も含めた行動の自由を保障する必要があることからすれば、上記のような限定解釈は、基本的に妥当なものと考えられます。
(2) 本件秘密保持義務の対象となる機密情報への該当性について
その上で、本判決は、前記のとおり、Xが機密情報と主張する①本件規格書、②本件工程表、③本件原価計算書及び④本件得意先・粗利管理表のいずれもが、従業員において秘密と明確に認識し得る形で管理されていたということはできないとしています。
前述のとおり、平成27年に全部改訂された経済産業省の営業秘密管理指針は、一部の裁判例等において営業秘密の秘密管理性の認定が厳しいとの指摘があったことを踏まえ、不正競争防止法によって差止め等の法的保護を受けるために必要となる最低限の水準を示すこととしていますが、秘密管理性については、「秘密管理性要件が満たされるためには、営業秘密保有企業の秘密管理意思が秘密管理措置によって従業員等に対して明確に示され、当該秘密管理意思に対する従業員等の認識可能性が確保される必要がある。(中略)企業における営業秘密の管理単位における従業員がそれを一般的に、かつ容易に認識できる程度のものである必要がある」と定めています。
営業秘密管理指針の上記記述からしても、本判決が、本件秘密保持条項の機密情報の該当性につき、「従業員において秘密と明確に認識し得る形で管理されていた」ことを要求し、Xの会社の規模を考慮しても、秘密管理性を満たしていないと判断したのは、妥当というべきでしょう。
実際、Xは、①本件規格書、②本件工程表及び③本件原価計算書については、誓約書兼同意書に具体的に機密情報として明示したり、日常の社員教育の際に警告したりすることが可能だったわけですし、④本件得意先・粗利管理表についても、代表者のPCへのアクセスを制限し、かつ、配布資料に㊙(マル秘)の印を押すことにより、従業員が秘密管理されていることを明確に認識できる措置を講じることができたはずです。
4 最後に
中小零細企業においてありがちなことですが、単に形式的な体裁を整えただけの営業秘密保持の誓約書を作っただけでは、実際に情報の開示・漏えいがあった場合に、法的な保護を受けられないケースがあります。
自社にとってどのような情報が保護の対象とすべき営業秘密であるかを具体的に特定した上で、従業員等情報にアクセスする者に対して営業秘密であることを明確に認識できる措置を講じておく必要があります。
中小企業は、本判決を正しく他山の石とすべきでしょう。