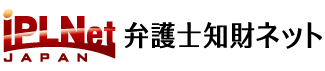営業秘密官民フォーラムメールマガジン掲載コラム 第42回
ドイツ連邦共和国における営業秘密保護新法の制定とその背景
~権利者優位の実務を行うプロパテントの国における特許侵害訴訟を以てしても、技術情報を守り切れない現実
弁護士知財ネット
弁護士 入野田 泰彦
ドイツ連邦共和国の新しい営業秘密保護法 “Geschäftsgeheimnisgesetz”(GTSA)は、長い時間をかけた厳しい議論の末、2019年4月26日に施行となった。その立法の過程を見れば、非公開ノウハウ情報及び非公開営業情報保護に関する欧州連合指令EU Directive 2016/943(Trade Secret Directive, “TSD”)を欧州連合域内の調和harmonizationの下(すなわち、本欧州連合指令の内容を最低限のものとして)、これを国内法化したもの、ということであるが、このドイツ国内の立法経過は、それほど単純なものではなかった。そのために、国内法としてのGTSAの成立は、欧州連合指令の求める期限を1年近くまで超過した。
すでに、民法上の一般不法行為責任としての営業秘密侵害行為に対する責任、不正競争防止法に基づく営業秘密侵害に対する責任、そして、刑事犯罪としての営業秘密侵害という三つの態様をドイツ国内には擁していた。それらは個々別々に存在していたが、深刻化する営業秘密侵害に対して、バラバラな対応であった感は否めなかった。そうした法秩序としての統合性という観点はもちろん大事である。そして、欧州指令を国内法化する要請があったのはもちろんのことである。
しかし、この立法過程(欧州規制の国内法化)において既に透けて見える事情は、欧州に留学、その後現地の知財実務家と協働して、すでに10年近くの滞在を経た筆者には、大変興味深い。非常に象徴的な「欧州とドイツとの関係」、そして急速に変化してきた「中国との関係をはじめとするグローバルな地政学的な変容と欧州におけるドイツ」、これを受けての「特許侵害訴訟を産業界の守護神とする知財立国ドイツの伝統的な在り方への見直しの機運」を表す事象のように思えるからである。
「欧州とドイツとの関係」
まず、何かと先走る「欧州」は、その「卓越した知見」に基づき、しかしながら、欧州連合加盟諸国にとって、実現困難なほどに高すぎるハードルを設定してきた。環境・安全法制然り、貿易・税制然りである。そうした欧州規則Regulationや、欧州指令Directiveの現実的な域内諸国における実施態様や、国内法制化及びその実務の実態は、「欧州」指導層の想定から隔たったものであることは、欧州で実際に生活している者であれば、暗黙の了解事項のように思える。小職は、2011年にドイツに留学に来て、2012年に卒業以来、ドイツの知財系事務所で研修、或いはドイツ人知財実務家と協働して、標準必須特許訴訟関連やインスペクション等の実務に携わってきたが、「欧州」の「前のめり振り」には、しばしば振り回されてきた。例えば、知的財産権権利行使に関する欧州指令Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights (IPRED)は、欧州域内の知財権侵害に対する証拠収集方法を定めたもので、2004年という欧州連合の「若気の至り」だったにせよ、Pre-litigation(提訴前)、Expert Oriented(技術専門家の広範な裁量による証拠探索とその選択)、Ex-Parte(相手方の弁護士の手続関与を大きく制限する)を柱とする画期的なものであったのは、もはや日本での立法作業の経緯もあって、周知となったとおりである。しかし、その欧州での現実は、特許訴訟先進国のうちの英国では、IPREDの要求内容を満たす1970年の判決に基づく判例法Anton Piller Orderを、1975年以来、実に制限的にしか運用しておらず、あくまでコモンローの要求する双方当事者の武器平等を優先しているし、ポーランドやチェコといった中欧諸国は、安いコストを武器に外国資本の工場を誘致している環境下にあって、このようなラジカルな知財権利者保護のための強制的証拠収集には消極的で、既存の民法や民事訴訟法の保全手続を援用するに止まる。同じドイツ語圏の国としてドイツの知財実務に通暁したオーストリアでも、強制的証拠収集には謙抑的である。ギリシャやスペインといった南欧諸国もまた然りである。欧州域内の調和Harmonizationの実態は、その辺りで止まっている。
そこで、今般の営業秘密保護に関する欧州指令TSDが、新時代に適合すべく打ち出した積極的な営業秘密保護がどこまで実効的に欧州諸国において実施されるのかは、少し距離を置きながら見ていく必要がある。また、このように先進的な欧州規制、欧州指令が定められる度に、「欧州」のモノの決まり方が、いかにも「天の声」の如く降ってくるのには、Brexitが本決まりになりそうな英国ならずとも、しばしば「ついていけない」と思うのもやむを得ない気がしてしまう。「いったい、誰のための欧州か」とは、EUが崩壊するのではないかという危機がクローズアップされる毎に問い直される根本的な問題であり、経済学者たちは、強大な経済大国ドイツが「欧州」を歪めているという批判をするし、実際、この指摘の多くは当たっているのであるが、他方で、「欧州」においてドイツが決して専制的に振舞えるような環境ではないことは、この欧州指令の国内法化の過程の議論を見ていてもわかることである。欧州連合の前身の欧州連盟、更にその前身の欧州石炭鉄鋼共同体の設立目的が、ドイツの抑え込みにあったことに鑑みれば、それはそれで理解はできるのだが、そもそも「大欧州」であろうとする「ドイツ」と、時に顔を出す歴史的系譜上の「ドイツ」が異なるような気もする。
「知財立国ドイツ」
次に、今般の立法が、「知財立国ドイツ」における重要な方針転換を行ったかもしれないその背景をご説明する前提として、ドイツの特許訴訟実務の概略を申し上げなければならない。
まず、ドイツにおける特許侵害訴訟の実務は、その主導的な裁判所であるデュッセルドルフ地裁において、特許権者(原告)の勝訴率が60~70%に及ぶ。この原告の優位性は、訴訟手続の至る所で貫徹されている。まず、証拠収集手続は、上述したインスペクション等の強力な方法が準備されている。欧州連合全域で成立した“IPRED”、知的財産権利行使のための欧州規制2004年EU Directiveが、知財権保護の3つの柱として採用した内容である、①提訴前に(Pre-litigation)②相手方代理人の関与を非常に制限した形でEx-parte ③技術専門家の広汎な裁量の元で行われ得るTechnical Expert oriented を最も体現するインスペクションをデュッセルドルフ地裁の訴訟実務の主導で導入して以来、廉価に、迅速に、的確に、侵害性にまつわる証拠を収集する。これに対して、日本では、証拠収集に関する査証手続を定めた新法においても、提訴後に、裁判所の裁量判断で、相手方代理人の関与の元で証拠収集を認めるものであり、欧州の主要国で実務上導入されたものに比べると非常に抑制的である。
そして次に、訴訟実務は、侵害訴訟手続と権利の有効性を決する無効訴訟手続とに分かれるbifurcate systemを採用する。一般に、侵害論では、権利者は、侵害被疑品(行為)を特許クレーム文言のスコープ中に収めるために文言解釈を広く主張する傾向となる反面、無効論では、先行文献の存在を避けるために、文言を狭く主張する傾向を持つ。ドイツ実務では、この両者を別個独立の手続にして、無効抗弁を侵害訴訟手続で提出できないようにし、権利者の侵害主張を広い文言侵害に基づくことを可能にしている。侵害訴訟手続は、無効訴訟よりも非常に迅速であり、訴訟手続開始後、最初の口頭弁論で当該事件の判決に至るまでのスケジュールが決定され、それを厳守する。年間で1000件から1200件に及ぶ特許侵害訴訟が行われるとされる。他方で、ドイツ連邦特許裁判所において行われる無効訴訟は、いささか不条理なほどに時間がかかる上(第一審結審まで2年から2年半、ときにはそれ以上)、侵害訴訟手続におけるようなスケジュール管理がきっちりとしておらず、見通しが立ちにくい。無効訴訟として係属する事件の多くは判決に至る前に侵害訴訟を含めた和解により取り下げられるとされ、年間では200件~250件程度が判決に至るに止まる。
ドイツの侵害訴訟における特許クレームの解釈実務は、日本実務と真っ向から異なる。ドイツ実務において重要なのは、発明課題の科学的・技術的理解であり、明細書の記載はこのための重要な辞書として扱われる。明細書中の実施例の記載は、あくまでも発明内容の技術的理解のための例に過ぎず、この存在を根拠にしたり、これに絡めたりする形でのクレーム文言の減縮は禁止される。発明当時の技術水準での問題点(発明課題)を技術的・科学的に理解し、この問題の解決としての発明を理解したならば、これが活かせるようにクレーム文言を合理的に解釈する。さらには、クレーム文言は、その文言が持つ機能的表現に着目し、発明内容が実現できるように、クレーム文言にある「機能的表現」が含意するものにまで広範にクレーム文言のスコープに包摂する。この結果、ほんの数年前まで、ドイツ実務家の間では、「均等論は死んだ」とまで言われ、広い文言解釈で権利を実現させる実務が定着した。均等論は、その上にさらに、欧州特許庁の厳しい補正要件を充足しきれないケースなどを事後的に救済する上で援用されるような形で復活し、特許発明の保護を図ってきた。
又、発明内容はあくまでも技術的・客観的に決せられるので、出願人の出願経過における主張や行動によって変容しない。ドイツ実務では、「包袋禁反言」という発想自体が、そもそも構造的に出てこない。英米法における特許制度は、出願人と国家との間の契約的な位置づけ故、禁反言という発想はむしろ当然であるが、ドイツの実務では、そもそもそうした構造になっていない。
さらに又、特許専門の裁判官の養成期間は十分に長く、いったんデュッセルドルフ地裁、マンハイム地裁、ミュンヘン地裁の特許専門部に配属されたassociate judge達は、そのまま同じ裁判所でキャリアを積んでいく。経験豊富な裁判官の継続的な指導の下、多くの事件に触れるために、練度が上がると同時に、相場観を涵養しやすい。技術的背景を持たない裁判官が多い実態ではあるが、特許クレーム、明細書の読み込みの能力は十分に高く、論点整理が明晰である。知財裁判官としてのキャリアの頂上は、最高裁の特許部の裁判長裁判官であり、憲法にすら、特許という言葉を以て、技術立国を支える必須の礎としている。こうした権利者優位の訴訟実務を以て、技術立国の守護神としての特許訴訟という位置づけである。
こうしてドイツは、とりわけ特許侵害訴訟を権利者優位の形で据えることで、知財立国の強固な礎とし、事後的な救済を盤石なものとする方針でやってきた。
「中国との関係をはじめとするグローバルな地政学的変容と欧州におけるドイツ」
技術立国ドイツの守護神たるに相応しいこのような特許訴訟裁判所を中心にした知財実務家たちは、ドイツ産業界の最重要な成長市場である中国に対しては、今世紀初頭以来、懐深い教育者として振舞ってきた。中国が、将来、ドイツ産業界を脅かすような技術立国になるという想定は、当時のドイツ首脳の頭にはおそらく皆無であったし、ドイツの輸出産業を振興する上で必須の巨大な成長市場である中国、そこへ、彼らの技術産業が安心して製品を輸出できるようにするために、中国の知財制度を整えるという政策を取ってきた。そのために、優秀な中国の学生を、裁判官や審査官、弁護士、弁理士の候補生としてドイツで教育し、特許権や実用新案権をはじめとするドイツの実務を中国にもたらす戦略的計画だった。中国とドイツの蜜月は、東西ドイツ統一後の経済成長率の低下と財政困難に悩んでいたドイツには、大変な金城湯池をもたらした。さらに、欧州統一通貨ユーロを導入するにはとても無茶な欧州の貧しい国々にも欧州連合への加入を認めることが、「結果として」、彼らの財政破綻によるユーロ安といういわば「天然の金融緩和効果」をもたらし、自国の輸出産業の空前の活況に関らず、自国通貨が上昇しないどころか、南欧諸国の財政逼迫・破綻により、崩落的に安くなる通貨を武器に、ドイツの輸出産業はますます潤った。
このような経済政策は、ドイツの世界戦略として、2015年頃までは、非常に有効で、ドイツはその黄金時代を享受した。中国における知財制度もますます活況を呈し、アメリカに次ぐ特許出願数を数えるに至り、ドイツから移入した実用新案制度も機能するようになり、特許侵害訴訟地としても、重要性を増してきた。この頃のドイツ知財実務家達、特に首脳陣は、大いに面目を施したはずである。
ところが、ドイツ指導層がロジカルに描いた、そして実現してきたパラダイスのような良い話は長く続かない。輸出産業の柱である自動車産業に、まず、アメリカから、背筋に悪寒が走る悪い知らせがあった。「クリーン・ディーゼル」という耳あたりの良い技術を以て、日本では黒煙を吐く、スピードが出ない、商用車やダンプカーにばかり使われて評判の悪かったディーゼル車を、「炭酸ガス排出がガソリン車より少ない環境適合車」として世界中に売り込み、欧州市場では自動車の主流に仕立て上げ、アメリカ市場にも乗り込んだのだが、そこで呆気なく躓いたのである。2015年9月、米国環境保護局(United States Environmental Protection Agency, EPA)が、VWグループのディーゼルエンジン車に、不正なプログラムが搭載されていたことを公表した。ドイツ政財界に君臨する現代の貴族の様な自動車工業界の首脳が、米国官憲に訴追され、米国環境当局に対して147億ドルにも上る和解金を支払うことで漸く合意に至るなどという屈辱的な扱いがなされた。そして、炭酸ガス排出が少ない環境適合車としてのディーゼル車に頼ったドイツ自動車産業は、毎年記録更新を続ける熱波の夏に見舞われた市民から、環境問題の根源として厳しい批判にさらされ始めた。そこで、ドイツ自動車産業は、生き延びるための方策を考えなければならないことになった。その新たな目標は、日本に大きく水を開けられたハイブリッド車で競うのでは勝算はなく、一足飛びに、電気自動車への切り替えであった。しかし、その電気自動車の技術において、或いは、自動運転車に必須の情報通信技術において、ドイツ自動車産業のすぐ背後に迫っていたのが、中国政府に多額の援助を受ける巨大な中国企業群であった。いつの間にか、中国企業の技術はドイツの先端技術に迫り、もはやドイツ産業の旗艦である自動車産業すらも、数多の中国企業に取り囲まれ、甲板まで海水に洗われる中、船の中にまで入ってこられている、という状況になっていた。それでも、中国市場で勝負を続けるしかないドイツ産業界は、なぜこのような短期間に、あの遅れた大国であった中国に追いつかれたのか、という至極当然の問いを自らに問うことになった。そして、まさしく今更ながら、中国との蜜月が、甘いばかりではない、強烈な苦みをもたらすものであったことを認めざるを得なくなった。ドイツ政府が旧東独領内に誘致した中国企業の工場団地を訪れてみれば、ドイツ人たちでなくとも、その苦さが如何ほどのものか、わかるであろう。少しゾッとするような気持になるかもしれない。工場団地の正門入り口に、巨大な五星紅旗が中央に翻り、ドイツの国旗とEUの旗が、主人に随う侍従のように少し低く、小さくはためいている。巨大な工場のあちこちには監視塔のようなものがあり、フェンスの上には、いくつもの監視カメラが作動している。これを見たドイツ指導層は、その明晰な頭脳を以て中国との蜜月にドイツの隆盛をかけてきたことの行き着く先の恐ろしい現実に眼を剥き、背筋に冷たいものが走ったのではないか。こうした中国との蜜月への疑心が鎌首をもたげてきたところに、米国の大統領が、Huawei社を筆頭とする中国情報産業を危険視し、敵意をあからさまにした貿易戦争が勃発した。普段であれば、米国のこうした「仕掛け」に距離を置くドイツ指導部が、以前とは明らかに異なった対応をし始めた。
「特許侵害訴訟を産業界の守護神とする知財立国ドイツの伝統的な在り方への見直しの機運」
Geschäftsgeheimnisgesetz”(GTSA)における重要なポイントは、技術・知財立国であるドイツにおいても、出願公開になじまない技術情報の重要性が顕著になってきたという技術情報の性質の変容と、技術情報の保護を、特許侵害訴訟、就中は、権利者優位の実務を徹底することで、重要な技術情報の出願公開を前提に、これを「事後的に」技術情報を守るという姿勢の伝統的な特許を中心にした知財政策を再考せざるを得なかった部分にこそあると思われる。後者の部分は、要らぬ憶測や地政学リスクを惹起することを厭う立法関係者が、公に、直截に口にすることはない。しかし、既に存在していた不正競争防止法上の営業秘密保護では不十分、ということの言外の意味、すなわち、既存の営業秘密保護と出願公開を前提とした知財権の訴訟を通じての事後的救済では、もはや技術情報の保護が図り得ないというドイツ産業界・政界の厳しい判断が背後に存在することを、汲み取っていくべきであろう。日進月歩の電気自動車の技術の進歩に、如何に優れた特許侵害訴訟を以てしても、2年、3年と時間がかかる。これで対応していて間に合うだろうか。又、重要な技術を公開して、侵害訴訟で決着をつけるというやり方では、権利化までの時間がかかり過ぎる上、公開するというやり方が良いとはとても思えない。そして何よりも、そもそも、なぜこんなに早く追いつかれたのだろうか。
この新法の出現は、特許侵害訴訟王国であるドイツにおいて、非常に画期的であると同時に、権利者優位の特許侵害訴訟を以てドイツ産業界の守護神とする知財政策方針についての軌道修正の苦渋の決断という面がある。すなわち、技術・知財立国であるドイツにおいてすら、その権利者優位の特許侵害訴訟をはじめとする制度及びその実務によって如何に事後的な救済を最大限図ったとしても、それでは国家、企業の虎の子の技術情報を守り切れないという現実、すなわち、市場にとって決定的な営業秘密が、監視の目を容易く潜り抜けて競合企業、それもドイツの司法・行政の手が届かない外国に持って行かれるという、技術立国の成り立ちを脅かす地政学リスクがあることをついに受け入れた結果ということでもある。そして、ドイツ指導層の苦渋の判断として、もはや知財侵害訴訟だけではなく、ドイツ人が必ずしもお得意ではない「人権問題」を不可避的に含む「営業秘密保護」を正面から求める立法をなすことであった。
しかし、実際のところ、日本では、そもそもドイツの営業秘密保護法の新法制定の事実をほとんどと言ってよいほどの実務家、企業は、残念ながらご存知ではない。それも無理からぬのは、日本の知財実務家とドイツとの接点は、ドイツの出願系の実務家に偏り、彼らは新法である営業秘密保護法の存在すらも知らぬことが少なからず、さらにその実務には全く疎く、尚、更に残念なことに、そもそも特許侵害訴訟の実務にすらも実は疎いことがある。出願系業務と権利行使業務の完全分業、まさにbifurcate systemと言ったら、言い過ぎだろうか。日米英独の均等論の要件比較など、日本でこそ有用で人気を博するテーマであろうが、ドイツでこれをやると、大変にしらける。これもまた、侵害訴訟の現実をご存知ないままに観念的比較をするばかりであると、ついしてしまうことのようであるが、こうした議論にも愛想よくお付き合いしてくれるドイツ人は、たいてい出願系の専門家である。
この法律の制定の前、ドイツにおける営業秘密の保護は、不正競争防止法の営業秘密保護を通じて行われていた。これは、日本における営業秘密保護の態様とほぼ共通であった。それ故、少し海外の事情に通じている日本の知財関係者であれば、「ドイツは知財権保護に熱心だから、さもありなん。不正競争防止法の営業秘密保護部分を切り離して独立した立法をしたのだろう。」という程度に受け止め方であったかも知れない。しかし、そのような感じ方であったとしたら、世界中で技術情報スパイ行為がますます頻繁に行われ、その中でも日本は最も技術情報の格好とターゲットとされ、技術情報の漏洩、否、もはや技術情報の横領、窃取、詐取、喝取、強奪と言うべき大胆なスパイ行為によって、容易く技術情報を入手できるスパイ天国のような状況を呈していることへの認識、それ以上に、感受性そのものが鈍磨した危機的な状況の証左である恐れがある。
かく言う筆者も、10年前まで、東京で実務をしていた頃は、営業秘密保護をあたかも一般条項の様な漠としたものと感じていた。他方で、営業秘密保護は、報道の自由との関連でジャーナリストとの関係、又、社内違法行為の通報に関する内部告発者との関係、更には、被用者の職業選択の自由との関係で緊張関係にあるといった、実に「一般法的」な理解に止まっていた。これらの要素は、むしろ、聞き慣れた事情であって、現在の状況からは、むしろ穏やかにすら見える。
しかし、「営業秘密(技術情報)保護リテラシー」の欠如は、やがて技術開発競争で常に不利な戦いを強いられることになり、世界市場で優位性を持っていた一つの産業を丸ごと失う事態になる。そうした状況を目の当たりにした後の筆者には、日本の状況が「茹でガエル」のように見えてならない。世界のトップを走っていた半導体産業を失い、液晶関連の産業を奪われ、次は情報通信技術を持って行かれ、優れた品種の確立をしてきた植物も容易く海外で真似られ、今度は蓄電技術も危うい。日本の産業界、法曹界、知財界は、未だ以て、自国内の競合他社との競争を念頭にしているのだろうか。もはや、日本企業の競合は、中国や韓国をはじめとする諸外国であり、中国や韓国は、海外では日本よりもよほどメジャー且つ強力な競合相手、或いはカスタマーとして君臨する存在となっている。情け容赦はない。
そうした競合、或いはカスタマーとの間では、しばしば、否、殆どといってよい程、日本国内の特許訴訟は当てにならない。それは、単に権利者が有利ではない実務であるというに止まらない。侵害行為はひたすら海外市場、海外工場で行われているからである。一度技術情報がそうした企業に渡ってしまったら、その領域での市場優位性を一気に失う恐れが高い。その上、日本は今や、地政学リスクの渦中にあると言っても言い過ぎではない。
知財の現場は、地政学と無縁では全くない。それどころか、国家の盛衰を決し得るのが技術情報、すなわち営業秘密及び知財である。国家機密に匹敵する情報の遣り取りに、日本が大嫌いな人々が何もしてこないと構えているとしたら、呑気過ぎる話である。技術情報は、市場を制する。それを失ったら、資源のない日本という国は生きていけるのか。
ドイツは、その優れた特許訴訟制度・その実務を通じて技術を守り切れるという考えでやってきた。それが、技術情報をターゲットにしたスパイ行為が行われる状況がますます明らかになり、どうやら特許侵害訴訟で侵害者を市場から排除するという方向性だけでは自国産業を守ることが難しいことを認めざるを得ないこと、巨大な成長市場であった中国を最も重要な市場と位置付け、自動車産業を筆頭にした自国の輸出産業を大いに振興するが、当時は知財不毛の地として悪名高く、侵害品海賊品の地としての悪名ばかりであった中国の地にドイツ流の知財教育を施せば、技術に依拠した自国の輸出産業を守り切れる、侵害品が出ても対処できるようになる、というシナリオがどうやら楽観的に過ぎたことを苦い思いで認め、その知財政策の軌道修正を図っている。
日本のどこかの大きな新鋭工場に、巨大な五星紅旗が翻り、それに付き従うように日章旗がちんまりとその横で嫋やかに風に吹かれている下、工場の制服に身を包んだ日本人たちが整列している図…。知財専門家として指導しに来たドイツ人同僚の彫りの深い横顔にさらに影が差し、こちらを見ようとしない。「時代は変わったんだよ」と呟かれて、正面には、こちらを向いている監視カメラがある中、問いかける事が怖いのに、惨めな思いを押し殺しながら「それはいつ?」とだけ、やっと問う…。
以上