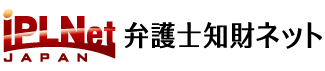営業秘密官民フォーラムメールマガジン掲載コラム 第56回
他人の技術情報を不用意に受け取ってはいけない
弁護士知財ネット
弁護士 近藤惠嗣
PDF版ダウンロード:[営業秘密官民フォーラムメールマガジン掲載コラム] 第56回 他人の技術情報を不用意に受け取ってはいけない
1.ある相談案件
もう、だいぶ前のことでしたが、アメリカでトレード・シークレットを盗んだという嫌疑をかけられているので、対応を相談したいという依頼がありました。古い話なので詳細は忘れてしまいましたが、おおむね、次のような話でした。
依頼者は電子材料などに使用される特殊な合金を開発しているメーカーでした。仮に、A社としましょう。
ある時、A社の中央研究所で部長を務めていたX氏はアメリカの同業者であるB社を表敬訪問しました。その同業者の会社構内に入構する際に、日本流にいえば「入構願」にサインし、引換に「入構証」を受け取りました。X氏は入構願に記載されている内容など気に留めませんでしたが、そこには会社構内で見聞きしたことを秘密に保持するという秘密保持条項が記載されていました。現在では、日本でもよく見られる実務ですが、当時の日本ではあまりなかったのかもしれません。いずれにしても、これはアメリカでの出来事です。
さて、X氏は応接室に通され、国際会議などで顔見知りのP氏と挨拶し、その後にしばらく雑談をしました。その折に、P氏はある合金にМ元素を添加する研究に触れました。P氏の研究している合金にはX氏も関心があり、また、М元素を添加するというアイデアはX氏にとっても「なるほど」という思いのするアイデアでした。
帰国後、X氏はその合金にМ元素を添加して最適な添加量を探す実験を行うことを思い立ち、部下に命じて実験計画を立てさせ、実行に移させました。実験は成功し、実験結果に基づいて特許出願がなされました。当然、特許出願は日本のみならず、国際出願がなされ、対象国にはアメリカも含まれていました。
それから数年後、X氏の発明はアメリカでも特許され、特許公報がP氏の目に触れることになりました。P氏は発明者としてX氏の名前があることに驚き、B社はA社に抗議することを決めました。
この抗議に対する対応についての相談が私のところにきたわけです。
この状況で、B社の手許にはP氏がX氏に話した内容の記録があると想定しなければなりません。当時のアメリカであれば、P氏が応接記録に雑談の内容を記入し、別の者がその内容と日付を確認することは当然に行っていたと想定しなければならないことでした。
一方、X氏が聞いたのは問題の合金にМ元素を添加するということだけです。そして、問題の合金にМ元素を添加するというアイデアがX氏によるB社訪問前から公知であれば、この程度の内容はトレード・シークレットにはなりません。そこで、この点の公知文献調査を依頼しましたが、このことを述べた文献は見つかりませんでした。
この点について、X氏は、この程度のことは常識で、自分はB社訪問前からМ元素添加の考えを温めていたと主張していました。そこで、手帳の欄外の走り書きでもよいから、X氏がМ元素添加についてメモしたものはないか探してもらいました。しかし、X氏の言葉とは裏腹に、形に残る記録は何も見つかりませんでした。
この状況で訴訟になれば、A社が不利なのは明らかです。そこで、私はなるべく有利な和解条件を探って和解することを勧めました。結末ははっきり覚えていませんが、特許の無償譲渡だったように記憶しています。
この事件が仮に訴訟になった場合、X氏の弁解が真実であったとしても、それを訴訟で立証することは難しかったと思います。したがって、和解はやむを得ないことでした。しかし、その結果、X氏が部下に命じて行った実験で得た最適添加量までもB社に渡さざるを得なくなったわけです。
この事件から得られる教訓は次のとおりです。
第1に、他人から技術情報を受け取ると危ないということです。
第2に、他人から技術情報を受け取らざるを得ない場合には、その前に、自ら保有している技術情報を文書化してその文書の作成日付を証明できるようにすることが必要だということです。この2つ目の要求を満たすために公証人を使うことが考えられますが、簡便な方法としては、文書をレターパックなどで自分宛に送って、その封を切らずに保存するという方法も考えられます。この方法の場合、紛争が起きた場合にのみ公証人の面前で封を切って公正証書を作成してもらえばよいことになります。急に海外で技術的な打ち合わせをしなければならず、公証人の予約が取れないというような場合に使える方法だと思います。
2.ある雑誌記事とその反響
上記の相談案件からだいぶ経ったころ、ある特許無効審判の案件の依頼者から似たような事件のことを知らされました。その事件の依頼者からの情報でインターネットを検索したところ、次のような事件があったことを知りました。
2008年10月、日本を代表するある会社(仮に、N社としましょう。)のウェブ・サイトに次のようなニュース・リリースが掲載されました。
「当社が、米国のT大学及びカナダのH社(原告)から米国テキサス州裁判所に提起されていた訴訟について、本日和解が成立しましたのでお知らせいたします。
和解の内容は、当社と原告は本訴訟を終結させること、当社は違法行為を認めないこと、当社は原告に和解金3000万ドルを支払うこと、訴訟対象の特許は当社が保持すること、及び今後は同特許を原告に独占的にライセンスすること等です。
本訴訟(平成13年6月提起)では、原告が当社に対し、充電式のリチウム電池に関する技術についての営業秘密を流用したとして損害賠償等を請求してきており、これに対し当社は、違法行為を一切否定して争ってきました。
しかし、当社は、このまま訴訟を継続する場合に発生する費用及び陪審審理の不確実性等を総合的に考慮し、和解したものです。
本件に伴う2008年度連結業績予想の修正は行いません。」
私は、前述の相談案件の結末から類推して、この会社は、他人の営業秘密を流用したとの疑いをかけられ、アメリカの訴訟手続の中でその疑いを晴らすことができそうもないと判断した結果、日本円にして約30億円もの和解金を支払うことになったのであろうと考えました。当時、私は「日経ものづくり」という雑誌から営業秘密に関する記事を依頼されていましたので、この推測を記載ました(2009年2月号)。
この記事に関して、私は、N社の依頼を受けた著名弁護士から名誉棄損であるという警告を受ける羽目になりました。この警告騒ぎは同誌5月号の編集後記に「確定した事実関係を記述したものではありません。」、「筆者が推測を述べたものです。」と記載していただくことで解決しましたが、私が専門家として事件の解釈を述べていることは記事全体を読めば自明であるにもかかわらず、なぜ、N社が著名弁護士を使ってまで、私に警告してきたのか分かりません。
以下に、この事件の経緯を要約し、この事件から得られる教訓に関する私の意見を明らかにしますが、詳細な事実関係について客観的な事実を述べるものではありません。教訓を明らかにするという目的との関係で、省略や単純化を含み得ることをご承知ください。
3.N社事件のあらまし
N社事件を素材にして、なぜ、このようなことになったのか、事件の背景をさぐってみましょう。
N社はアメリカのT大学に技術者であるA氏を客員研究員として派遣しました。派遣に際して、A氏がT大学に在籍中に取得した一切の技術情報については、いかなる開示、無断使用も禁止するという内容の契約が締結されました。
A氏が派遣された大学の研究室には、リチウムイオン電池の正極活物質としてLiFePO4という材料を使用することを研究している博士課程の大学院生が在籍していました。A氏は、その大学院生に対してアドバイスをしていました。この事実は大学院生の論文の謝辞にA氏の名前があることから窺い知ることができます。A氏は、大学院生との接触を通じて、結果として、リチウムイオン電池の正極活物質としてLiFePO4を使用するという知見を得たものと思われます。その当時、リチウムイオン電池の正極活物質としてLiFePO4を使用することは公然と知られた情報ではありませんでした。
1年間の在籍期間を終えて、A氏は日本に帰国しました。帰国後、A氏は、リチウムイオン電池の正極活物質としてLiFePO4を使用することに関する研究を行い、N社は、その約1年後に日本特許を出願し、その後、この出願に基づいて日本特許を取得しました。一方、T大学では、前述の大学院生とその指導教員の研究に基づいてアメリカ特許を出願しました。このアメリカ特許の出願に基づいてT大学はアメリカ特許を取得し、リチウムイオン電池やリチウムイオン電池を組込んだ製品(パソコン、電動工具など)についてアメリカでビジネスを行う可能性のある日本企業に対して、H社と共同してライセンス交渉を開始しました。電機メーカーであるS社は、その交渉の過程でN社の日本特許の存在をT大学に指摘して、T大学からのライセンスのみでは事業化が困難であることを述べました。
S社からの指摘により、T大学は、リチウムイオン電池の正極活物質としてLiFePO4を使用するというアイデアをN社が盗用したと考えて、テキサス州の裁判所においてN社を被告とする訴訟を提起しました。その主張の骨子は、N社の日本特許がT大学のライセンスビジネスの障害となっているところ、N社の特許出願はA氏の派遣に際して締結された秘密保持契約に違反してなされたものであるから、N社は、T大学のライセンスビジネスが円滑に進まないことによる損害を賠償すべきであるというものでした。
訴訟は長期間を要しましたが、N社のニュース・リリースにもあるとおり、最終的に、N社は、T大学に3000万ドルを支払って和解することを余儀なくされました。
以上がN社事件のあらましです。
4.情報の受け手の情報管理
これまで、営業秘密の保護に関しては、自社のノウハウをどのようにして守るか、という視点からの解説が多かったと思います。そのために、不用意に他人の営業秘密を知ってしまうことが技術開発の足かせになってしまうという側面が見落とされてきました。しかし、冒頭に述べた相談案件の事例や、N社事件は他人の営業秘密を知ることの怖さを物語っています。
アメリカでは、州ごとに営業秘密の保護に関する法律が制定されています。法律の細かい規定は州ごとに多少の相違があると考えられますが、全体としてみれば、わが国の不正競争防止法における営業秘密の保護規定と大差のないものとなっています。したがって、アメリカで上述したような訴訟が起きるのは、営業秘密の保護に関する法律の違いに原因があるわけではありません。
違うのは、法律そのものではなく、営業秘密の保護に関する研究者や技術者の認識なのです。営業秘密の保護に関して法的手段、具体的には訴訟も辞さないという態度をとることに関しては、アメリカの企業や研究機関は日本よりもはるかに徹底しています。研究開発担当の技術者が退職して競争企業に移籍したような場合、競争企業に対して営業秘密の保護に関する警告書を送付することも一般的に行われており、他社を退職した技術者を受入れる側も、不用意に他社の営業秘密に触れることのないように注意しています。最近では、ソフトバンクと楽天の間で起きた退職者の受け入れに絡むトラブルのように、日本でも時代が変わりつつあるようです。
今後、N社事件のような訴訟がわが国でも増えるかもしれません。わが国の不正競争防止法の下でも、理論的には、このような訴訟が起こる可能性はあります。アメリカでは、以前から人材の流動性が大きかったことから、このような訴訟の可能性も大きかったわけですが、今後、わが国でも人材の流動性が大きくなるにつれて、このような訴訟が起きるかもしれません。
自然の成り行きとして、人とともに情報は拡散します。しかし、その情報に他人の営業秘密が含まれていれば、その情報を使用したり、開示したりすることは他人の知的財産を侵害することになり、N社のように巨額の和解金を支払わなければならない羽目にもなります。自社の営業秘密の漏洩を防ぐことも大切ですが、新時代の情報管理においては、他社の営業秘密を不用意に受取らないことが必要となります。また、自社情報の管理は、自社の営業秘密を保護するという観点のみならず、他社の情報を誤って使用したり、開示したりしないという観点からも必要となるのです。
5.ある中小企業を襲った悲劇
ここまで述べたことは、大企業や先端技術の研究開発に関わっているベンチャー・ビジネスだけに関係することではありません。全く別な形で大企業から製造委託を受けている中小企業にも起こり得ることです。以下、「コイルマット事件」(東京高判平成6年3月23日、判時1507-156)の背景技術をヒントにして「コイルマット事件・後日談」を創作することによって中小企業の技術情報管理の重要性を明らかにします。なお、「後日談」はあくまでも説明のためのフィクションであり、登場人物等については、現実の「コイルマット事件」とは何の関係もありません。誤解のないようにお願いします。
コイルマットは独特の形態を有し、その形態ゆえに、玄関などに設置することにより靴裏の砂などを除去するという効果を有しています。この形態を文章で説明するのは難しいですが、調理前のインスタントラーメンを想像してもらえばイメージがわくかもしれません。大きなビルの玄関の外側や男性用トイレの足元などによく使われています。この形態は製造プロセスに由来し、その製造プロセスに従う限り、似たような形態が得られます。コイルマット事件では、この形態が商品等表示に該当するか否かが争点になりました。
この製造プロセスは、細かい差異を別にすれば、溶融した樹脂をノズルから射出し、射出された糸状の溶融樹脂を冷却水に落下させることによって、冷却水表面で糸状の樹脂をループ状に屈曲させるという製法です。このような製造過程を経るため、形態そのものを直接決定することはできません。そのコイル状構造は不規則なパターンとして常に異なった形態のものとしてしか形成されえず、その意味では、その形態は偶然によって定まるものであり、前述のように、この形態の特徴の故に、靴裏の砂などを除去するという機能的効果を有します。
コイルマット事件の結果、コイルマットの製造プロセスに関する特許権が消滅していること、コイルマットの形態は商品等表示として保護されるものではないことが明らかになりました。K社はこの機会にコイルマットの市場に参入することを考え、特許公報を参考に試作品を製造しましたが、ループ状になった糸状の樹脂が使用とともにバラバラにほどけてしまうなどの問題があり、商品としては出荷できませんでした。
そこで、K社は別の製品の製造委託をしたことがあるL社に製造を委託しました。委託に際してK社はL社に対してノズルを貸与し、試作品の製造記録(実験記録)のコピーを交付しました。製造記録といっても、製造装置の手書きのスケッチ、樹脂を射出するポンプのスクリューの回転数、ノズルを加熱するヒータの設定温度、冷却水の水温など、いくつかの数値が記載されているだけでした。また、コピーには、マル秘など、秘密を表すマーク、スタンプ等は一切付されていませんでした。
L社は樹脂製品の製造に使用する基本的な設備を自前で保有していました。これらはK社から受け取ったものではなく、K社の指示で購入したものでもありませんでした。また、コイルマットの製造は初めてでしたが、樹脂製品の製造に関する独自のノウハウも保有していました。したがって、L社にとっては、K社の失敗作の製造記録のコピーをもらっても何の役にも立たないことは明らかでした。しかし、K社が無理に置いていってしまいましたので、返すまでもないと考えて引き出しに放り込んでおきました。
前述のとおり、コイルマットの製造プロセスは、溶融した樹脂をノズルから射出し、射出された糸状の溶融樹脂を冷却水に落下させることによって、冷却水表面で糸状の樹脂をループ状に屈曲させるというものですからそれほど複雑ではありません。また、ノズルはK社から貸与されたものを使用しますので、糸状の樹脂の太さはだいたい決まっています。しかし、樹脂をノズルから射出するスピード、ノズルと冷却水の水面までの距離、冷却水の温度などによって、ループ状に屈曲した糸状の樹脂が相互にくっついたり、バラバラになったりします。冷却が速ければ後からくる樹脂に接触しないうちに表面が硬化してくっつきません。反対に冷却が遅ければ樹脂同士がくっつきすぎてマットの弾力がなくなります。したがって、試行錯誤で好みの硬さを出していくことになります。
L社には職人気質の技術者がいましたので、試行錯誤の結果、それほど長い時間を要せずに、適度な硬さの試作品が得られました。試作品をK社に提出したところ、他社から市場に出ていた製品と比べても遜色がなく、むしろ優れているとの評価を得ました。そこで、K社とL社は正式に製造委託契約を締結し、L社の製品をK社が販売することで市場からも高い評価を受けました。
K社とL社の関係は20年以上にわたって良好でした。しかし、価格設定の考え方の相違等から関係が次第に悪化し、とうとう、L社はK社との製造委託契約を解除して、コイルマットの直売を開始してしまいました。K社とL社の製造委託契約には競業禁止期間の定めはありませんでしたし、契約解除は契約の任意解約条項に従ったものでしたので、L社が契約を解除してコイルマットの直売をすることは契約違反にはならないはずでした。
そこで、K社が思いついたのは営業秘密の不正使用を理由としてL社によるコイルマットの製造を差し止めることでした。失敗した試作品の製造記録のコピーが営業秘密に該当し、L社がコイルマットの製造を継続すること自体が営業秘密の不正使用に該当するという主張に基づいて、K社は、L社に対して差止及び損害賠償を請求する訴訟を提起しました。
確かに、不正競争防止法の逐条解説などでは、失敗した実験の記録も「事業活動に有用な技術上の情報」に該当するとされています。しかし、上述した「後日談」のシナリオにおいて、K社とL社の製造装置は異なりますので、K社の製造装置では、ポンプのスクリューの回転数が例えば毎分98回転であったという情報をL社がもらっても何の役にも立ちません。また、製造条件を最適化していく試行錯誤の過程で、ある一つの条件が失敗条件であったことを知っても、試行錯誤の過程にはほとんど影響しません。
そんなわけで、L社としてはこの訴訟の結果を楽観視していました。しかし、驚いたことに、裁判所はK社の主張をすべて認めたのです。
L社にとっては意外な結論ですが、不正競争防止法の条文を素直に読むと、裁判所がこの結論に至った理由を理解できないわけではありません。営業秘密の定義に基づいてこの結論に至った論理を検討してみましょう。
6.営業秘密の使用とは何か
不正競争防止法は、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていないもの」を営業秘密と定義し、この定義に合致する情報を保護しています。この定義に基づいて、「管理・有用・非公知」を営業秘密の3要件と呼ぶこともあります。
この定義にあてはめると、K社からL社に渡した製造記録にはマル秘のマーク等はありませんでしたが、裁判所は、製造記録などは、通常、秘密として管理されていると考えたようです。次に、前述のとおり、失敗した実験記録であっても、「事業活動に有用な技術上の情報」に該当することについては、学説、判例において争いのないところです。最後に、公然と知られていない点についても、製造記録に記載された事実、例えば、特定の日に、特定の実験室で、ノズルのヒータの設定温度が198℃であった事実等が公然と知られていないことも、社会通念上、明白だと思われます。ここで、注意すべきことは、材料の樹脂の流動性を保つには190℃以上の温度が必要であるという技術常識が周知であったことを立証しても、実験記録そのものが公然と知られていたことにはならないことです。
以上のように考えると、製造記録は、L社にとっては無益な情報であっても、営業秘密の定義を充足することになります。営業秘密の定義を充足することは、不正競争防止法の保護を受ける適格性を有することを意味するにとどまり、営業秘密を受領した者にとって価値があるか否かは問われないからです。
もっとも、当然のことながら、受領者にとって価値のない情報は使用する余地はないはずです。例えば、仮に、L社がノズルのヒータの設定温度を実験記録の数値と同じ198℃に設定したとしても、異なる作業環境(気温等)、異なる製造設備(冷却水槽の大きさ、冷却水の撹拌装置等)を前提とすれば、数字だけが一致していてもK社の影響秘密を使用したことにはならないはずです。しかし、不正競争防止法に営業秘密の「使用」の定義はありません。したがって、裁判所による「使用」の認定は恣意的なものになる可能性があります。
失敗した試作品の製造記録であっても、反面教師としては役に立ったはずだ、と断言された場合に、何を証明したら、「それは違う」といえるのでしょうか。反面教師として利用して製造条件を最適化したのだから、製造を継続すること自体が失敗した製造記録の使用に該当すると裁判所が認定することをどのようにしたら防げるのでしょうか。
上述した仮想の「後日談」におけるL社はどうしたらよかったのでしょうか。その点を考えてみましょう。
7.記録を残すことの重要性
前述のとおり、L社の技術者は職人気質でした。製造装置を前にして、ポンプのスクリューを駆動するモータやヒータの調節つまみを握り、もう少し速く、もう少し高くなどと勘を頼りに製造条件を最適化したでしょう。それは、長年にわたって身に付けた職人の勘ですから、それを数値で表して記録に残すなどということは思いもつかなかっただろうと思います。
しかし、失敗した試作品の製造記録を利用しなかったという事実を直接に証明することは不可能ですから、裁判所を説得しようと思ったら、具体的に、スクリューの回転数や、ヒータの設定温度を記録して、どのようにして製造条件を最適化していったかを記録によって示す必要があります。そうすれば、その記録とK社から無理やりに受け取らされた製造記録を比較することによって、製造記録に記載された数値とは無関係に試行錯誤の過程が進行したことを証明できたかもしれません。例えば、L社が現場の作業日報に、「〇月〇日、ヒータの設定温度決定予備試験、ヒータの設定温度190℃、くっつかず、ヒータの設定温度200℃、べったりくっつく、ヒータの設定温度195℃、ほぼ良好」などと記録し、その記録を書証として提出できたならば、裁判所も現場のノウハウの実情を理解できたかもしれません。
このように考えると、L社の技術者の職人気質があだになったといえるのではないでしょうか。L社の技術者は自らの技術に自信を持っていましたから、自分たちがK社よりも優れていることを文書によって立証しなければならない事態を想定していませんでした。そんなことは、当然、裁判所が理解してくれることだと信じていたわけです。しかし、現実はそんなに甘くありません。証拠のない事実は存在しないものとして扱われるのが裁判です。
以上の仮想シナリオ「コイルマット事件・後日談」からお分かりのとおり、自分たちのやっていることを記録に残すことは、何も、最先端の技術を開発している現場でのみ意味を持つわけではないのです。他人から営業秘密を盗んだと言われたときに自らを守るのは、プライドではなく、記録なのです。
以上