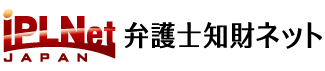営業秘密官民フォーラムメールマガジン掲載コラム 第63回
「示された」の要件について
~第1回及び第2回コラムの追っかけ「訴訟における営業秘密保護・続きの続き」~
弁護士知財ネット常務理事
弁護士・弁理士 小松 陽一郎
弁護士知財ネット近畿地域会事務局
弁護士・弁理士 山崎 道雄
PDF版ダウンロード:[営業秘密官民フォーラムメールマガジン掲載コラム] 第63回 「示された」の要件について ~第1回及び第2回コラムの追っかけ「訴訟における営業秘密保護・続きの続き」~
第1 はじめに
営業秘密の保護は,不正競争防止法2条1項4号から10号まででいろいろなパターンが規定されています。そのうち,同法2条1項7号では,従業員など営業秘密を正当に保有している者が当該営業秘密を不正に利用した場合を規律しています。そして,同号をそのまま引用しますと,「営業秘密を保有する事業者(以下「営業秘密保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において,不正の利益を得る目的で,又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で,その営業秘密を使用し,又は開示する行為」となり,ここで「示された」の要件を満たすことが必要となります。
この「示された」の要件を充足する典型例は,雇用契約関係にある使用者が従業者に対象の営業秘密を開示していた場合です。反対に,従業者が自ら開発したノウハウや自ら収集した顧客情報等(従業員創作型)が対象となる場合には,事業者の物理的な開示行為を介することなく従業者が当該情報に接するため,「示された」の要件を充足するのかについて議論があります。また,例えばA社とB社が共同で創作した営業秘密についてB社が不正利用した場合(事業者共同創作型)も,同様に「示された」の要件を充足しうるのか問題となりえます。
以上のような従業員創作型や事業者共同創作型の事案は,実務上しばしば起こり得る問題であり,そのため,このような場合に「示された」要件を充足することがあるのか,充足するとしていかなる場合かを理解することは実務上重要です。
第1回コラム(小松陽一郎=山崎道雄「営業秘密の特定及び特定の際の留意点――口金ノズル事件」)では,「示された」の要件に関する学説上の議論として,①事実行為説(否定説)-事業者から秘密情報を開示されて取得したという事実がない限り,「示された」の要件を充足しないという考え方,②帰属説-当該営業秘密の本源的保有者により決定するという考え方(本源的保有者が事業者の場合は要件充足),③秘密管理提示説-対象情報について秘密管理性があり,そのことを従業者等に示したか否かで判断する考え方をご紹介しました(https://iplaw-net.com/tradesecret-mailmagazine-column/tradesecret_vol_1)。しかし,この問題は,当コラム第2回(末吉亙「続・口金ノズル事件-前回第1回コラムの追っかけ」)でも分析されているとおり,「古くて新しい」・「簡単な問題なのに難問」な論点です(https://iplaw-net.com/tradesecret-mailmagazine-column/tradesecret_vol_2)。
そこで,本コラムでは,読者の皆様に実務上の参考としていただくべく,「口金ノズル事件」以外の裁判例を5つほどご紹介します。
第2 「示された」要件が問題となった裁判例
1 コーヒーサーバー事件(東京高裁平成12年4月27日判決平成11年(ネ)第5064号等・裁判所ウェブサイト)
【事案の概要】
オフィス・コーヒーサービス事業を行うX社(原告・被控訴人)において,X社と同種の事業を行うY社,その代表取締役Y1及び従業員等Y2~Y5(被告・控訴人)に対し,Y社がX社の顧客情報を利用し,顧客の勧誘をすることは不正競争防止法2条1項7号等に該当するとして,顧客勧誘の禁止や,顧客勧誘によって被った損害の賠償等を求めた事案です。なお,Y1はX社の元取締役でY社を設立した者であり,Y2はX社の元代表取締役,Y3~Y5はX社の元従業員であり,いずれもX社の退任・退職を契機に,Y社での勤務を開始しました。
第一審判決[1]は,X社の顧客情報が営業秘密に該当するとし,短期間に大量の顧客がX社からY社に切り替えられた事実等をもってY社の営業秘密の使用を認定し,不正競争防止法2条1項7号該当性を認め,原告の請求を認容しました。
控訴審判決も,不正競争防止法2条1項7号該当性を認めましたが,対象となった顧客情報は,Y1の人脈やY2らの営業活動を通じて同人らの記憶の中に残されているものであってX社から「示された」ものではない旨のYらの主張に関し,次のとおり,判示しました。
【判決】
「 被控訴人は,その設立時から相当数の顧客を有しており,その後も従業員が新たな顧客を開拓したとき,他人から新たな顧客を紹介されたときは報奨金ないし謝礼を支払い,また,顧客の開拓を担当する者を雇用するなどして顧客の開拓をしてきたのであって,・・・このようにして開拓された顧客の情報は,被控訴人が保有するものである。」
「 しかも,控訴人会社は,・・・何らかの形で整理された顧客情報を,そのようなものとして使用したものと推認せざるを得ない。そうすると,控訴人会社に切り替えられた顧客中に,控訴人Y1の人脈や,Y2,Y3,Y4,Y5らが紹介ないし開拓したものが含まれていたとしても,これらの切替えが,右の者らが被控訴人から示されずに独自に開発し,まだそれを記憶していたもののみを用いて行われたものと認めることはできない。」
「 さらに,本件で控訴人らの責任の根拠とされているのは,顧客情報の不正使用のみではなく,これを一部として含む一連の違法な行為であることは前述のとおりであり,これらは総体として一個の不法行為をなすものと評価することが可能であるから,控訴人らが用いた顧客情報の中に控訴人らの主張する意味で「示された」ものでないものが含まれていたとしても,そのことをもって控訴人らの責任を否定する根拠とすることはできないものというべきである。」
【補足】
本判決は,Y社らの主張を否定する第一の理由として,報奨金・謝礼金の存在や雇用契約の存在から顧客情報の保有者がX社であると認められるという点を挙げています。そのため,②帰属説と整合的と考えられます。
但し,本判決は,Yらの営業活動について,「何らかの形で整理された顧客情報」を使用した事実も認定のうえ,「被控訴人から示されずに独自に開発し,まだそれを記憶していたもののみを用いて行われた」事実を否定していることからすれば,会社から秘密情報を開示されて取得したという事実がない限り,「示された」の要件を充足しないという考え方(上記①事実行為説)からも説明が可能なように考えられます。
2 原価セール事件(東京高裁平成16年9月29日判決平成14年(ネ)第1413号・裁判所ウェブサイト)
【事案の概要】
医薬品等の製造販売等を業とするX社(原告・控訴人)において,ドラッグストアを経営するY社及びその代表者であるY1(被告・被控訴人)に対し,Y社がX社の営業秘密である商品の仕入価格を開示して「原価セール」を行ったことは不正競争防止法2条1項7号の不正競争行為である等として,損害賠償等を求めた事案です。対象となった営業秘密は,Y社がX社から仕入れた商品代金であり,Y社は,「仕入価格」との表示のもと,当該代金をチラシに記載する等して,一般消費者に開示しました。
第一審判決[2]はX社の請求を棄却し,控訴審判決も,「示された」の要件を充足しない等として,控訴を棄却しました。
【判決】
「 被控訴人Y社が一般消費者に開示したのは,被控訴人Y社が販売しようとしている控訴人商品の仕入価格,つまり,控訴人と被控訴人Y社との間における控訴人商品の売買代金額である。いうまでもなく,売買代金額は,売買契約の主要な要素の一つであり,契約当事者が合意することにより形成されるものである。本件においても,控訴人と被控訴人Y社が卸し・仕入れとして,売買代金額(控訴人にとっての卸価格,被控訴人Y社にとっての仕入価格)を合意したことにより,仕入価格という情報が成立し,双方が保有することになったのであり,控訴人が保有していたものが被控訴人Y社に「示された」ものでないことは明らかである。」
「 なお,・・・控訴人があらかじめ一定の金額を定め,被控訴人Y社としては,この金額を受入れるか否か,受け入れればその金額で仕入れをし,受け入れられなければ当該商品の仕入れをしないという取引形態になっていることがうかがえないではない。しかし,仮に,本件仕入れがこのような形態でされたものであったとしても,被控訴人Y社の意思により,控訴人が定めた金額で合意して売買契約が成立していることに変わりはないのであって,両者の意思の合致により,売買契約が成立し,その要素である売買代金額(仕入価格)も成立したものであることに変わりはない。
したがって,控訴人があらかじめ売り渡す価格を定め,被控訴人Y社にそれを示して,売買契約に至ったものであるとしても,控訴人があらかじめ定めた価格が売買契約の要素である売買代金額といえるものではなく,あくまでも控訴人として売り渡す予定価格であると評価されるべきものである。このことは,上記予定価格が値引きなどの交渉が許されないものとして運用されており,結果的に,控訴人のあらかじめ定めた価格(予定価格)が成立した売買契約の代金額と一致することになるとしても,変わりはない。ちなみに,被控訴人Y社は,本件において,「原価セール」の原価が控訴人があらかじめ定めた価格と一致しているということを開示したわけではないし,競争関係にある販売店の仕入価格(売買代金額)を控訴人から示されて,それを開示したりなどしたわけでもない。」
「 以上のとおり,本件は,不正競争防止法2条1項7号によって規律することができない事案であるというほかないのであって,仕入価格の営業秘密性に関するその余の要件について判断するまでもなく,被控訴人Y社の本件仕入価格の開示行為は,不正競争防止法2条1項7号所定の不正競争行為には該当しない。」
【補足】
本判決は,対象となった仕入価格がX社及びY社の合意により形成されたことをもって「示された」要件の充足を否定しています。営業秘密の帰属やその秘密管理性について特段の言及はなく,上記3つの見解のうちいずれに属するかは判然としませんが,事業者共同創作型における事案として参考になると思われます[3]。
3 印刷受発注情報事件(東京地裁平成24年6月11日判決平成22年(ワ)第23558号・裁判所ウェブサイト)
【事案の概要】
印刷物やHPのデザイン等を業とするX社(原告)において,X社の営業担当者であり,退職後にY社に就職したY1がX社の営業秘密である顧客情報等を開示・使用等した行為が不正競争防止法2条1項7号,同8号等に該当する等として,Y社・Y1らに対し,当該顧客情報の利用等の差止及び損害賠償請求等をした事案です。
判決は,雇用契約上の債務不履行及び不法行為責任を認めて請求を一部認容しましたが,不正競争防止法に関する点は,顧客情報を持ち出して利用した行為が認められないとして,請求を認めませんでした。
X社は,Y1らのY社での営業活動が手控え等に基づいてなされたものだとしても,それも営業秘密の利用にあたる旨主張しましたが,判決は,以下のとおり,当該主張を排斥しました。
【判決】
「 ・・・原告は,新就業規則において,就業中に得た取引会社の情報につき漏えいすることや,取引先,顧客等の関係者の個人情報を正当な理由なく開示し,利用目的を超えて取扱い,または漏えいすることを退職後も禁ずる旨規定している。上記新就業規則は,・・・全従業員に対し周知する手続がとられていたものとみることができ,従業員に対する法的拘束力を有するものであるということができる。」
「 しかし,本件顧客情報のうち,顧客の氏名,電話番号等の連絡先に係る部分については,被告Y1等の営業担当者が営業活動を行い,取得して事業主体者たる原告に提供することにより,原告が保有し蓄積することとなる性質のものであって,営業担当者が複数回にわたり営業活動を行うことなどにより,当該営業担当者と顧客との個人的信頼関係が構築され,または個人的な親交が生じるなどした結果,当該営業担当者の記憶に残るなどして,当該営業担当者個人に帰属することとなる情報と重複する部分があるものということができる。そうすると,このような,個人に帰属する部分(個人の記憶や,連絡先の個人的な手控えとして残る部分)を含めた顧客情報が,退職後に当該営業担当者において自由な使用が許されなくなる営業秘密として,上記就業規則所定の秘密保持義務の対象となるというためには,事業主体者が保有し蓄積するに至った情報全体が営業秘密として管理されているのみでは足りず,当該情報が,上記のような個人に帰属するとみることのできる部分(個人の記憶や手控えとして残る部分)も含めて開示等が禁止される営業秘密であることが,当該従業員らにとって明確に認識することができるような形で管理されている必要があるものと解するのが相当である。」
「 ・・・原告における顧客情報の管理体制は,顧客の連絡先の手控え等までもが,雇用契約上開示等を禁じられるべき営業秘密に当たることを当該従業員らに明確に認識させるために十分なものであったとはいえず,・・・原告は,本件顧客情報に関し,債務不履行又は不法行為の主張に加え,不正競争防止法2条1項4号又は7号所定の不正競争が成立する旨も主張するが,・・・被告Y1が保有していた情報については,営業秘密とは認められない以上,上記各号所定の不正競争の成立を認める余地はない。」
【補足】
本判決は,不競法2条1項7号該当性を否定するにあたり,対象情報が営業秘密でないこと等を理由としており,「示された」要件について直接言及するものではありません。もっとも,雇用契約上の義務違反の有無に関する判示部分ではありますが,顧客情報のうち担当者の記憶や手控え等に残った情報について,担当者個人にも帰属することを認めながらも,当該情報が秘密保持義務の対象となることを明確に認識できるような措置を講じることによって,責任が認められる余地があるとしている点が注目されます(不正競争防止法の観点からは②帰属説よりも③秘密管理提示説に近いものと考えられます。)。
4 投資用マンション事件(知財高裁平成24年7月4日判決平成23年(ネ)第10084号等・裁判所ウェブサイト)
【事案の概要】
投資用のマンションの販売等を業とするX1社(原告・被控訴人兼附帯控訴人)とその子会社であるX2社が,Y1及びY2において,Xらの営業秘密である顧客情報をY社で使用等した行為が不正競争防止法2条1項4号,同7号,同8号等に該当するとして,Y1ら(被告・控訴人兼附帯被控訴人)に対し,損害賠償を求めた事案です。Y1及びY2は,X1社の元営業部課長ないし元営業部員であり,X2社の業務をも担っていたものの,X1社を退職した後,Y社(Y1が代表取締役)において,X1社らの顧客情報を使用しました。
第一審判決[4]は,顧客情報についての不正競争行為を認定し,原告の請求を一部認容しました。本判決も,原審と同様に原告の請求を認容しましたが,営業秘密の帰属等に関し,次のとおり判示しました。
【判決】
「 1審原告X1社から投資用マンションを購入して1審原告X2社に賃貸管理を委託した顧客の氏名,年齢,住所,電話番号,勤務先名・所在地,年収,所有物件,借入状況,賃貸状況等から構成される情報(以下「本件顧客情報」という。)は,いずれも1審原告らの従業員が業務上取得した情報であるから,これを従業員が自己の所有する携帯電話や記憶に残したか否かにかかわらず,勤務先の1審原告らに当然に帰属するというべきである。
・・・1審原告らは,互いに一致協力することで投資用マンションにより投資の実を挙げようとする顧客の需要に応じているものであって,1審原告X1社の有する本件顧客情報は,当然に1審原告X2社の業務にも必要なものであって,かつ,投資用マンションの売買契約及び賃貸管理委託契約の一方の当事者である顧客も,これを当然了解しているものである。以上のような1審原告らの関係によれば,1審原告らは,本件顧客情報を相互に提供することで顧客の需要に応じているものと認められ,本件顧客情報は,1審原告らのうちのいずれの従業員が取得したかを問わず,1審原告ら双方に帰属するものといえる。」
「 以上に対して,1審被告らは,1審原告X1社の従業員が全ての営業先の連絡先を得ていたわけではなく,独自の経済的負担で営業活動をしていたばかりか,業務上知り得た情報が全て勤務先に帰属すると解することが職業選択の自由を著しく制限するから,1審原告X1社の顧客情報がその元従業員であった1審被告Y1及び同Y2にも帰属する旨を主張する。
しかしながら,・・・その業務遂行に当たって独自の経済的負担があったからといって,1審原告X1社の従業員は,直ちに本件顧客情報の帰属主体となるものではないし,1審原告らの事業内容及びそこにおける本件顧客情報の重要性に照らすと,本件において1審原告X1社の従業員が業務上知り得た情報が1審原告らのみに帰属したとしても,憲法の規定を踏まえた私法秩序に照らして1審原告X1社の従業員の職業選択の自由を看過し難い程度に著しく制限するものとまでは評価できない。」
「 ・・・1審原告らは,その双方の従業員に対して本件顧客情報を含む営業秘密の管理について研修等を実施しており,・・・本件顧客情報は,1審原告らに帰属しているものである以上,1審原告X1社の営業部所属の従業員又は元従業員(1審被告Y1及び同Y2を含む。)は,いずれも,1審原告X1社に対して,本件就業規則に基づき本件顧客情報についての秘密保持義務を負うほか,併せて,1審原告X2社の代理人又は使者としての善管注意義務に基づき,1審原告X2社のために賃貸管理委託契約の締結に当たり開示される本件顧客情報について,秘密保持義務を負うものと解するのが相当である。」
「 (筆者注:不正競争防止法2条1項7号の成否に関し)前記2に認定のとおり,1審原告X1社の営業部所属の従業員は,1審原告X2社からも本件顧客情報を開示されて取得しているものといえる。
したがって,1審被告Y1及び同Y2が1審原告X2の営業秘密である本件顧客情報を取得したのは,1審原告X2社から示されたことによるというべきである。」
【補足】
本判決は,「示された」要件を充足する理由が明記されていませんが,対象となった顧客情報がX社らに帰属すると認定しており,②帰属説を採用していると考えられます。但し,Y1らがX2社から顧客情報を「開示されて取得している」ことを認定する前提として,営業秘密の管理体制等についても言及していることから,③秘密管理提示説からも説明ができそうです[5]。
5 医薬品配置販売事件(大阪地裁平成30年3月5日判決平成28年(ワ)第648号・裁判所ウェブサイト)
【事案の概要】
A社から医薬品配置販売業の事業譲渡を受けたX社において,いずれもA社の元従業員であり,A社退職後に競合会社である被告Y社の代表者又は一員となった3名(Y1~Y3)がA社から示された顧客情報を不正使用したとして不正競争防止法2条1項7号該当性等を主張して,損害賠償等を求めた事案です。
判決は,一部の被告について同7号該当性等を認めX社の請求を一部認容しましたが,「示された」の要件に関して,被告らが対象顧客情報の保有者はA社とY1~Y3であると主張したのに対し,次のとおり判示しました。
【判決】
「 被告らは,被告ら3名が平成26年7月31日にA社を退職するまで,A社とともに,被告ら3名も同顧客情報の保有者であったと主張する。しかし,被告ら3名は,A社の従業員として稼働していた者であり,A社の営業として顧客を開拓し,医薬品等の販売を行うことによってA社から給与を得ていたものであり,被告ら3名が営業部員として集めた情報は,A社に報告され,A社の事務員がデータ入力して一括管理していたのである。そうすると,実際に顧客を開拓し,顧客情報を集積したのは被告ら3名であっても,それは,被告ら3名がA社の従業員としての立場で,A社の手足として行っていたものにすぎないから,被告ら3名が集積した顧客情報は,A社に帰属すべきものというべきであり,被告ら3名が独自に顧客情報の保有者となり得る地位にあったとは認められない。
したがって,廻商リストやルート一覧として配布された情報はもとより,そのおおもとである,被告Y1自身が集積した顧客情報を含むA社の懸場帳そのものについても,被告ら3名の保有する情報ではなく,A社から示された情報というべきである。」
【補足】
本判決は,Y1らはA社の従業員であったこと,顧客情報はY1らが従業員として収集しA社に報告のうえ,A社が管理していたこと等をもって,A社の手足にすぎないとして顧客情報がA社に帰属すると認定しており,②帰属説を採用していると考えられます。
第3 まとめ
「示された」の要件が問題となった裁判例の代表例は以上のとおりであり,多くは,②帰属説又は③秘密管理提示説と同様の立場を採用していると考えられます。
第1回コラムでご紹介した「口金ノズル事件」も,営業秘密の帰属について言及した点で②帰属説に近く,また,③秘密管理提示説を採用したと捉える見解もあります[6]。但し,この問題について具体的に言及した最高裁判決はなく[7],学説上は,①事実行為説も有力です。
この点については,営業秘密を保有する事業者の視点で,
①事業者にとっては必ずしも有用とはいえない事実行為説からは,従業員創作型や事業者共同創作型の営業秘密について法的保護が一切及ばないのかというとそうではなく,同説は,守秘義務契約等による契約責任を排斥するものではありません。そのため,この見解も存在することを意識した事業者の対策としては,就業規則や守秘義務契約等の作成・管理,及び,従業員教育の実施等の秘密管理性要件充足でも要求される手段を徹底することが有効策となりそうです(なお,コーヒーサーバー事件を参考にする限り,事実行為説のもとでも,従業員が収集した情報-旧情報について,事業者において他の情報と結合するなどして加工し新たな媒体に記録して新情報とし,これを従業員に示したうえ,当該従業員が新情報を不正利用したことを立証できれば,要件充足となる余地がありそうです。)。
また,
③秘密管理提示説でも,対象情報の秘密管理を行い,当該事実を従業員に認識可能にする措置を講ずるべきということとなるので,いずれにせよ守秘義務契約等の作成・管理,及び,従業員教育の実施等が重要な対策となります。
一方,
②帰属説においては,営業秘密の帰属の基準となる具体的な条項がなく[8],帰属の予測可能性に乏しい側面があります。上記裁判例では,従業員創作型について比較的緩やかに事業者に営業秘密の帰属を認めているものもありますが,下級審の事例判断ですので同種事案で再び適用されるとは限りません。また,事業者共同創作型になると,事業者同士が物的・人的資源を投入して営業秘密が形成されますので,帰属が認められるハードルも上がるように思われます。ただ,対従業員との雇用契約又は対外部事業者との契約において,創作される情報の帰属を明記することは,帰属を決する重要な証拠となり得るところですし,仮に不正競争防止法上の請求が認められないとしても契約責任を問いうるという点で有効策だと考えられます。
以上のとおり,「示された」要件を巡っては,なかなか難しい問題を含み,現在でも裁判実務が確立しているとは言いがたい状況ですので,あらためて予防法務としての契約実務の重要性を痛感させられるところです。
以上
[1] 横浜地裁平成11年8月30日判決平成7年(ワ)第2513号,平成8年(ワ)第145号・LEX/DB28052748。
[2] 東京地裁平成14年2月5日判決平成13年(ワ)第10472号・判タ1114号279頁。
[3] なお,事実行為説の立場から本判決の結論を批判する見解もあります。田村善之「商品の仕
入価格と不正競争防止法2条1項7号の保護の成否―「原価セール」事件」(判例タイムズ11
73号68頁)。
[4] 東京地裁平成23年11月8日判決平成21年(ワ)第24860号・裁判所ウェブサイト
[5] 山根崇邦「不正競争防止法2条1項4号・7号の規律における時間軸と行為者の認識の構造」(特許研究No57 43頁以下)を参照。
[6] 上掲5山根。
[7] 但し,原価セール事件では,上告棄却ないし上告受理申立てに対する不受理決定がなされている(最高裁平成17年10月13日判決平成17年(オ)第27号等・LEX/DB25568575)。
[8] 第2回コラムでは,技術上の情報について,特許法35条の職務発明要件の充足により,規範的に「示された」要件を充足するとする考え方が示唆されています。