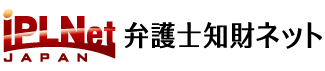弁護士知財ネット
弁護士 吉原 祐介
PDF版ダウンロード:[営業秘密官民フォーラムメールマガジン掲載コラム] 第80回 産総研事件(東京地判令和7年2月25日(令和5年特(わ)第1278号不正競争防止法違反被告事件))を題材にした秘密管理性の検討
第1 はじめに
本稿では、営業秘密に関する近時の裁判例である産総研事件(東京地判令和7年2月25日(令和5年特(わ)第1278号不正競争防止法違反被告事件))を紹介し、その後、営業秘密の要件のうち、秘密管理性にフォーカスして検討を行うものとする。
第2 事案の概要
国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「産総研」という。)において上級主任研究員として勤務し、材料・化学領域触媒化学融合研究センター革新的酸化チームにおいて、低環境負荷型フッ素材料の開発等に関する研究に従事していた被告人が、産総研の研究成果であるへプタフルオロイソブチロニトリル(化学式「C4F7N」。以下「C4」という。)の合成技術情報(以下「本件ノウハウ」という。)が記録されたファイルデータ(以下、単に「ファイル」という。)を、中華人民共和国(以下、単に「中国」という。)所在のB社の従業員宛てにメールに添付して送付し、産総研の営業秘密を開示したとして不正競争防止法違反に問われた事案である。
第3 判旨の概要
1 結論
判決は、本件ノウハウが営業秘密に当たるとして、営業秘密侵害罪の成立を肯定した。
本件の争点は多岐にわたるが、以下、判決における産総研に関する認定に触れた上で、本件ノウハウの営業秘密該当性に絞って紹介する。
2 産総研に関する認定
産総研は、国立研究開発法人産業技術総合研究所法(以下「産総研法」という。)等に基づいて、「鉱工業の科学技術に関する研究及び開発等の業務を総合的に行うことにより、産業技術の向上及びその成果の普及を図り、もって経済及び産業の発展…に資することを目的」(産総研法3条)として設立された国立研究開発法人(産総研法4条、独立行政法人通則法2条3項)であって、その職員等は職務上知ることのできた秘密の漏示・盗用を禁じられており、その秘密保持義務違反等の罰則の適用については法令により公務に従事する職員とみなされる(産総研法10条の2、10条の3、14条)。
3 営業秘密該当性
(1)秘密管理性
ア 産総研における研究成果物等の取扱い
産総研法及び規則は、産総研職員に対し、職務上得られた秘密に関する守秘義務を定め、成果物規程は、全ての研究成果物等について秘密保持義務を定め、各職員において研究成果物等を秘密として厳重に管理すべきこと、公表したり第三者に提供したりする場合には産総研の承認が必要であることなどを明記している。さらに、産総研では、研究成果物の秘密管理を徹底するため、職員以外が立ち入ることができないよう研究施設を施錠するほか、職員固有のパスワードを入力しなければ産総研が貸与するパソコンを使用できないようにするなど秘密が漏洩しないための措置がなされていた。
以上によれば、産総研は、研究成果物等全般について包括的に秘密管理意思を有しており、これは、産総研に所属する各研究者が職務として従事する日常的な研究の過程で得られた産総研に帰属する研究成果物等を産総研の国立研究開発法人としての性質に沿って我が国の公益のために最大限の研究成果物等を確保するための合理的な秘密管理の方法であるといえる。
そして、産総研では、職員全員に秘密保持に関する研修の受講を義務付け、成果物規程や規則が定める秘密保持義務の内容や秘密として管理されるべき研究成果物等の範囲や秘密管理の方法等について周知を徹底していた。また、研究成果物等の定義についても上記のとおり明確に成果物規程で示されていた。産総研の職員は、産総研が研究成果物等について秘密として管理する意思があることも、その研究成果物等の対象範囲についても明確に認識できる状況にあったといえる。
したがって、産総研の研究成果物等である本件ノウハウについても、秘密管理性を有するといえる。
また、これらが規則や成果物規程に記載されていることや上記研修を被告人も受講していること、被告人自身が産総研での長期間にわたる研究の結果、特許ないし営業秘密に当たる種々の研究成果物等を得た経験があり、研究成果物等の産総研での取扱い方法等を熟知していたと考えられること等からすれば、被告人にこの点の認識があったことは明らかである。
イ 弁護人の主張
弁護人は、秘密管理意思としては、情報一般についての管理意思では足りず特定の情報の秘密管理意思が必要であるところ、本件当時、産総研は、本件ノウハウもC4の研究の存在自体すらも把握しておらず、内部調査後に初めてその存在を認識したのだから、産総研に本件ノウハウの秘密管理意思は存在せず、また、本件ノウハウに機密であることが付記されてないから、秘密管理意思についての客観的な認識可能性も認められないなどと主張する。
しかし、弁護人の主張は、いわゆる職務発明ないし事業者が保有する営業秘密について使用者等に秘匿して従業者等がし又は取得した場合は使用者等が何らの権利を有しないとする点で関連法規(特許法35条、不正競争防止法2条1項4号、7号等)にそぐわない独自の見解といわざるを得ない。本件においては、上記の規程等が全ての研究成果物等について、産総研の把握の有無を問わず、これらを産総研に帰属させて研究者に秘密として管理させる意思が客観的に示されていることは明らかで、これが産総研の国立研究開発法人としての性質に沿った合理的な秘密管理の方法であることは既に述べたとおりであり、産総研に個別の成果物の具体的な認識があることは秘密管理性の前提となるという主張は採用できない。一般に、営業秘密に当たる研究成果物等は産総研との雇用契約に基づき適用される成果物規程により原始的に産総研に帰属するから、当該研究成果物等の発生を職務上認識していればその職員は「営業秘密を保有者から示された者」に当たるのであって、産総研職員等が秘密性の明認を怠ったとしても秘密管理性に影響を及ぼすことはない。
(2)非公知性
本件ノウハウと同様の合成技術が記載された論文等の文献や特許は一般に知られていなかったから、本件ノウハウは、本件当時において、非公知性があったといえる。なお、本件ノウハウは第1工程と第2工程を気相法により連続的に実施できる点や第3工程において生成物と副生成物を分離しなくてよい点、最も効率的な反応条件を検討している点などで特許cと異なる有用性があるから、特許cが本件ノウハウの非公知性に影響を及ぼすものではない。
弁護人は、本件ノウハウに添付されたNMRスペクトル図は、産総研の機器を利用して作成されたにせよ、平成30年1月頃のB社の研究状況紹介資料や報告書等に掲載されたものを流用しており、非公知性がない旨の主張をする。しかし、弁護人指摘の流用があったとしても、同図は本件ノウハウの一部にすぎないから、本件ノウハウ自体の非公知性は否定されない。
したがって、本件ノウハウには営業秘密の要素としての非公知性が認められる。
(3)有用性
有用性については、判決が認定した前提事実から明らかに認められること、また、弁護人も明示的に争っていないとして肯定された。
(4)小括
以上より、判決は、本件ノウハウの営業秘密該当性を肯定し、その余の要件も充足するとして、営業秘密侵害罪の成立を認めた。
第4 検討
1 秘密管理性について
営業秘密とは、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」(不正競争防止法2条6項)をいい、秘密管理性、非公知性及び有用性がその3要件とされている。
本稿でフォーカスする秘密管理性について、営業秘密管理指針は、以下のとおり記載している。
「秘密管理性要件が満たされるためには、営業秘密保有者が当該情報を秘密であると単に主観的に認識しているだけでは不十分である。
すなわち、営業秘密保有者の秘密管理意思(特定の情報を秘密として管理しようとする意思)が、具体的状況に応じた経済合理的な秘密管理措置によって、従業員に明確に示され、結果として、従業員が当該秘密管理意思を容易に認識できる(換言すれば、認識可能性が確保される)必要がある。」
「秘密管理性要件は、従来、①情報にアクセスできる者が制限されていること(アクセス制限)、②情報にアクセスした者に当該情報が営業秘密であることが認識できるようにされていること(認識可能性)の2つが判断の要素になると説明されてきた。しかしながら、両者は秘密管理性の有無を判断する重要なファクターであるが、それぞれ別個独立した要件ではなく、「アクセス制限」は、「認識可能性」を担保する一つの手段であると考えられる。したがって、情報にアクセスした者が秘密であると認識できる(「認識可能性」を満たす)場合に、十分なアクセス制限がないことを根拠に秘密管理性が否定されることはない(東京高判平成29年3月21日判タ1443号80頁参照)。
もっとも、従業員等がある情報について秘密情報であると現実に認識していれば、営業秘密保有企業による秘密管理措置が全く必要ではないということではない。法の条文上「秘密として管理されている」と規定されていることを踏まえれば(法第2条第6項)、何らの秘密管理措置がなされていない場合には秘密管理性要件は満たさないと考えられる。」
この記載からすれば、秘密保持に関する規程等の取決めやアクセス制限等の秘密管理措置がなされていることを前提に、これによる秘密管理意思の表明の程度を踏まえて、従業員が当該秘密管理意思を認識できたか否かがポイントであると考えられる。
2 「技術情報」と「営業情報」の違いが秘密管理性の判断に影響するか
営業秘密となりうる秘密情報は、研究開発情報等の「技術情報」と顧客名簿等の「営業情報」に大きく分けることができる。
この「技術情報」と「営業情報」の違いが秘密管理性の認定に影響を及ぼすかについて、名古屋高判令和3年4月13日は、以下のとおり判示している。
「秘密管理性が営業秘密の要件とされている趣旨は、保有者において秘密として管理しようとする情報の範囲を従業員等に対して明確化することにより、従業員等の予見可能性、ひいては、経済活動の安定性を確保することにあるところ、顧客名簿のように集合体となった情報が秘密として管理されている場合、個々の顧客情報の収集に当たった従業員にとって、名簿を構成する顧客情報の相当部分は自ら収集し、日常的にアクセスしている情報であることからすれば、そうした従業員による営業秘密の侵害が問題となる事案において、情報の集積結果である顧客名簿等のみならず個々又は一部の顧客情報についても営業秘密であると認めるためには、どのような顧客情報を秘密情報とするかという事業者の秘密管理意思が秘密管理措置によって従業員に明確に示され、その認識可能性が確保される必要があるといえる。これに対して、本件のような技術情報に係る営業秘密は、直接開発に従事した従業員はもとより、そのような情報へのアクセスを許可された従業員も、事業者が当該情報を秘密として管理し外部への漏えいを禁じる意思や利益を有していることやその範囲を容易に認識し得るといえることからすれば、顧客情報等のようにどのような情報を秘密情報とするかを明確にする管理措置を問題にする必要はないものというべきである。」
この裁判例では、営業情報である顧客名簿を構成する個々の顧客情報については、従業員が自ら収集し日常的にアクセスしている情報であることから、どのような顧客情報を秘密情報とするかにつき秘密管理意思が秘密管理措置によって従業員に明確に示され、その認識可能性を確保する必要があると判示された。その一方、技術情報に係る営業秘密の場合は、直接開発に従事した従業員のみならずその情報へのアクセス権限を有する従業員も、当該情報に係る秘密管理意思とその範囲を容易に認識し得るとして、顧客情報等のようにどのような情報を秘密情報とするか明確にする秘密管理措置を問題にする必要はないと判示されている。
この裁判例を前提とすると、少なくとも、顧客情報のような従業員が日常的にアクセスするような営業情報については、当該情報を秘密情報とするのであれば、秘密管理措置によってどの情報を秘密情報とするのかについての秘密管理意思を明確に示しておく必要があるということになろう。他方で、技術情報については、上記判示事項には明確な記載はないものの、一般的に、その会社の企業活動に直結する重要なものであり秘匿性の高いものであることから、厳格な秘密管理措置を要求しなかったものと考えられる。
3 産総研事件の検討
(1)産総研事件における秘密管理性肯定のロジック
ア 秘密管理措置の認定
本判決は、まず、産総研による秘密管理措置につき、
- 産総研法及び規則が産総研職員に対して職務上得られた秘密に関する守秘義務を定めていること
- 産総研の成果物規程が全ての研究成果物等について秘密保持義務を定めていること
と、産総研法等において守秘義務や秘密保持義務が定められている点を認定するとともに、
- 産総研が職員以外が立ち入ることができないよう研究施設を施錠していたこと
- 職員固有のパスワードを入力しなければ産総研が貸与するパソコンを使用できないようにしていたこと
と研究成果物等に対するアクセス制限を講じていた点を認定した。
そして、産総研は、上記秘密管理措置により、研究成果物等全般について包括的に秘密管理意思を有していると認定するとともに、上記秘密管理措置につき、「産総研に所属する各研究者が職務として従事する日常的な研究の過程で得られた産総研に帰属する研究成果物等を産総研の国立研究開発法人としての性質に沿って我が国の公益のために最大限の研究成果物等を確保するための合理的な秘密管理の方法である」と認定した。
イ 秘密管理意思の認識可能性についての認定
本判決は、次に、秘密管理意思に係る従業員の認識可能性につき、
- 職員全員に秘密保持に関する研修の受講を義務付け、成果物規程や規則が定める秘密保持義務の内容や秘密として管理されるべき研究成果物等の範囲や秘密管理の方法等について周知を徹底していたこと
- 研究成果物等の定義についても上記のとおり明確に成果物規程で示されてい たこと
を認定し、産総研の職員は、産総研が研究成果物等について秘密として管理する意思があることも、その研究成果物等の対象範囲についても明確に認識できる状況にあったと認定した。
ウ 小括
以上のとおり、本判決は、産総研が講じている秘密管理措置により、産総研の職員に対して、産総研に帰属する研究成果物等全般につき包括的に秘密管理意思が示されており、産総研としても、研究成果物等の定義を成果物規程において明示した上、成果物規程等で定めた秘密保持に関する研修の受講を義務付けていることからすれば、職員の認識可能性もあったとして、本件ノウハウに関する秘密管理性を肯定した。
(2)弁護人の主張と本判決による排斥
本件において、弁護人は、以下の事情から、秘密管理性は否定されるべきとの主張を行っていた。
①秘密管理意思につき、情報一般についての管理意思では足りず、特定の情報の秘密管理意思が必要であるところ、本件当時、産総研は、本件ノウハウもC4の研究の存在自体すらも把握していなかったことを理由に、産総研には、本件ノウハウに関する秘密管理意思は存在しなかったこと
②本件ノウハウに機密であることが付記されていないこと
これに対し、本判決は、上記弁護人の主張が「いわゆる職務発明ないし事業者が保有する営業秘密について使用者等に秘匿して従業者等がし又は取得した場合は使用者等が何らの権利を有しないとする点で関連法規(特許法35条、不正競争防止法2条1項4号、7号等)にそぐわない独自の見解といわざるを得ない。」とこれを排斥した。具体的には、
【上記①の主張に対して】
「上記の規程等が全ての研究成果物等について、産総研の把握の有無を問わず、これらを産総研に帰属させて研究者に秘密として管理させる意思が客観的に示されていることは明らかで、これが産総研の国立研究開発法人としての性質に沿った合理的な秘密管理の方法であることは既に述べたとおりであり、産総研に個別の成果物の具体的な認識があることは秘密管理性の前提となるという主張は採用できない。」
【上記②の主張に対して】
「一般に、営業秘密に当たる研究成果物等は産総研との雇用契約に基づき適用される成果物規程により原始的に産総研に帰属するから、当該研究成果物等の発生を職務上認識していればその職員は「営業秘密を保有者から示された者」に当たるのであって、産総研職員等が秘密性の明認を怠ったとしても秘密管理性に影響を及ぼすことはない。」
と判示した。
(3)産総研事件における秘密管理性判断の特徴
本判決は、秘密管理措置につき、「産総研の国立研究開発法人としての性質に沿って我が国の公益のために最大限の研究成果物等を確保するための合理的な秘密管理の方法」とした上で、産総研が具体的に認識していない研究成果物等についても包括的な秘密管理意思を認めた点に特徴があると考えられる。
国立研究開発法人については、独立行政法人通則法2条3項に定義があり、「公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中長期的な視点に立って執行することが求められる科学技術に関する試験、研究又は開発(以下「研究開発」という。)に係るものを主要な業務として国が中長期的な期間について定める業務運営に関する目標を達成するための計画に基づき行うことにより、我が国における科学技術の水準の向上を通じた国民経済の健全な発展その他の公益に資するため研究開発の最大限の成果を確保することを目的とする独立行政法人として、個別法で定めるもの」とされている。
ここにいう個別法とは、産総研法であり、産総研の目的については、産総研法第3条において、
第3条
「国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)は、鉱工業の科学技術に関する研究及び開発等の業務を総合的に行うことにより、産業技術の向上及びその成果の普及を図り、もって経済及び産業の発展並びに鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保に資することを目的とする。」
と定められているほか、役員及び職員の秘密保持義務については、同法第10条の2において、
第10条の2
「研究所の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。」
と定められている。
本判決は、詳細には述べていないものの、上記のような産総研の性質や産総研に関する規定ぶりを踏まえて、産総研の秘密管理の方法につき、合理的であると判示したと考えられる。
(4)本件が民間企業における事案だった場合、同様の判断となったのか
本判決は、前記のとおり、産総研の性質等を踏まえて秘密管理性が判断された点が特徴と考えられるが、仮に、本件が産総研ではなく民間企業において発生した事案であった場合、本判決と同様の結論となったのか。
この点につき、前記名古屋高判では
「技術情報に係る営業秘密は、直接開発に従事した従業員はもとより、そのような情報へのアクセスを許可された従業員も、事業者が当該情報を秘密として管理し外部への漏えいを禁じる意思や利益を有していることやその範囲を容易に認識し得るといえることからすれば、顧客情報等のようにどのような情報を秘密情報とするかを明確にする管理措置を問題にする必要はない」
と判示されていた。
もっとも、前記名古屋高判は、営業秘密に係る個別の技術情報についての事業者による具体的な認識をも不要であり、包括的な管理意思で足りるとまでは述べていない。
この点については、民間企業における就業規則や秘密保持契約書等の取決めにおいて、事業者の把握の有無を問わず、研究成果物等を事業者に帰属させる旨規定さえすれば、当該技術情報に係る具体的な認識が不要であり、本件のように包括的な秘密管理意思を認定できるのか、それとも、異なる判断となったのか、この点については、今後の研究や裁判例の蓄積が待たれるところであると考える。