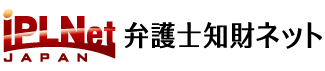営業秘密官民フォーラムメールマガジン掲載コラム 第4回
失敗事例から学ぶ営業秘密管理
弁護士知財ネット事務局
弁護士 星 大介
PDF版ダウンロード:[営業秘密官民フォーラムメールマガジン掲載コラム] 第4回 失敗事例から学ぶ営業秘密管理
1 はじめに - 知財戦略と営業秘密 -
「知的財産戦略(知財戦略)が重要」と言われて久しいですが、そもそも知財戦略とは何でしょうか?様々な定義や考え方があると思いますが、分かりやすくいうと、「会社(事業)の強みを見つけること」だと考えることができます[1]。そのような知財戦略を検討することは、まさに、会社の中のあらゆる資産の中で、会社(事業)の成長の武器となる強みを見つけていく作業にほかなりません。
「知財戦略」というと、「ウチの会社は製造業じゃないから知財は関係ない。」、「ウチは下請けだから知財とか言っても仕方ない。」、「会社にとってはコツコツと人財を育てることが大事で、そんなアイデア1つで儲けようなんて考えはない。」といった知財に否定的なご意見をお聞きすることがあります(本メールマガジンの読者の皆様はそんなことはないと思いますが。)。
しかし、自社のビジネスを支えている要素を見てみると、そこには、顧客から高い評価を得ているサービスのマニュアルや、他社よりも安価での商品の販売を支えている仕入情報、顧客の細かいニーズまで把握している取引先(顧客)情報、実は元請会社が重要視している自社の加工技術、長年受け継がれてきた人財の育て方(技術等の伝承)など、重要な知的資産の存在が見つかったりするのではないでしょうか。これらのマニュアルや仕入情報、顧客情報、加工技術、技術の伝承方法等は、特許することはできなかったり、特許にすることが適当でない情報であったりします。また、製造業で多数の特許を有しているような会社であっても、重要な差を生み出す部分や核となる部分はあえて特許化せず、秘匿しておくことも重要です(いわゆる「オープン・クローズ戦略」[2])。
このような特許だけでは守れない「強み」は、「営業秘密」として保護・活用することが重要です。
2 営業秘密管理のポイント
営業秘密も知的財産権の1つとして捉えられる以上は、それを侵害された場合には、特許等の他の知的財産権と同様に権利行使できなければ意味がありません。他方で、自社が、他社の営業秘密を侵害しないようにリスク管理をする必要もあります。
この点、特許は、一度登録されれば、無効と判断されない限り、侵害行為に対して差止請求や損害賠償請求することができます。また、リスク管理という面でも、他社の特許は登録され公開されていることから、これにより、自社の発明等がこれを侵害しないか(侵害してしまう特許がないか)を発見し、他社の特許を侵害してしまうリスクを避けることができます(少なくとも一応の調査を行うことができます。)。
しかし、営業秘密は、特許のように登録すれば権利行使できるのではなく、「秘密として管理」され、「有用な技術上又は営業上の情報」であり、「公然と知られていないもの」である必要があり、そうでなければ、自社の情報を無断で使用されても止めることができません(秘密保持義務違反等、別の法的根拠に基づいて差止め等を請求できる可能性はありますが。)。また、そのように他社の「秘密として管理」され「公然と知られていない」情報は、特許とは異なり、外から見ることができませんので、注意しなければ、知らぬ前に従業員が侵害してしまっていたということにもなりかねません。
これらの「権利行使」と「リスク管理」を適切に行うためには、社内体制・規程の整備や、社員教育、他社・従業員等との契約、資料の保存管理、競合他社との関係、紛争になった場合の備え(先使用権の立証等)など、単に知的財産法のみならず、契約法や労働法、商法・会社法、独占禁止法、訴訟法など、法分野横断的な対応が必要になります。
営業秘密は、社内でどのような管理・対応をしてきたかによって結論が変わり得るものですが、どのような管理が適切かは、各社の規模や対象となる情報の性質等によっても異なります。適切な営業秘密管理は、知財戦略を立てる中で、他の知的財産権との関係も踏まえ、日々の業務の中で進めていく必要がありますが、そのためのヒントとなるのが、過去の裁判例であり、特に失敗事例は、自社の営業秘密管理のために、様々な示唆を与えてくれます。これまでの裁判例には様々なものがあり、いずれも個別具体的な事実関係の元での判断ですので、それをそのまま自社にあてはめることはできませんが、そこから教訓を学び取り、自社の営業秘密管理・知財戦略に活かしていくのがよいのではないかと考えます。
本コラムでは、営業秘密侵害事件において、秘密保持契約等の契約が関係し、秘密管理性が否定され、権利行使が認められなかった事例を検討し、権利行使が可能な営業秘密管理を行うためのヒントを学びたいと思います。
3 事例検討
(1) 秘密保持契約とプログラムの開示(東京地方裁判所平成25年6月26日判決)
本事例は、ウェブサイトの制作を業とする原告が、不動産業者である被告に対して、不動産物件情報をインターネット上に公開し広告できるようにするためのプログラム(以下「本件プログラム」といいます。)が保管管理されているサーバーのURLを開示したところ、被告が、原告に無断で、このURLを通じて本件プログラムにアクセスした等として、営業秘密の不正取得・不正使用を主張している事案です。なお、原被告間には、本件プログラムの制作請負契約の成否をめぐって争いがあり、原告が被告に対して、請負代金の支払いを求めたところ、被告がこれを拒否し、訴訟にまで至ったものの、最終的に原告の請求が棄却されたという背景があります。このような背景からも分かるように、原被告間では、秘密保持契約はおろか、制作請負契約書等の書面が作成されていませんでした。また、本件プログラムに対しては、上記URLを入力することでアクセスすることができ、パスワードなど特段の保護手段は採られていませんでした。
このような事実関係を前提に、裁判所は、営業秘密に当たるというためには、「当該情報にアクセスした者に当該情報が営業秘密であることが認識できるような措置が講じられ、当該情報にアクセスできる者が限定されているなど、当該情報に接した者が、これが秘密として管理されていることを認識し得る程度に秘密として管理している実体があることを要する」とした上で、「本件プログラムには、本件URLを入力することでアクセスすることが可能な状態であったこと、秘密保持契約を締結するなど、被告に何らの義務を課することもなく、本件URLは同年(注:平成21年)1月16日に被告に対して開示されていたこと、原告は同年5月31日付け内容証明郵便において被告に対しアクセスを禁止する旨を通知したものの、その後も、本件プログラムへのアクセスに関し、特段の措置を講じていなかったことが認められるから、本件プログラムに関しては、当該プログラムにアクセスした者にそれが営業秘密であることが認識できるような措置が講じられていたとはいえず、また、当該プログラムにアクセスできる者が限定されていたともいえないのであって、秘密として管理されていたものということはできない。」と判示し、原告の請求を棄却しました。
本件では、開示した時点において秘密保持契約を締結していなかったことが秘密管理性を否定する1つの事情として挙げられています。もちろん、アクセスを制限するような措置を講じていなかったことも考慮されていますので、秘密保持契約を締結していれば必ず営業秘密として保護されたとは言い難いですが、少なくとも、被告に対しては、秘密保持契約を締結した上で本件プログラムが開示されたということになり、「秘密として管理している」と認定される可能性も高まったのではないかと思われます(そもそも、プログラムの制作請負契約の成否が問題になっていたことからすると、やはり、原告のような立場からすれば、少なくとも、きちんと制作請負契約書を締結し、その中で守秘義務条項を入れておくべきであったといえます。)。
(2) 秘密保持契約の内容(東京地方裁判所平成20年11月26日判決)
上記裁判例では、「やっぱり契約書は作っておくべき」ということが改めて分かりましたが、では、守秘義務契約を締結しておけば、その内容はどのようなものでもよいのでしょうか?東京地方裁判所平成20年11月26日判決の事例は、レコード、CD等の仕入情報に関する営業秘密侵害事件ですが、守秘義務契約(本件の中では「秘密保持合意」とされています。)の内容について、検討されています。
本件の原告はレコード、CD等のインターネット通信販売業を営む会社であり、被告は原告の元従業員で退職後競合他社に就職した者です。被告は、原告への就業中に、次の内容を含む誓約書を差し入れました。
- 6.業務上知り得た会社の機密事項、工業所有権、著作権及びノウハウ等の知的所有権は、在職中はもちろん退職後にも他に一切漏らさないこと。
また、被告は、原告に対し、次の内容を含む誓約書を差入れて、秘密保持や競業避止に関する合意をしました。
- 「3.退職後の秘密保持義務 私は、貴社を退職後も、機密情報を自ら使用せず、又、他に開示いたしません。」
- 「4.競業避止義務 私は、退職後も2年間は貴社と競業する企業に就職したり役員に就任するなど直接間接を問わず関与したり、あるいは競業する事業を自ら開業したり等、一切しないことを誓約いたします。」
そして、被告が競合他社に転職した後、原告の仕入先情報(仕入先業者の名称等、住所又は所在地、電話番号、ファクシミリ番号、仕入先担当者の氏名及び電子メールアドレス、取扱商品の特徴等の情報とされています。)を使用したとして、原告が被告等[3]に対して、損害賠償を請求しました。
これに対して、裁判所は、秘密管理性の判断基準について「当該情報を利用しようとする者から容易に認識可能な程度に,保護されるべき情報である客体の範囲及び当該情報へのアクセスが許された主体の範囲が客観的に明確化されていることが重要であるといえる。したがって,秘密管理性の認定においては,主として,当該情報にアクセスした者に当該情報が営業秘密であると認識できるようにされているか,当該情報にアクセスできる者が制限されているか等が,その判断要素とされるべきであり,その判断に当たっては,当該情報の性質,保有形態,情報を保有する企業等の規模のほか,情報を利用しようとする者が誰であるか,従業者であるか外部者であるか等も考慮されるべきである。」とした上で、「原告においては、アルバイトを含め従業員でありさえすれば、そのユーザーIDとパスワードを使って、サーバーに接続されたパソコンにより、本件仕入先情報が記載されたファイルを閲覧することが可能であって、そのファイル自体には、情報漏洩を防ぐための保護手段が何ら講じられていなかった上、従業員との間で締結した秘密保持契約も、その対象が抽象的であり、本件仕入先情報がそれに含まれることの明示がされておらず、その他、原告において、従業員に対して、本件仕入先情報が営業秘密に当たることについて、注意喚起をするための特段の措置も講じられていなかったというのである。このような管理状況に加え、本件仕入先情報の内容の多く(名所、住所又は所在地、電話番号、ファクシミリ番号など)が、インターネット等により一般に入手できる情報をまとめたものであり、また、本件証拠上、原告に、個々の仕入先を秘匿しなければならない事情も窺われないことから、本件仕入先情報は、その性質上、秘匿性が明白なものとはいい難いこと等を考慮すれば、本件仕入先情報を用いて日常業務を遂行していた原告の従業員にとって、それが外部に漏らすことの許されない営業秘密として保護された情報であるということを容易に認識できるような状況にあったということはできず、他に秘密管理性を基礎づける事実を認めるに足りる証拠はない。」と判示し、原告の仕入先情報の秘密管理性を否定しました。
本件においては、秘密保持契約が抽象的であり、原告が営業秘密であると主張している仕入先情報がそれに含まれることの明示がなされていないことが秘密管理性を否定する事情の1つとして挙げられています。確かに、これは考慮事情の1つにすぎず、アクセス制限をしていなかったことや仕入先情報という営業情報の持つ特質(一般に入手可能な秘匿性の低い情報であり、日常の業務で利用される)といった事情も重要な判断要素ですが、仮に、当該秘密保持契約(誓約書)において、秘密保持の対象として「仕入先情報」が挙げられていた場合には、少なくとも従業員については仕入先情報が他社に開示してはいけない情報であるという認識であったと認められる可能性もあったのではないかと思われます[4]。実際、本件においては、原告は、営業秘密侵害に基づく請求とは別に、契約上の秘密保持義務違反に基づく請求を行っていますが、これについても、誓約書の記載内容について、上記と同様の理由で棄却されています。
(3) 就業規則等による秘密保持義務と営業秘密(大阪地方裁判所平成12年7月25日判決)
上記のとおり、従業員から差し入れられた誓約書において、単に「機密情報」と記載してあるのみでは、問題となっている営業情報が「機密情報」に当たるか不明であり、契約上の義務違反の責任を追及することも、営業秘密として保護を受けることもできません。
大阪地方裁判所平成12年7月25日判決は、派遣会社が、元従業員やその転職先の会社に対して、派遣社員や派遣先企業の情報を無断で使用した等として、損害賠償等請求した事案において、従業員が誓約書を差し入れているだけでなく、就業規則において「従業員は、『在職中は勿論のこと、退職または解雇された者も、自己の担当であるなしにかかわらず、会社の業務上の機密事項及び会社の不利益となる事項を他に漏らさないこと』との秘密保持条項が置かれている場合に、やはり、上記情報が「機密事項」に含まれると明示していたとは認められないとして、請求を棄却しました。
すなわち、裁判所は、「営業上の情報が秘密として管理されていたといえるためには、情報に接する機会のある社員に対し、それが営業秘密であることを認識できるような何らかの客観的な措置が原告によって講じられていたことが必要である」とした上で、「本件情報が記載された書類が綴じられたファイルは、事務所内のキャビネットに置かれて、原告の社員であれば誰でも自由に見ることができ、そもそも被告を始めとする原告の営業担当社員は、職務上、当然に本件情報に接する立場にあったものである。しかるに、右書類等の管理は一般的な態様のものであり、それらには特段原告の機密事項である旨を示す表示はなされていなかったのであるから、他に特段の事情のない限り、本件情報が、秘密として管理されていたということはできない。」、「もっとも、被告の誓約書には、原告の業務上の機密を漏らさない旨の記載があり、また、原告の就業規則には、原告の機密を漏らしてはならない旨の記載がある。しかし、原告が、これらにいう『機密』の中に本件情報が含まれると明示していたと認めるに足りる証拠はなく、その他原告が『機密』の中に本件情報が含まれると客観的に認識できるようにしていたことを窺わせるに足りる証拠はない以上、これらの記載をもって本件情報が秘密として管理されていたということはできない。」、「右誓約書や就業規則の記載をもって、本件情報が秘密として管理されているといえるためには、単に本件情報が極めて重要であり、性質上『機密』に該当するというだけでは足りず、原告が現実に、本件情報が『機密』に当たることを客観的に認識できるように管理しておく必要があるというべきである。」と判示しました。
本判決が興味深いのは、単に問題となっている情報が秘密保持義務の対象になっているか不明であると指摘するにとどまらず、誓約書や就業規則の記載によって秘密管理性が認められるためには、その情報が性質上契約上の秘密保持義務の対象となっているだけでは足りず、その対象となっていることが「客観的に認識できるように管理」されていなければならないと、秘密保持契約と秘密管理性の関係を示したことです。本件も対象の情報について、具体的なアクセス制限措置が採られていない事案でしたので、そのような事情と合わせて就業規則等の記載の不備等が考慮されているのですが、上記の判示からすると、前期(2)において述べたように、例えば、誓約書等において、具体的な機密情報の内容(項目)を特定した場合に、「機密に当たることを客観的に認識できるように管理」されているといえるのか、その可能性まで否定するものではないと言えるかもしれません。
しかし、会社にとって重要な情報を誓約書等において全て網羅するのは不可能ですし、そもそも、書面に重要な情報を記載すること自体はばかられるところかと思いますので、やはり、就業規則や誓約書等だけに頼らず、アクセス制限措置やマル秘表示など客観的な管理方法も合わせて行うべきであるといえます。ただ、顧客情報等の営業情報は業務上日常的に利用されることもあり、業務効率性と営業秘密の保護とのバランスを考えながら、管理方法を検討する必要があり、あまり厳密なアクセス制限等は採用しづらいところですので、そのこととのバランスから、契約上の秘密保持義務を定めておくことの意義が認められるのではないかと思われます。
4 まとめ
以上のとおり、「営業情報」、「秘密保持契約」というポイントに絞って秘密管理性の要件をみても、営業秘密管理には様々な課題が生じ得るところです。会社内の情報には技術情報や営業情報等の様々なものがありますし、営業秘密として保護されるためには、秘密管理性だけでなく、「有用性」、「非公知性」の要件を満たす必要もあります。さらに、その管理方法は、会社の規模や業務の運営方法等によっても異なるものです。そのため、会社の知財戦略を立てる中で、外部の専門家等の助力を得ながら、適切な営業秘密管理を進めていく必要があります。
なお、弁護士知財ネットでは、昨年度から独立行政法人 工業所有権情報・研修館と「営業秘密・知財戦略セミナー」を共催し、弁護士知財ネットの理事・会員の弁護士が、全国各地で行われるセミナーにおいて講師をしております。昨年度は、「営業秘密の刑事的保護」と題して刑事手続を通じた営業秘密の保護について解説を行いましたが、今年度は、「失敗事例に学ぶ営業秘密保護」と題して、複数の裁判例から、営業秘密管理のために学ぶべきポイントを解説しています(本コラムとは異なる要件、裁判例、トピックを採り上げています。)。ご興味のある方は、ぜひご参加ください。
https://iplaw-net.com/news/information/2244.html
[1] 知財戦略には、「会社(事業)の弱みを補完する」という側面や考え方もあり得ると思いますが、そのようなものも含めて「強み」と考えたいと思います。
[2] オープン・クローズ戦略の詳細は、小川紘一「オープン&クローズ戦略 日本企業再興の条件」をご参照ください。
[3] なお、原告は、被告の身元保証をしていた被告の父親に対しても損害賠償を請求しています。
[4] ただし、最終的に秘密管理性が認められるためには、従業員の主観的な認識だけでなく、ある程度は客観的なアクセス制限が講じられている必要があるのではないかと思われます。