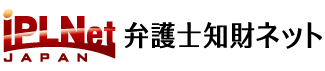営業秘密官民フォーラムメールマガジン掲載コラム 第2回
続・口金ノズル事件-前回第1回コラムの追っかけ
弁護士知財ネット専務理事
弁護士 末吉 亙
PDF版ダウンロード:[営業秘密官民フォーラムメールマガジン掲載コラム] 第2回 続・口金ノズル事件-前回第1回コラムの追っかけ
1.はじめに
前回第1回の本コラム(小松陽一郎=山崎道雄「営業秘密の特定及び特定の際の留意点――口金ノズル事件」)、お読みになりましたか。とても面白かったですね。是非、ご一読下さい[1]。筆者は、これを読んで、いろいろ考えさせられました。そこで、別の観点から、今回もこの口金ノズル事件(大阪地判平成10年12月22日(平5(ワ)8314)知財集30巻4号1000頁)を取り上げたいと思います。追っかけコラムです。
ところで、筆者が営業秘密に初めて出会ったのは、日立IBM事件(プログラムの著作権、営業秘密等が主な争点です)のお手伝いをさせて頂いた昭和58(1983)年でした(筆者は駆け出し弁護士でした)。筆者はこの時まで、知的財産の「知」の字も知らなかったので、ゼロから勉強しました。しかし、当時は、営業秘密に関する本が殆ど無かったのです(営業秘密が知的財産として保護される前の時期ですから)。唯一、小野昌延『営業秘密の保護』という凄い本がありまして、比較法も細かくされていて、いろいろ勉強になりました。[2]
その後、さらに、営業秘密をコツコツ勉強していくと、この口金ノズル事件に行き当たりました。この事件提訴の少し前、平成2(1990)年の不正競争防止法の改正で、初めて「営業秘密」が知的財産として保護されました(それまでは、民法の不法行為で保護されることがありうるだけでした)。この改正法は平成3(1991)年6月15日に施行されましたが、口金ノズル事件は、この改正法の事件として法律構成し、平成5(1993)年に提訴して果敢に挑戦したものです。しかも、顧客情報の多い営業秘密侵害事件のなかで、珍しく、技術上の情報に関する事件でもありました。さらに、約5年の歳月をかけて、原告は一部認容判決を獲得している点も注目されます。以下、少し前置きをしつつ、口金ノズル事件を再度検討してみましょう。
2.営業秘密の主張立証に関する訴訟指揮
そもそも、営業秘密侵害訴訟において、原告は、「請求原因」として、営業秘密にかかる被告の不正競争行為(不競法2条1項4号~10号)を記載する必要があります。これを被告が争う場合には、原告は、原告営業秘密の存在や具体的内容を適宜主張立証しなければなりません。営業秘密に配慮した訴訟審理のための制度等(訴訟記録閲覧等制限制度(民訴法92条・平成10(1998)年1月1日施行)、秘密保持命令(不競法10~12条・平成17(2005)年4月1日施行)、当事者尋問等の公開停止(不競法13条・前同日施行)、守秘契約締結による証拠提出の実務等)が充実している現状においては、この主張立証が緩和されることはあまり期待できないものと解されます。しかし、被告侵害行為の特定は必ずしも容易ではないこと、特定による被告への秘密の開示が避けられないこと等に鑑みると、そもそも、原告営業秘密の全貌を訴訟で明らかにせよとすることは酷だと考えられます。そこで、個別のケースにおける裁判所の適切な訴訟指揮が実務では発動されています。
この点、つとに、平成9(1997)年に発表された論文である設樂隆一「現行民訴法及び新民訴法における営業秘密にかかる不正競争の差止請求及び損害賠償請求の訴訟上の問題点」[3]では、訴訟当事者の実際の主張立証活動に応じて、請求原因の具体的な主張立証の程度を相対的に決定していこうとしています。すなわち、①被告の反論反証が不十分なら原告は原告営業秘密の一部の主張立証で十分な場合もあるが、被告の防御方法が十分行われている場合には原告開示不十分とされる場合もあり、②原告が原告営業秘密についてある程度主張立証をしている場合に、被告が独自技術を主張しながら被告営業秘密を理由に一切開示しないというのは被告防御不十分となる場合が多い、とされています。これは、適正かつ妥当な訴訟指揮だと解されます(なお、現在では、前記②の場合には被告営業秘密の開示に関連して秘密保持命令の適用等が考えられます)。[4]
営業秘密の主張立証をめぐっては、このようなダイナミックな訴訟運用が実際に行われているのです。
3.営業秘密の特定
(1) 営業秘密の特定の程度
そこで、営業秘密の特定の程度についてですが、まず、「不正競争防止法2条1項4号、5号所定の営業秘密の不正取得等による不正競争の成否を判断するに当たって、営業秘密が特定されているというためには、そのすべてを開示する必要はなく、有用性、秘密管理性、非公知性という同法2条4項所定の要件の充足の有無を判断することができ、かつ、同法2条1項4号、5号所定の不正取得等の有無を判断する前提として、その不正取得行為等の対象として客観的に把握することができる程度に、具体的に特定されていれば足りる」とする判決があります(セラミックコンデンサー積層機事件[5])。同判決は、合計約6000枚に上るセラミックコンデンサー積層機及び印刷機の設計図の電子データにつき、「別紙営業秘密目録記載」のとおりの特定で足りるとしました(なお、同判決の指摘する不競2条4項は現行法の同条6項です)。
また、「訴訟において、損害賠償請求及び差止請求等の営業秘密にかかわる請求をするためには、審理の対象を特定して当事者双方の攻撃防御対象を明確にし、執行の際に無用な混乱を起こさないために、請求者が営業秘密を特定する必要がある」「いかなる程度に営業秘密を特定する必要があるのかは、個々の営業秘密の特性及び不正競争行為の態様等に応じて、当事者双方の利益等を勘案しながら決すべき」とする判決もあります(半導体全自動封止機械装置等事件[6])。同判決は、被告が本件営業秘密の内容及び価値等を十分理解できる立場にあったと推認して、当事者双方に本件営業秘密について共通認識があるとし、より具体的な特定作業を行わなくとも、請求原因としての特定は「別紙営業秘密目録A1ないし3」の記載で十分であるとしました。
以上によれば(もっとも、営業秘密という性格上、判決の記載から具体的な秘密の内容は省略されていますが)、営業秘密の特定は、訴訟における攻撃防御対象の特定として充分かどうかの観点から検討されるべきで、この際、個々の営業秘密の特性、不正競争行為の態様等に応じて、訴訟当事者の認識も踏まえて当事者双方の利益等を勘案しながら具体的に特定の程度を決定すべきであると解されます。
なお、この特定には、確定判決に基づく強制執行の際に、無用な混乱を起こさないという効果もあることに留意すべきでしょう。
(2) 営業秘密の段階的特定
営業秘密の性質上、訴え提起の時点で、その内容を正確に特定することは困難ですし、上述のような営業秘密の特定の程度の観点から考えてみると、訴訟の進行に応じて、「特定」の程度を段階的に変えていくことができるものと解されます。すなわち、訴訟提起段階においては、その時点でのできる限りの特定がなされていれば、たとえ抽象的な特定であっても許容されるべきであり、その後、訴訟の進行過程で相手方の出方に応じて営業秘密がより具体的に特定されていく訴訟遂行が望ましく、このような訴訟進行過程に即している限り、営業秘密の段階的特定を時機に後れた攻撃防御方法(民訴法157条1項)として却下すべきではないと解されます。
ここで、口金ノズル事件が登場します。同事件では、つぎのような経緯の下での営業秘密の段階的特定が許容されています。
| 訴訟の段階 | 営業秘密の特定 |
| 平成5年9月6日付け訴状添付目録
|
フッ素樹脂シートの溶接技術に関して、左記の技術のすべて又は一部を使用すること。
一 ホットガンの先端に加工口金を取り付けること。 二 三井デュポンフロロケミカル株式会社製のディスパージョン(溶接用の触媒)を使用してロッド溶接及びテープ溶接をすること。 |
| 同年11月22日付け原告準備書面
|
訴状添付目録記載の営業秘密をより具体的に特定すれば、原告が平成4年5月25日に納品した、契約先興銀リース株式会社、納入先有限会社東田鉄工(最終納入先は日産輸送株式会社富山支店)の、7.2キロリットルEL硝酸タンクローリー内面のフッ素樹脂シートのライニングに際して使用した加工口金ノズル及びディスパージョン並びにこれらを使用したロッド溶接及びテープ溶接であり、この工程については被告【C】が行い、内容を知悉している。 |
| (この間) | ・特定につき原被告の争いを残しつつ、人証調べ(証人尋問手続)。
・原告は、平成8年6月20日付準備書面及び平成9年2月27日付準備書面において、逐次目録の変更を行い、その主張する営業秘密の内容をより具体的に特定。 |
| 平成10年4月22日付け原告準備書面添付目録
|
フッ素樹脂シートの溶接技術に関して、左記の技術のすべて又は一部を使用すること。
一 〔省略〕 1〔省略〕、2〔省略〕、3〔省略〕、4〔省略〕 二 三井デュポンフロロケミカル株式会社製のディスパージョン(溶接用の触媒)を使用してロッド溶接及びテープ溶接をすること。 |
同判決では、①原告主張が、広くフッ素樹脂シートの溶接技術一般ではなく、口金ノズルの加工とディスパージョン(溶接用の触媒)とに限定していることは訴訟提起当初から一貫していること、②被告【A】らはいずれも、原告が営業秘密として主張する技術方法の内容や価値等について十分に理解できる立場にあったこと、③技術情報にかかわる営業秘密は、原告においても、その内容を具体的に特定するのはその性質上必ずしも容易なことではないし、不用意に開示することによって秘密性が失われるおそれもないとはいえないこと、④被告の応訴態度をみながら営業秘密の内容をより具体的に特定するということも、原告の立場からするとやむを得ない面があることをいずれも認定し、これら営業秘密の特定をめぐる攻撃防御の利害関係を前提にして、本件訴訟の経過をみると、原告が故意又は重大な過失によって営業秘密の特定を時機に後れて行い、あるいは、そのために被告の防御に著しい支障を生じたものとは認められないとしました(民訴157条1項(時機に後れた攻撃防御方法の却下等)の適用を否定)。これは、段階的特定の事例として大変参考になります(もっとも、適正・迅速な訴訟進行の観点からは、同判決ほどの長期裁判は、現在では、許されないと解されますが)。
4.「示された」営業秘密とは
前回第1回コラムでは、被告従業員が在職中に自ら開発した又は開発に携わったノウハウ(従業開発型の営業秘密)について、原告会社から「示された」営業秘密といえるのかの論点についても取り上げています[7]。そのうえで、①否定説(会社から秘密情報を開示されて取得したという事実がない限り、「示された」の要件を充足しないという考え方)、②当該営業秘密の本源的保有者の帰属により決定されるという説(本源的保有者が会社の場合は要件充足、従業員の場合は非充足という考え方)、③秘密管理性の有無で判断する説(営業秘密としての管理(営業秘密管理)が及んでいる情報であれば「示された」の要件を充足するという考え方)の3説を紹介しています。同様の論点は、被告従業員が自ら集めた顧客情報等についても問題になります。
この論点は、古くて新しいものです。筆者は、平成17(2005)年の座談会において、この論点を勉強しましたが、いまだ、未解決のようです。[8]
技術上の情報については、職務発明(特許法35条)の制度が整備されている会社では、職務発明との整合性を考えると、ノウハウ開発と同時に当然に会社に営業秘密が帰属しており、「示された」と考える方が自然のように思われます(もっとも、物理的に示されたというより、規範的に示されたと考えられるということですが)。これに対しては、情報である営業秘密の「帰属」を考えること自体が誤りであるとの批判や、特許法35条を基準に営業秘密の帰属を考える法的根拠が乏しいとの批判等があります。
他方、顧客情報の場合については、会社に対する顧客情報報告義務が当該会社で従業員に対して規定されていれば、当然に会社から顧客情報が示されているという結論には、若干違和感があるかもしれません(もっとも、これも規範的な判断ですが)。しかし、会社が従業員から報告を受けた後に初めて会社が保有することとなると、当該顧客情報は、当該従業員との関係では「示された」営業秘密ではないこととなりそうで、これも不都合ですね(当該従業員との関係では、営業秘密侵害行為は想定できず、単に守秘義務違反になりうるのみとなりそうです)。ここでも、情報である営業秘密の「帰属」を考えること自体が誤りであるとの批判や、営業秘密の帰属を考える基準の法的根拠が乏しいとの批判等があります。
簡単な問題なのに、難問です。
営業秘密は奥深いですね。[9]
以 上
[1] 前回第1回コラムのアドレスはつぎのとおりです。
https://iplaw-net.com/tradesecret-mailmagazine-column/2169.html
[2] 小野昌延『営業秘密の保護』(有信堂・1968年)。同書は、現在、小野昌延『営業秘密の保護〔増補版〕』(信山社・2013年)となってパワーアップして復活しています。
[3] 斉藤博=牧野利秋編『知的財産関係訴訟法(裁判実務体系(27))』(青林書院・1997年)572頁以下所収。なお、当該論文の筆者は、現在、知的財産高等裁判所所長です。
[4] 本文2で指摘している「営業秘密に配慮した訴訟審理のための制度等」は、口金ノズル事件の時には、いずれも、制度自体がない、あるいは実務が定着する前の段階でしたが、本文に述べている理由(被告侵害行為の特定は必ずしも容易ではないこと、特定による被告への秘密の開示が避けられないこと等に鑑みると、そもそも、原告営業秘密の全貌を訴訟で明らかにせよとすることは酷であること)から、口金ノズル事件における営業秘密の特定の問題に対する判旨(とくに、同事件での訴訟指揮や、本文3(2)で取り上げる営業秘密の段階的特定の問題)は、今日でも参考になると解されます。ただし、細かい点ですが、訴訟記録閲覧等制限制度は、平成10(1998)年1月1日から施行されており(平成8年改正民事訴訟法92条)、この改正法の附則では、新法の施行前に生じた事項にも適用するとされているので(同附則3条)、同制度は、同施行日以降口金ノズル事件にも適用され、実際に閲覧制限されたのです(これは、前回第1回コラムでも紹介されています)。この点、平成10年まで粘ったのが大正解だったようですね。
[5] 大阪地判平成15年2月27日(平13(ワ)10308・平14(ワ)2833)。
[6] 福岡地判平成14年12月24日(平11(ワ)1102外)判タ1156号225頁。
[7] 不正競争防止法2条1項7号は、「営業秘密を保有する事業者(以下「保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為」を不正競争行為たる営業秘密侵害行為の一類型としています(保有営業秘密の不正使用・開示行為)。ここでは、この7号に該当するかどうかを議論しています。なお、不正競争防止法2条6項では、「この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。」とされており、営業秘密には技術上の情報と営業上の情報があるのです。
[8] 牧野利秋監修・飯村敏明編集『座談会・不正競争防止法をめぐる実務的課題と理論』(青林書院・2005年)176頁~186頁。同書は、出版社には在庫があるようです。
http://www.seirin.co.jp/book/01373.html
[9] 秘密管理性の論点については、ここでは、省略しました。この点、拙稿「営業秘密-保護の経緯と秘密管理性」『東京大学法科大学院ローレビュー9号』(2014年10月)所収も参照下さい(下記Webサイト)。
http://www.sllr.j.u-tokyo.ac.jp/09/papers/v09part08(sueyoshi).pdf
なお、同拙稿では、前掲(注8)書171頁から、秘密管理に関する飯村敏明 前知的財産高等裁判所所長(発言当時は東京地方裁判所部総括判事)のつぎのとおりの発言を引用しています。これは、とても参考になります。
「退職者に秘密を持ち出されないようにする最良の方法は、従業員に裏切られないように、従業員の保護を手厚くして、退職されないようにするということかと思います(笑い)。それはそれとして、企業が、退職者によって営業秘密を奪われたと主張して訴訟を提起する場合における対策としては、外からも確認できる、見える形での秘密管理も重要かと思われます。例えば、秘密情報について、一定の範囲の従業員以外にはアクセスできないようにする物理的な方法も考えられますが、業務の円滑な遂行とのバランスで、そのような方法が現実的でないのであれば、就業規則、内規、契約などによって拘束する方法とか、いろいろなあらかじめの対策が必要になってきます。いろいろな規則を定める際に重要なことは、業務の過程で、実際に遵守されているという実態があることは必要かと思われます。」
営業秘密侵害事件の多くは、会社と元従業員の間のものであり、上記の考え方は、これを前提に営業秘密管理の極意を示唆しています。
本文で述べた「示された」の要件を考えるに当たっても、営業秘密管理の状況をも考慮し、その際、上記の考え方を取り入れるのが妥当なように思います。