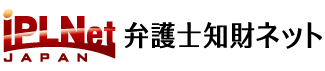営業秘密官民フォーラムメールマガジン掲載コラム 第3回
営業秘密訴訟の被告の防御方法と被告にならないための予防対策
弁護士知財ネット事務局長
弁護士 林 いづみ
PDF版ダウンロード:[営業秘密官民フォーラムメールマガジン掲載コラム] 第3回 営業秘密訴訟の被告の防御方法と被告にならないための予防対策
1.はじめに
現代はインターネットに様々な「もの」が繋がるインターネット・オブ・シングズ(Internet of Things)、「IoT時代」といわれています。さらに、IoTは変革のごく一部にすぎず、次世代スパコンや次世代人工知能により、今後短期間に無数の革命的事象が連続的・同時多発的に生じるという「特異点(シンギュラリティ)」論すら説かれています[1]。いずれにしても、今後益々、個人・企業・国家にとって、「繋がる情報財」の取得・保護・活用が重要になることは間違いありません。
「繋がる情報財」の価値増加に伴い、この10年来、国際的な自前主義からの脱却や非競争領域における情報共有と競争領域における情報独占の戦略化(オープン・イノベーション、オープン・クローズ戦略など)が進んでいます。こうした背景のもと、平成27年改正不正競争防止法は民刑両面の多岐にわたり、営業秘密保護強化のための改正を行いました。
改正項目には、立証責任の転換や没収規定など、他の知財法に先駆けた新たな制度の導入も含まれており、普及・実践のための具体的な取組みを急ぐ必要があります。
本稿では、まず、2.で、改正項目のうちの立証責任の転換規定の内容と実務について解説します。次に、3.で、被告にならないための予防対策として、日常的な企業取引を通じて外部秘密情報が自社情報に混入するいわゆる「情報コンタミリスク対策」について解説します。企業にとっては、営業秘密の管理・漏洩対策もさることながら、特許権・営業秘密の侵害警告に対する防衛上も、情報コンタミリスク対策は必須になっているからです。
2.原告の立証責任の軽減
(1)改正の趣旨
被告による営業秘密の不正使用について被害救済を求める営業秘密訴訟において、原告は、被告が当該秘密を使用した事実を立証できなければ裁判に負けてしまいます(これを「立証責任」と言います。)。
日本の民事訴訟法には、米国のディスカバリー制度のような強力な証拠収集手続がなく、被害救済を求める原告は、被告のみが持っている証拠を収集することは、とても困難です(これを「証拠の偏在問題」といいます。)。
特に、物の生産方法などの技術上の営業秘密の使用に関する証拠は被告の工場や事務所内部にしかなく、証拠の偏在問題が顕著です。従って、侵害事実の立証責任を負担する原告の立証負担は非常に重いのです。
確かに、民事訴訟法における証拠収集手続として文書提出命令制度が存在し、特に、知財各法においては侵害立証の容易化のための法改正(インカメラ制度や秘密保持命令制度など)も行われてきましたが、実務における同制度の運用はとても謙抑的です。
実際、原告が侵害立証のための文書提出命令の申立てをしても、裁判所は、ほとんどの場合、被告に対する訴訟指揮によって、任意の文書提出を促すだけで、原告の申立ては却下されています。
こうした裁判所の実務の理由として、通常、挙げられるのは、原告の探索的な申立てによる制度の濫用により被告の営業秘密を守る必要性、開示範囲の柔軟な調整(発令後に即時抗告が申し立てられた場合には抗告審の判断を待たなければならない等。)、および訴訟期間の長期化を防止するなどの観点です。
一般に、民事上の証拠収集の問題は、被害救済を求める原告側の証拠収集の必要性と、被告側の営業秘密保護との、バランス(利益衡量)の問題といえます。
被告の立場に立てば、原告の営業秘密を使用していないという証拠について、自らの営業秘密を開示することなく、開示しても問題のない限度の任意の証拠提出で許される現状の方が望ましいのは当然です。しかし、上記のいずれの観点も、はたして、法律上定めた制度を活用しない十分な理由と言えるのかは、疑問でしょう。
こうした現状に対し、文書提出命令制度自体の有用性や実効性の限界を指摘し、証拠収集制度の見直しを求める声は、かねてより、ありましたが、上記の利益衡量を解決することができず、抜本的改革には至っていません。
平成27年不正競争防止法の改正においては、こうした証拠の被告偏在問題を解決し、営業秘密侵害訴訟における立証責任を公平に配分するため議論を重ねた結果、まずは、特定の条件を満たす場合についてのみ、原告の立証責任を軽減する推定規定を新設することなったものです。
(2)新5条の2の推定規定
≪第5条の2(技術上の秘密を取得した者の当該技術上の秘密を使用する行為等の推定)
技術上の秘密(生産方法その他政令で定める情報に係るものに限る。以下この条において同じ。)について第2条第1項第4号、第5号又は第8号に規定する行為(営業秘密を取得する行為に限る。)があった場合において、その行為をした者が問うが技術上の秘密を使用する行為により生ずる物の生産その他技術上の秘密を使用したことが明らかな行為として政令で定める行為(以下この条において「生産等」という。)をしたときは、その者は、それぞれ当該各号に規定する行為(営業秘密を使用する行為に限る。)として生産等をしたものと推定する。≫
新5条の2は、「不正に若しくは悪意重過失で一定の営業秘密を取得した者には、当該営業秘密を使用する蓋然性・経験則が認められる。」という考え方に基づく規定です。
すなわち、被告による営業秘密の不正使用が推定されるために原告は、
(A)被告の不正取得(不競法2条1項4号)、または取得時に不正取得や不正開示の介在について悪意重過失(同5号、8号)、
【注1】推定の前提事実である営業秘密を取得する行為が改正法の施行前にあった場合には、推定規定は適用されません(改正法附則2条)。
【注2】4,5,8号以外の、7号(正当取得者の不正利用行為)、6号または9号(正当取得後に不正取得・開示の介在について悪意重過失となった者の不正利用行為)については、推定規定は適用されません。
(B)原告の営業秘密が「生産方法」または「政令指定の技術上の秘密」であること、
【注3】「生産方法」には生産工程の効率化やコストカット技術を含みます。
【注4】生産方法以外の分析方法などの技術上の営業秘密を推定の対象とするか否かは政令委任事項とされています。被告の反証容易性の確保及び濫訴防止の観点から適用対象の限定を行ったものであり、今後、政令において新たな対象行為を指定するにあたっては、同様の観点が考慮されるべきでしょう。
(C)原告の営業秘密と被告の生産物との間の関連性
【注5】原告技術と明らかに無関係の製品について推定規定が濫用されないように設けられた条件です。被告生産物の原告生産物との同一性は不要ですが、製品の機能、品質、コスト等、競合他社との差別化要因となり得る点において共通していることが要求されます。
の3点について立証責任を負います。
これらに対する被告反論、すなわち、
・秘密管理性要件などの営業秘密非該当
・被告の取得なし
・取得時の善意無重過失、
・被告製品は、原告の生産技術に該当しない
・原告の生産技術は、被告の生産物との関連性なし、等
は、反証として位置付けられます。
以上の3点について原告が立証した場合には、被告による営業秘密の不正使用行為が推定され、被告はこの推定を覆すために、被告製品の具体的な製造工程や製造状況を開示するなどして、自己の不使用の事実について立証責任を負うことになります(立証責任の転換)。
審理においては、裁判所が上記の3条件を充足する心証を得て使用の事実につき立証責任が被告側に転換された場合であっても、被告側としては、当然ながら、自らの秘密を防御するために、秘密保持契約や、秘密保持命令制度(法10、11条)を活用することができます。
なお、平成16年に秘密保持命令制度が導入されたことを踏まえ、営業秘密であることは、不正競争防止法6条の具体的態様明示義務の例外(但書の「相当の理由」)に該当しないことが、今回の改正議論において明確に確認されました[2]。
(3)推定規定の適用対象の限定
上記のとおり、推定規定の適用対象はごく特定の場合に限定されています。これは推定規定の制度設計において、上記の利益衡量や、従業員の転職の自由、正当な企業活動を行う企業が意図しない情報コンタミネーション(後述)により事業可能性を制約されるリスク、言いがかり的な濫訴の被告になるリスクについても考慮したためです。
したがって、今後、政令で推定が及ぶ範囲を決める場合も、こうした立法趣旨に照らして合理的な経験則の範囲及び原告と被告の立証負担の公平性をはかるべきであり、政令が立法から委任された範囲を超えないよう、気を付けていかねばなりません[3]。
(4)証拠収集制度の改革に向けた議論
他方、条文上も本規定の適用範囲は限定されているので、営業秘密侵害訴訟における原告の立証の困難を軽減するためには、引き続き、現行の文書提出命令(民訴法及び不競法)の積極的な運用が期待されますし、知的財産戦略本部(知財紛争処理システム検討委員会)の検討を経て[4]、現在、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会[5]において、証拠収集制度の見直しについて検討中です。
3.被告にならないための予防対策
(1)情報コンタミリスク対策の必要性
企業は、自らの営業秘密の漏洩を防止する場面と、意図しない外部秘密情報が自社情報に混入(汚染)する「情報コンタミリスク」を避ける場面との、両面の取り組みを進める必要があります。
平成27年1月に全面改訂された「営業秘密管理指針」や、新たに策定された「秘密情報の保護ハンドブック~企業価値向上に向けて」も参考になるでしょう[6]。
前者の漏洩防止については、自社の営業秘密の存在にすら気づいていない中小企業や大学・研究機関などにおける、「実践的な」秘密管理保護体制づくりのサポートが必要です。しかし、海外展開など組織が複雑な大企業には、大企業ゆえの難しさもあります。特に、IoT時代のサイバーアタック対策は、大企業であるほどコストも高額になるため、経営陣が対策の重要性を十分に理解して機動的に実行する必要性を感じざるを得ません。
企業においては、もっと後者の情報コンタミリスクの必要性を重視すべきでしょう。日常的な企業間取引や従業員採用の結果、意図しないまま他社の秘密情報が自社情報に混在したまま事業を行っていると、ある日突然、営業秘密侵害訴訟を提訴され、自社の事業の方向性自体が制約されるリスクがあります。
(2)具体的対策
情報コンタミ対策については、各社で様々な工夫をされていると思いますが、ここでは4つの対策を挙げます。
①分離保管
コンタミ防止のためには、秘密保持契約のもとで受領した顧客や取引先企業の秘密情報は、必ず、自社情報と分離して保管(アクセス制限)する体制を作る必要があります。
そのためには、まず、従業員等による重要情報の取得・利用を確認するために必要な手続を決めます。後述する契約によるリスクヘッジ次第ですが、情報受領による事業リスク、紛争リスクを超えるだけの必要性のない情報は、そもそも受領しないというポリシーを持つ企業もあります。
また、従業員等の重要情報の取得・利用が手続き通りに行われているかどうかを、上司による決済の際に確認し、日常の研修等でも徹底します。
②中途採用時の注意
社員等(委託、派遣やアルバイトを含む。)の採用に際しては、前職等での秘密保持義務、競業避止義務の内容を確認し、前職での他社の営業秘密を持ち込まないことを誓約させることは、最低限、必要でしょう。
例えば、同一の大口顧客を取り合っている競合企業(原告)か ら研究開発部長を含む技術者数名を相次いで中途採用して間もなく、原告が長年かかって開発した秘密の生産方法によってのみ実現できていた機能を持つ同種の製品を、被告が同一の顧客に販売していることが判明したとします。
上述の改正法5条の2によれば、被告による不正使用が推定されるためには、原告は「(A)被告の不正取得(不競法2条1項4号)、または取得時に不正取得や不正開示の介在について悪意重過失(同5号、8号)」を立証しなければなりませんが、中途採用を巡る客観的事実は、不正開示の介在についての被告の重過失の認定に重要な影響を与えると思われます。
③分離保管の管理状況を証拠として残す
一旦、訴訟になったら、分離保管の管理状況を証明できるように、証拠として残しておく必要があります。なお、漏洩事案では、アクセスログを保存していたが何年も漏洩に気づかなかったという例がよくあります。アクセスログは常時監視して異常状態が発見されたら対処が手遅れにならないようにすることが肝要です。
証拠としては、データ管理に限らず、入退室管理や、対象となる秘密情報の「範囲」を漏れなく特定した秘密保持誓約書を、入社時、プロジェクト開始時、異動時、退職時にとることも役立ちます。
④企業間取引の契約対策
前記のとおり、企業間取引による情報の取得は、改正法の推定規定の射程外です。
しかし、企業間取引は、意図しない情報コンタミリスクが高い場面ですから、事業を計画する段階から、そのリスクを十分に意識した戦略的な契約をすることが重要です。
従来の契約交渉においても、いわゆる知的財産権的なコンタミリスクについては比較的、意識されてきました。たとえば、共同研究開発や委託製造販売の取引においては、誰がその技術を発明したのか、寄与の度合いが分かりにくくなるため、バックグラウンドIP(BIP)と成果物(FIP)の帰属や利用の在り方を明確化させる条項を、予め契約に盛りこむことが多いと思います。
情報財としての価値を考えれば、当然、営業秘密についても同様の取り決めを行うべきですが、そこまで詰めていない契約が多いようです。以下、残念ケースと巧妙ケースをご紹介しましょう。
○取引の可否検討段階で、ルーティンとして秘密保持契約(NDA)を結んでいることがよくあります。
もちろん、企業としては、
・取引先に対する開示・非開示の方針を社内で明確にし、
・情報開示前には必ず秘密保持契約を締結し、
・契約を集中管理すること
は、当然のことです。
しかしNDAも「この目的以外には使わないこと」ぐらいの大雑把な条項ではとても済まないような時代になっており、色々な意味で「本当は怖いNDA」といえます。
たとえば、秘密の範囲(口頭で話したことまですべて秘密なのか等)が特定されていない場合、情報開示者側から広範な権利主張をされるリスクがあります。逆に、訴訟で、契約書の内容で、もう少しここにちゃんと書いてあれば権利を守れたのに、契約文言が不明確なために、何をお互いに秘密にしたのかわからないという事案も少なくないようです。
○相手方から提示されたNDAに盲目的に捺印していたが、後日、紛争になって弁護士に見せたら、事実は、当方は情報提供者なのに情報受領者として対象情報の将来の利用を制限する内容になっていたという例もあります。
○共同研究開発契約において、開示情報と同じ分野の同じ技術に関するものについて、たとえば特許出願や論文を出すときには、先に相手方に提出して検閲を受けることを規定する場合もあります。
○メーカーが相手方との購買取引を期待して、NDA(秘密保持契約)や共同研究開発契約を締結して情報提供したが、その後の購買取引に至らない場合があります。これらの契約書中に、購買取引の保証もなく、契約対象の情報の目的外利用の禁止と広範な関連製品の第三者への販売を禁止する条項が入っていると、情報提供したメーカーは飼い殺し状態になってしまいます。
まずは、「残念さん」にならないことが肝要ですが、「巧妙さん」の相手方になってしまったら、どうすればよいでしょうか?最終的には当事者の力関係で決めざるを得ない、とはいえ、少なくともリスクを認識して交渉するならば、獲得した契約を前提とした自社としての対処法をみつけられるはずです。諦めずに何度でも粘り強い契約交渉をすべきではないかと思います。
4.おわりに
今後、ますます、「繋がる情報財」の取得・保護・活用が重要になります。知的財産権未満の情報についても、予め、契約書において、お互いに自由に使える情報の範囲を明確にし、お互いがどういう情報をもったときにどういう報告を相手方に出すのか等、情報の利用ルールについて合意しておくことが、事業の予測可能性および紛争予防のために役立つと思います。
以上
<注>
[1] 斎藤元章「エクサスケールの衝撃」(PHP研究所)
[2] 経済産業省が作成した不競法逐条解説(経済産業省知的財産政策室編著「逐条解説不正競争防止法 平成23・24年改正版」(2012年、有斐閣))においては、同法6条の具体的態様明示義務に関して、「明示する内容に営業秘密が含まれている場合には、ただし書きの「相当の理由」に該当」という記述が修正されました。
[3] 筆者は同改正議論を行った営業秘密小委員会に参加した者として最終的に同改正に賛同していますが、本来的には、証拠の偏在問題は、このような推定規定よりも、証拠収集制度の改革によって解決すべきだと考えています。
[4] https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2016/syori_system/dai1/gijisidai.html
[5] https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/tokkyo_seido_menu.htm
[6] 経済産業省のウェブサイト参照 http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/trade-secret.html