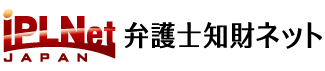営業秘密官民フォーラムメールマガジン掲載コラム 第6回
米国における新たな営業秘密保護法“Defend Trade Secrets Act”
弁護士知財ネット
弁護士 奥村直樹
PDF版ダウンロード:[営業秘密官民フォーラムメールマガジン掲載コラム] 第6回 米国における新たな営業秘密保護法“Defend Trade Secrets Act”
世界を驚かせた大統領選挙も終了し、トランプ次期大統領の一挙手一投足が注目されている米国ですが、知財絡みでは日本にも大きな影響を与えかねないTPPからの脱退等の宣言が注目を集めています。TPPとは直接の関係はありませんが、今回は、日本企業にとって今なお最重要市場の一つといえる米国での営業秘密保護法制の動向について簡単に紹介したいと思います。
日本の弁護士として米国の知財訴訟に何らかの形で絡む場合、専ら特許事件絡みであり、商標関連訴訟や営業秘密関連訴訟で米国の民事訴訟手続に関わることは、あまり(少なくとも筆者は一度も)ありません。そのような事情もあって、筆者も、米国留学中は、特許法の授業は受講したものの、不正競争・営業秘密関連法の授業については取得しておらず、自身の知見を広めたいと同時間に開講されていた、畑違いの金融関連法の授業をとっていました(決して、期末試験がマークシート式であったからという安易な理由ではございません)。
前置きが長くなりましたが、間もなく任期終了するオバマ政権のレガシーの一つとして、2016年5月に、連邦法としての営業秘密保護法(Defend Trade Secrets Act)が成立しました。これによって、営業秘密冒用事案に対しても、連邦法の管轄が与えられることになり、営業秘密冒用事案の被害者が、州裁判所だけではなく連邦裁判所にも救済を求めて訴訟提起できることになりました。
背景として、アメリカ合衆国成立の経緯にも絡む同国のやや複雑な民事訴訟法体系について説明させて頂きます。皆様ご存知のとおり、米国では、州と連邦という二重体制・二重主権とも呼ぶべき体系となっており、司法制度に関しても、連邦裁判所体系と州裁判所体系という二つの体系が存在します。これは、もともと、各州が一つの国(State)であったという米国成立の沿革に端を発するものです。
そのような中で、連邦裁判所の第一審管轄権は、特に連邦制定法によって認められた事件のみに限定されており、従前は、営業秘密冒用を巡る民事訴訟は州裁判所にしか提起することができませんでした。この点、特許法が、連邦法であり、特許権侵害事件については連邦裁判所のみに管轄が認められることと比べると大きな相違があったといえます。(ただし、営業秘密冒用事案に対する各州法の内容を統一しようとしたUniform Trade Secrets Actは存在し、多くの州が営業秘密の冒用に対する保護として、その内容を採択しており、営業秘密保護法の内容自体は統一がはかられてきました)。
しかし、各州裁判所における手続では、州毎に手続や証拠のスタンダードが統一されていないこと、さらには、一般的に連邦裁判所の方が州裁判所よりも営業秘密関連事件のように複雑な技術的知見が絡む案件には専門性を有すると見られていることや、海外企業がからむ事件にも慣れていると見られていることなどから、営業秘密冒用訴訟についても連邦裁判所で扱うことができるようになることを望む企業の声が大きく、今般のDTSA成立の運びとなったようです。なお、念のためですが、DTSAは、州法に加えての保護であり、州法による保護自体が廃止されるわけではありません。
それでは、ここから先は、DTSAの具体的な特徴と中身について、さらに、説明させて頂きます。
DTSAの大きな特徴として、裁判所が、一定要件のもと、特別な状況の場合に、一方当事者のみの申し立て(ex parte)によって、営業秘密の拡散や流布を防止するために必要な物を差し押さえできるとしていることがあります。差押えの発令要件については、次のとおり、非常に詳細に定められています(余談ですが、筆者は、留学当初、米国は判例法を中心としたコモンローの国であり制定法は脇役に過ぎないという勝手な印象を持っていましたが、実際に勉強すると、各法分野で非常に詳細・大量(かつ分かりにくい)の制定法が存在しており、その理解に苦しめられました。)。
- 当事者が命令を回避し、避け、又はそうでなければ命令に従わないであろうため、衡平法上の救済等が不適切であること、
- 差押えがされなければ、切迫かつ回復不能な損害が起きること、
- 差押えされる当事者に対する害よりも、差押えが否定された場合に申立人に生じる害が上回ること、及び、そのような差押えによって害されかねない第三者に対する害も大幅に上回ること、
- 申立人が、(a) 情報が営業秘密であり、かつ、(b) 差し押さえを発令されるべき人が、不適切な手段により営業秘密を冒用したこと、又は、申立人の営業秘密を冒用するために不適切な手段を用いることを共謀したこと、の立証に成功しそうなこと、
- 差押えを命じられる人が現実に営業秘密及び差押え対象となる財産を占有すること
- 申立書が、合理的な詳細さで差押えられるべきものを説明していること、及び、当該状況のもと合理的な程度に当該者が差し押さえられるべき場所を特定していること
- 仮に申立人が通知しようとすれば、差押えの発令される人物又はそのような人物と共に行動する人物が、そのような物を破壊し、移動し、隠匿し、あるいは裁判所のアクセスを不可能にすること、及び、
- 申立人が要求に係る差押えを公表していないこと
なお、差押対象物については、差押対象物について利害関係を有する者の一方的(ex parte)申立により、媒体を暗号化することも認められると定められています。
DTSAでは、日本の不正競争法2条1項と同様に、どのような行為が規制される「(営業秘密の)冒用」や「不適切な手段」に該当するかについても、詳細な定義規定を設けており、そのような営業秘密の冒用に対する救済手段として、大きく分けて差止と損害賠償が定められています。
差止については、裁判所が条件を付することが認められています。ただし、いわゆるinevitable disclosureを禁止する条件を付けることはできないとされます。すなわち、営業秘密冒用の差止を求められている従業員が、ある情報を知っていることに基づき別の使用者と雇用関係に入ることを差止することは認められないとされます。なお、差止を不衡平とする例外的状況では、ロイヤルティ支払を条件として、冒用者側が営業秘密を将来の一定期間使用できるように、裁判所が命じることもできるとされます。
損害賠償については、(a) 営業秘密の冒用によって生じた実損害、及び、営業秘密の冒用により生じた不当利得、又は、(b) 合理的なロイヤルティ相当額をもって損害賠償請求できることが定められています。さらに、営業秘密が、故意かつ悪意をもって冒用された場合には、懲罰的賠償として2倍を超えない金額の賠償を命じることができるとされます。
最後に、DTSAの特徴的条文として、一定条件のもとにおける従業員内部告発者の免責と使用者に課せられる従業員保護規定の告知義務があります。これらについては、米国に進出している日本企業の日常業務にも影響を及ぼすと可能性があるので意識的に確認された方が良いでしょう。
いわゆる、corporate whistleblower(内部告発者)への保護を念頭として、営業秘密の開示が、法令違反の疑いの報告又は調査目的で連邦や州等の職員に秘密になされること、又は、当該開示が訴訟手続等において提出される訴状等でなされること(ただし閲覧制限が必要)、このような要件が満たされる場合には、連邦又は州の営業秘密法制下で、当該個人が民事刑事責任を負うことはないとされます。また、反報復訴訟(Anti-Retaliation lawsuit)における営業秘密の使用として、使用者による被疑法令違反事実を報告したことに対して報復がされたことを理由に訴訟提起した個人について、一定条件下で、代理人に営業秘密を開示し、かつ、訴訟手続で当該営業秘密を用いることが認められています。
また、DTSAは、使用者側が、営業秘密又は機密情報の使用を管轄する従業者との間の契約書等の中で、このような免責を通知しなければならないとしています(ただし、通知義務は、使用者が、被用者に提供される指針文書(法違反の嫌疑についての使用者の報告指針を定めたもの)へのクロスリファレンスを提供すれば遵守したとみなされます)。仮に、使用者が上記通知義務を果たしていない場合には、そのような通知を欠く従業者に対しては懲罰的損害賠償命令や弁護士費用の賠償命令が認められないこととなるので注意が必要です。