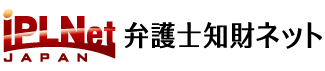営業秘密官民フォーラムメールマガジン掲載コラム 第66回
営業秘密の転得者の悪意又は重過失
弁護士知財ネット
弁護士 佐藤 安紘
PDF版ダウンロード:[営業秘密官民フォーラムメールマガジン掲載コラム] 第66回 営業秘密の転得者の悪意又は重過失
営業秘密侵害訴訟の実務的に重要な論点の一つとして、企業が営業秘密を転得した場合に、当該企業の悪意又は重過失をどのように認定するのかという問題があります。訴訟当事者は、この悪意又は重過失を基礎付ける具体的事実について、どのような主張立証を心掛けるべきでしょうか。裁判例を踏まえながら検討してみます。
[目次]
1 悪意又は重過失の意義
営業秘密の転得者による営業秘密の取得(転得)、使用、開示等が不正競争行為となるためには、その転得者の悪意又は重過失という主観的要件の主張立証が必要となる(不正競争防止法2条1項5号、6号、8号、9号等)。悪意とは不正競争行為が介在した事実を知っていることをいい、重過失とは取引上当然払うべき通常の注意義務を尽くせば容易に不正競争行為の事実が判明するにもかかわらず、その義務に違反する場合いう(通商産業省知的財産室『逐条解説営業秘密』82頁。知財高判H30.1.15(平29(ネ)10076号)も同旨)。営業秘密は公示性を欠くため、情報取引の安全の観点から、その転得者の主観により不正競争行為の範囲を合理的に画する趣旨である。
2 誰の悪意又は重過失か?
この悪意又は重過失は、誰の認識を問題にすればよいか。転得者が個人の場合は、その個人の認識を問題にすれば足りることに争いはない。問題は、転得者が企業その他の団体(以下単に「企業」という)の場合である。この場合、企業自体の悪意や重過失を問題にすればよいのか、それともその企業の機関や構成員の悪意や重過失を問題にする必要があるのかは、必ずしも明らかではない。条文の文理からは、いずれの解釈も成り立ち得るように思われる。観点を変えれば、転得者が企業の場合、その悪意又は重過失を基礎付ける具体的事実は何かという当事者の主張立証の問題である。
(1) 従来の裁判例
悪意又は重過失を肯定した最近の裁判例をみてみると、裁判所は、当事者の主張立証に応じて、企業の悪意又は重過失を事案ごとに柔軟に判断しているように思われる。
まず、(a)企業の代表者の認識に基づき、当該企業の悪意又は重過失を認定している裁判例がある。例えば、①知財高判H28.4.27(平26(ネ)10059号外)は、被告(企業)を設立した代表者が、原告の退職者が原告を退職後も原告のソースコードを廃棄せずこれを使用して被告側のプログラムを作成したことを知っていたという事実を認定し、その代表者の認識に基づき当該企業の悪意を判断している。また、②知財高判H30.3.26(平29(ネ)10007号)は、被告(企業)を設立した代表者自身が、原告の営業秘密へのアクセス権限を有する者に対し、被告側の製品と同等のソフトウェアを作成することを指示していた事実を認定し、その代表者の認識を通じて当該企業の重過失を判断している。③大阪地判H30.3.5(平28(ワ)648号)も、被告(企業)の代表者が原告の営業秘密が持ち出されている可能性を認識していたにもかかわらず特段の措置を講じなかったことを理由に、被告(企業)に重過失があったと判示している。
次に、(b)企業の従業員の認識に基づき、当該企業の悪意又は重過失を認定している裁判例がある。例えば、④大阪地判H28.6.23(平25(ワ)12149号)は、原告を退職して被告(企業)に転職した者が、その企業の従業員として原告の顧客に対して営業活動をしていた事実を認定し、その従業員の認識に基づき当該企業の悪意を判断している。また、⑤大阪地判H30.3.15(平27(ワ)11735号)は、顧客情報が営業秘密であると主張された事案において、被告(企業)の従業員が営業秘密の不正取得者から原告の顧客であることを知らされていた事実を認定し、その従業員の認識を介して当該企業の重過失を判断している。
さらに、(c)企業の代表者や従業員の認識に具体的に言及することなく、企業自体の悪意又は重過失を直接認定している裁判例もある。例えば、⑥福井地判H30.4.11(平26(ワ)140号外)は、原告側の製品と被告(企業)側の製品が有意に類似していること等の外形的事実に基づき、当該企業の代表者や従業員の認識を問題とすることなく企業の悪意を認定している(控訴審である名古屋高判金沢支部R2.5.20(平30(ネ)81号外)もほぼ同旨)。また、⑦東京地判H30.11.29(平27(ワ)16423号)も、被告(企業)側の製品を開発した委託先が原告側の製品の開発に携わった者の一人であること等の外形的事実を認定し、それ以上に代表者や従業員の認識を問うことなく、当該企業自体の重過失を判断している(控訴審である知財高判R1.8.21(平30(ネ)10092号)は、営業秘密の使用の事実が認められないとして原判決取消)。
(2) 原則は代表者の認識を問うこと
裁判例が上記(1)の(a)~(c)のように整理されるとして、企業が営業秘密を転得した場合の悪意又は重過失は、何を基準に考えるべきだろうか。手掛かりになるのは、東京高判S63.3.11(昭57(ネ)281号外)と思われる。この事案では、クロロキン製剤を輸入、製造、販売等した企業が、同製剤を服用し、その副作用によりクロロキン網膜症に罹患した原告に対し、企業活動自体による民法709条の不法行為責任を負うか否かが争点の一つとなった。東京高裁は、企業の故意又は過失という主観的要件について、次のとおり判示している(強調は筆者)。
・「(民法709条により直接法人に不法行為責任を認めるためには)様々な理論上の問題点を克服しなければならない。まず、法人の代表機関の故意、過失とは別個に法人自体の故意、過失というものが存在し得るか否かが問題となる」
・「法人の不法行為責任は、当該法人がいかに企業規模が大きくて社会的、外見的にはいかにも実在の人間のように活動しているようにみえても、それが結局のところ機関の存在を不可欠としており、具体的、法律的には右機関を通じて活動するほかない」
・「不法行為の主観的構成要素である故意または過失とは自然人の精神的容態であり、法人の不法行為法上の故意、過失とは、具体的には、法人の機関、株式会社においては代表取締役の故意、過失を意味する」
この東京高裁の判決は、企業の不法行為責任については、民法709条とは別に、①代表者を介した責任として一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条、会社法350条(この当時は、平成17年改正前の商法261条3項、78条2項の準用する平成18年改正前の民法44条1項)、及び②被用者を介した責任として民法715条がそれぞれ規定されていることを前提に、企業の故意又は過失はその企業の代表者の故意又は過失を意味する旨を判示したものである。民法709条(不正競争防止法4条に相当)に関する解釈ではあるものの、この東京高裁の判示を前提にする限り、企業が転得者となる事案では、その悪意又は重過失は、当該企業の代表者の認識を問題にするのが本来の姿であると考えられる。このような解釈は、営業秘密侵害の刑事責任が問われる場合に、企業は不正競争防止法21条1項各号の規定が直接適用されるのではなく、両罰規定(同法22条1項1号)を適用することにより処罰対象になることとも整合的である。
(3) 代表者の認識は規範的に評価すればよいこと
もちろん、このことは、民事事件において、企業の代表者を具体的に特定し、その代表者の現実の認識を常に厳密に明らかにしなければならないということではない。特に重過失は、前述のとおり、取引上当然払うべき通常の注意義務を尽くせば容易に不正競争行為の事実が判明するにもかかわらず、その義務に違反する場合を意味するとされている。これは、いわゆる規範的要件であるから、企業の代表者の認識を規範的に評価することも許されよう。最判H13.3.2(平12(受)222号)も、著作権侵害の事案において、カラオケ装置のリース業者には、リース契約の相手方に対して著作権者との間で利用許諾契約を締結等したことを確認した上でカラオケ装置を引き渡すべき条理上の注意義務があるとして、企業の過失を規範的に評価して企業に直接民法719条(共同不法行為責任)を適用している。
また、代表者が内部的にその権限を従業員に委譲し、その従業員がその権限に基づいて対外的に行為をしたといえるような場合には、代表者ではなくその権限を委譲された従業員の主観により当該企業の認識を判断することもできると考えられる。健康保険法に関する事案であるが、大阪高判H31.2.14(平30(行コ)39号)も、代表者による従業員に対する権限の委譲がある場合には、その従業員の主観をもって法人の故意又は過失の有無及び過失の程度を判断するべきであると判示している(大阪地判H30.3.1(平25(行ウ)137号)の判示を引用)。これも、企業の内部的な権限の委譲を起点として、代表者の認識を規範的に評価する一態様とみることができる。
前述の(a)~(c)の各裁判例は、こうした規範的な評価の観点を踏まえることにより、整合的に理解することができると思われる。まず、裁判例①②③は、当事者の主張立証により、代表者の認識を具体的に明らかにすることができた事案(=本来の姿)である。また、裁判例⑤⑦は、代表者の認識を具体的に明らかにすることまでは困難であったものの、当時の従業員の認識(⑤)や製品開発の状況(⑦)等の具体的な状況を踏まえると、当該企業の「代表者」(=観念的な代表者)が注意義務を尽くせば容易に不正競争行為の事実を判明できた事案といえる。裁判例④⑥は、重過失(評価)を超えて悪意(事実)まで認定している点では擬制的に過ぎるともいい得るものの、これも、当時の従業員の認識(④)や製品開発の状況(⑥)等の具体的な状況に照らして、当該企業の「代表者」(=観念的な代表者)の認識を規範的に捉えたものと整理することができる。
(4) 規範的な評価のプロセス
このように考えると、企業の悪意又は重過失を評価するに当たり、最も重要なことは、営業秘密が取得、開示、使用等された時点の状況をできる限り具体的に明らかにすることといえる。企業自体の認識を抽象的に論じようとしても、前述の東京高裁が判示するように民法や会社法上の理論的な問題点を抱える可能性があるし、そもそも裁判所に対して主観的要件の充足を説得的に説明することが困難である。重過失であれば、例えば、営業秘密を受領した従業員及びその担当部門、製品開発の契機や経緯、製品を上市するまでの期間、製品の類似性の程度、営業活動・宣伝広告・販売態様等の状況をできる限り具体的に明らかにした上で、その状況に置かれた企業の代表者ないし経営陣であれば、通常の取引上の注意義務を尽くすことで不正競争行為の介在を容易に認識し得たであろうということを、分かりやすく主張立証しようとする姿勢が肝要である。
3 さらに的確な立証を目指して
企業の認識はその代表者の認識と捉えることが原則である以上、原告(被害者)にとって悪意又は重過失の立証のハードルは高いといわざるを得ない。何故なら、部外者である原告(被害者)が代表者やその他の役職員による不正競争行為への関与の有無及び程度等まで含めた具体的な状況を明らかにすることは困難なことが多く、立証に窮することもあるからである。その立証の困難を打開するため、営業秘密侵害の事案では刑事告訴も検討に値する。実際、東京地判R3.6.4(平27(ワ)30656号)や大阪地判R2.10.1(平28(ワ)4029号)などでは、刑事事件を介して営業秘密侵害を裏付け得る資料が入手された。企業の主観的態様との関係では、例えば、代表者の認識を端的に裏付ける電子メールや検察官調書、製品開発の契機・経緯を示す社内会議の資料等を入手できる可能性もある。
自社の重要な営業秘密を的確に守るためには、主観的要件を含め、あらゆる手段を活用して綿密な主張立証を心掛けるべきである。
以 上