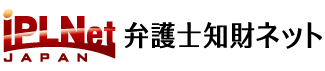弁護士知財ネット
弁護士 寺前翔平
PDF版ダウンロード:[営業秘密官民フォーラムメールマガジン掲載コラム] 第81回 知財高判令和7年3月25日(令和5年(ネ)第10057号損害賠償等請求控訴事件)の検討
第1 はじめに
本稿は、知財高判令和令和7年3月25日(令和5年(ネ)第10057号損害賠償等請求控訴事件)について、原審と控訴審とで営業秘密に係る不正競争行為の有無の判断が分かれた営業秘密の「使用」の有無の点を中心に検討するものである。なお、本判決は、控訴人及び被控訴人らをそれぞれ、原告及び被告らなどとしているので、以下これにならって検討する。
第2 事案の概要
原告(平成10年設立)及び被告会社(平成18年設立。なお、令和元年7月30日まで登記簿上の本店所在地が原告と同一であった。)は、いずれもインターネット競馬新聞の提供等を目的とする株式会社であり、それぞれ競馬の勝ち馬を数値で予想する「指数」(IDM指数)を算出して掲載している。原告の元従業員である被告Y1及びY2は、在職時、原告事務所内のパソコン等を使用して、被告会社の競馬新聞の発行業務に従事していたが、令和元年10月27日深夜から同月28日未明までにパソコン等を持出し、原告を退職したうえ、その後も被告会社の提供するインターネット競馬新聞であるハイブリッド競馬新聞及びマキシマム競馬新聞(地方競馬に係る競馬新聞)の発行を継続した。
本件は、原告が、被告会社及び被告Y1~Y3に対し、原告の①IDM指数作成プログラム及び指数作成手法、②デジタル競馬新聞作成システムプログラム、③IDM構成要素データ、④顧客管理名簿(以下順に「本件情報1」などといい、総称して「本件情報」という。詳細は本判決別紙参照)[1]が原告の営業秘密に該当するとしたうえで、被告会社及び被告Y1らが不正の利益を得る目的で原告の営業秘密である本件情報を使用するなどしたとして、不正競争防止法(以下「不競法」)3条1項・2項に基づき、本件情報の使用開示等の差止等を求めた事案である。
原判決(大阪地判令和5年4月24日(令和2年(ワ)第4948号損害賠償等請求事件)は、本件情報の営業秘密該当性について判断することなく、本件情報の「使用」等がないとして、不正競争防止法2条1項4号又は7号に当たる行為がないとした。これに対し、本判決は、本件情報の営業秘密該当性を肯定したうえで、被告らが図利加害目的で「使用」したとして、不正競争防止法2条1項7号の不正競争行為に該当するとし、同法3条に基づく差止請求等を認めたものである。
第3 営業秘密に係る不正競争行為の有無に係る判決の要旨
1 営業秘密該当性について
結論として、本件情報はいずれも原告の営業秘密に該当すると判断した。
(1) 有用性
ア 本件情報1及び3について
「レース結果における考慮要素に係るデータを数値化した点数を計算要素とし、原告独自のロジックとデータとプログラムに基づき競走馬及びレースごとの総合得点を算出して数値化し、これを前提に、開催されるレースの条件も勘案した補正等を加えて予想値となる数値をIDM指数(IDM結果値)として算出するものであり、これに基づき、原告独自のレース予想値として、IDM予想値を原告が発行するインターネットによる競馬新聞に掲載しているのであるから、」有用性が認められると判断した。
被告らの「単なるデータと個人の経験に基づくものであるから、有用性はない」との主張に対しては、「IDM予想値自体は、予想者の経験に基づくものだとしても、その基礎となるIDM結果値は、原告が独自に考案した考慮要素及び数値化の内容並びにこれを実行するプログラム(本件情報1)によって算出されるのであるから、本件情報1の有用性はあるというべき」と判断した。
また、被告らの「競馬新聞の作成に利用する公式データは、JRAのものであり、原告の営業秘密ではない」との主張に対しては、「原告は本件情報1及び3により、公式データからIDM指数作成のために必要となる考慮要素に応じたデータ等を抽出し、IDM結果値を作成するのであるから、公式データそれ自体は原告の営業秘密とはいえないとしても、IDM構成要素となるデータとして項目毎に整理された後のデータは、単なる公式データということはできないというべきである」と判断した。
イ 本件情報2について
「原告の発行するインターネットによる競馬新聞を作成するためのプログラムであるから、」有用性が認められる。
(2) 秘密管理性及び非公然性[2]
ア 本件情報1~3について
「『社外秘』とされて原告社内のコンピュータ等に格納され、業務の必要から従業員全員がアクセスすることができるが、社内ID及びパスワードの入力を必要とし、退職者がいる場合には一斉にパスワードが変更されるのであるから、」秘密管理性、非公然性が認められる。
イ 本件情報4について
「形式的には被告会社に帰属する情報であるが、被告会社は実質的には原告の一事業部門であったというべきであり、その性質に照らし、本件情報1から3までと同様の情報管理がされたいたことが推認されるから、営業秘密に該当する[3]。」
2 不競法2条1項7号該当性―原告及び被告らとの関係並びに図利加害目的での「使用」について
原告は、従前から、原告の従業員が形式的に会社を設立することを認め、売上の70%を原告に支払うこと等を条件に原告のデータやノウハウその他原告の物的・人的設備を使用することを認めていたのであり、平成18年2月に被告Y1を代表者として設立された被告会社におけるハイブリッド競馬新聞の発行も、その実体は原告の従業員が従前と同様の方法でハイブリッド競馬新聞の発行を継続していたにすぎない[4]。平成20年5月にハイブリッド競馬新聞が有料化された後は、被告会社から、原告に対し、約10年余の長期にわたり、その売上の70~75%が原告に支払われていたことがそれぞれ認められるから、原告と被告会社間においては、売上の70~75%相当額を支払うことを条件として、原告のシステムであるプログラムやデータを含む原告の物的・人的設備を使用することを認める旨の黙示の合意があったものと推認される。
また、ハイブリッド競馬新聞の作成には原告のシステムが使用されていたものであり、平成24年3月頃には、被告会社のシステムのプログラム言語が変更されたものの、ハイブリッド競馬新聞の作成は引き続き原告の社内で原告のシステムを使用して行われていたこと、被告Y1及び被告Y2が原告を退社した後の令和元年11月以降も、原告の発行するインターネットによる競馬新聞におけるIDM指数と、被告会社の発行するハイブリッド競馬新聞におけるハイブリッド指数とは類似性・相関性があること、及び被告Y1及びY2の退社に至る経緯(令和元年6月頃、被告会社の経費が高額になったことをY1に問いただして通帳の写し等の関係資料の開示を求めても被告Y1がこれに応じないなどの不審な行動に終始した挙句、被告Y1及び被告Y2が令和元年10月27日深夜から同月28日未明までに原告の社内からパソコン等を持出し、原告を退職した等の事実が認定されている)等を踏まえれば、不正の利益を得る目的又は原告に損害を与える目的で原告の営業秘密を使用した(不競法2条1項7号)ものと認めるのが相当である。
第4 検討
前記第3のとおり、本判決は、本件情報はいずれも原告の営業秘密に該当するとしたうえで、本件情報の被告らによる使用等について、不正競争防止法2条1項7号の不正競争行為に該当すると判断した。ここでは、原審と控訴審とで判断が分かれた営業秘密の「使用」の点について検討する。
1 営業秘密の「使用」の意義
営業秘密の「使用」とは、営業秘密の本来の使用目的に沿って行われ、当該営業秘密に基づいて行われる行為として具体的に特定できる行為を意味する(経済産業省知的財産政策室編『逐条解説 不正競争防止法(令和6年4月1日施行版)』(https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/Chikujo.pdf)282頁)。もっとも、全ての利用行為が営業秘密の「使用」に該当するわけではなく、営業秘密の「本来の使用目的に沿って」利用されていることが必要である。例えば本件で問題となった顧客名簿等でいえば、当該名簿に掲載された顧客に対して勧誘のための一斉メール送付等を行う行為は「使用」に該当するが、その本来の目的と全く異なる目的で利用する場合[5]には「使用」には該当しない。
また、営業秘密の「使用」といえる場合は、当該営業秘密と同一の情報を使用する場合に限られるものではなく、当該情報をもとに一部改良を加えた場合も含まれる(東京高判平成14年1月24日(平成13年(ネ)第3411号))が、原型をとどめないほどに営業秘密に改良が加えられた場合は「使用」には該当しない[6]。
技術上の情報が問題となった事例として、例えば、大阪地判平成25年7月16日判時2264号94頁は、営業秘密たるソフトウェアのソースコードについて、「営業秘密として保護される対象となるのは、現実のコードそのものに限られるというべき」とし、ソースコードに表現されるロジック(データベース上の情報の選択、処理、出力の各手順)をソフトウェア開発にあたり参照とすることは、「ソースコードの記述そのものとは異なる抽象化、一般化された情報の使用をいうものにすぎ」ないとして、不競法2条1項7号の「使用」には該当しないとした。また、知財高判令和元年8月21日金商1580号24頁は、同じくソフトウェアのソースコードについて、原告のソースコードと被告のソースコードの一部に類似部分があり、被告らが、類似部分について、原告のソースコードの変数定義部分を参照した可能性は否定できないとしつつ、当該変数定義部分は営業秘密ではないこと、その余の類似部分はソースコードを参照したことにより生じたとはいえないこと、並びに鑑定の対象となったソースコードのうち非類似部分が99%であることなどを理由に、不競法2条1項7号の「使用」には該当しないとした。
営業秘密の「使用」の立証は、直接証拠で立証することは難しく、困難な場合も多い。その立証は、本件でもそうであったように、多くの場合、間接事実を積み上げて行うことになる。
2 本件の検討
本件では、原告が、その従業員に対し、形式的に自らの会社を設立することを認め、売上の70~75%を原告に支払うこと等を条件に原告のデータやノウハウを使用することを認めてきたところ、被告会社も原告の従業員であった被告Y1を代表者として設立された会社であり、当該会社の業務の一部は、原告の社内で、原告の設備を利用して行われていたという特殊性があった。この点に関し、原判決は、被告Y1が従事した業務が明確に原告ものである場合を除き、ハイブリッド競馬新聞の発行やそのためのシステムの整備などは被告会社独自のものであるとした。当該認定に基づき、被告Y1と被告Y2が原告の社内から、インターネット上で提供する競馬新聞を作成するために使用していたパソコン等や私物を搬出した事実を認定したにもかかわらず、本件情報を使用等していたものとは認めるに足りないとして、「使用」には該当しないと判断した。
これに対し、本判決は、前記第3の2に記載のとおり、前記搬出の事実を含む前後の経緯について、被告会社におけるハイブリッド競馬新聞の発行の実体が原告の従業員が従前と同様の方法でその発行を継続していたにすぎないこと、原告と被告会社間においては、売上の70~75%相当額を支払うことを条件として、原告のシステムであるプログラムやデータを含む原告の物的・人的設備を使用することを認める旨の黙示の合意があったこと、ハイブリッド競馬新聞の作成には、被告会社内のシステムのプログラム言語変更後も原告の社内で原告のシステムが使用されていたこと、被告Y1及びY2が原告を退社した後も原告の発行するインターネットによる競馬新聞におけるIDM指数と被告会社の発行するハイブリッド競馬新聞におけるハイブリッド指数とは類似性・相関性があること、並びに被告Y1及びY2の退社に至る経緯等を比較的詳細に認定し、また、本件情報のそれぞれについて、その内容及び使用態様を相当詳細に認定して[7]、結論として原告の営業秘密の図利加害目的での「使用」を基本的に肯定した。
他方で、原告が地方競馬に係る新聞(被告の作成するマキシマム競馬新聞がそれにあたる)を作成発行したことが無かったこと、原告のシステムにおいてマキシマム競馬新聞の作成に用いられるデータが存在したり、プログラムが組み込まれたりするなど、被告会社がマキシマム競馬新聞の作成において原告のシステムを使用していたことを窺わせるような証拠も提出されていないことなどから、被告会社において、本件情報等を利用してマキシマム競馬新聞を作成していたことを認めるに足りる証拠がないとして、不競法違反を否定した。
原審と控訴審の認定・判断が分かれており、控訴審の認定・判断においても、原告における営業秘密の使用態様と被告らの当該情報の利用態様等に応じて結論が分かれている点で、実務上参考になると考えられる。
以上
[1] 本件情報が具体的にどのような内容であるかについては、閲覧制限によるマスキング箇所が相当広範囲に及んでいるため、不明な点も多い。
[2] 非公知性とするのが一般的と思われるが、本判決の用語法によっている。
[3]有用性に関する判示は特段なく、顧客管理名簿の具体的な内容が省略されているため詳細は不明であるものの、特に争いはなかったものと思われる。
[4] 下線部は筆者が付したものである。以下同様。
[5] このような場合の例として、小倉秀夫ほか編著『新版 不正競争防止法コンメンタール』131頁〔山口美惠子=西川喜裕〕(第一法規、2025年)は、顧客名簿をあいうえお作文や俳句を作成することに利用する場合を挙げる。
[6] 髙部眞規子『実務詳説不正競争訴訟』223頁(きんざい、2020年)
[7] もっとも、相当部分がマスキングされており具体的な認定の内容は不明な部分も多い。