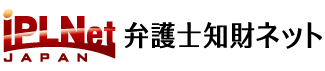弁護士知財ネット
弁護士 荏畑 龍太郎
PDF版ダウンロード:[営業秘密官民フォーラムメールマガジン掲載コラム] 第79回 公正取引委員会「音楽・放送番組等の分野の実演家と芸能事務所との取引等に関する実態調査報告書」における営業秘密と独占禁止法の関係について
本コラムでは、2024年12月26日に公正取引委員会が公表した「音楽・放送番組等の分野の実演家と芸能事務所との取引等に関する実態調査報告書」(以下、「本報告書」という。)において指摘されている、営業秘密と独占禁止法に関する論点について検討する。
第1 はじめに
公正取引委員会が2024年12月26日に公表した「音楽・放送番組等の分野の実演家と芸能事務所との取引等に関する実態調査報告書」では、実演家(アーティスト、俳優、タレント等)と芸能事務所との契約や取引慣行について調査が行われた。本報告書は、優越的地位の濫用等を防止し、クリエイター個人の創造性が最大限発揮される取引環境を整備するため、音楽・放送番組等の実演家(アーティスト、俳優、タレント等)とその所属する芸能事務所・プロダクション(以下、「芸能事務所」という。)との契約等について実態を調査したものである。
本報告書の中で、営業秘密に関わる論点として、競業避止義務と独占禁止法に関する論点の指摘がなされているため、以下紹介する。
第2 営業秘密と競業避止義務の関係
不正競争防止法上、営業秘密は、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」(2条6項)と定義され、このような「営業秘密」として保護の対象となるためには、①秘密管理性、②有用性及び③非公知性の3つの要件を満たす必要があり、こえにより同法に基づき民事上及び刑事上の保護を受けることが可能となる。
他方で、どれほど重要な情報であったとしても、データ化・マニュアル化に資さないような特定の従業員に紐づいている知識や経験等については、不競法上の営業秘密として保護されるための3つの要件に該当しないと判断される場合もありうる。このような場合に、企業としては、従業員との間で秘密保持契約を締結することにより秘密保持義務を課す場合の他、当該従業員の転職に伴う当該知見の競業他社への流出を防ぐため、入社の段階から「競業避止義務」を課す場合がある[1]。
ここでいう、「競業避止義務」とは、相手方と取引を行う際に、相手方に対し、行為者の事業と競合する事業活動を行わない義務を課すことをいう[2]。競業他社のために技術情報や営業情報が利用されることを防止するため、従業員が会社の業務と競業する事業を自ら営むことや、そのような事業に就職させないようにする際に課されることが一般的である。
競業避止義務の違反があった場合であっても、上記の不競法上の要件を満たさない限り、流失した情報を利用しようとする競業他社に対しては義務違反を主張できず、義務違反者に対して刑事罰が科されるわけではない。しかしながら、競業避止義務違反の有無は、営業秘密や秘密保持義務違反の場合の秘密情報の漏洩の有無よりも外形的に把握、立証することが容易であるため、使用者側としては競業避止義務を定めておきたいという実務上の要請がある[3]とされている。
このような競業避止義務に関する論点としては、競業避止義務契約の有効性に関する論点と、競業避止義務を課すことの独占禁止法の問題に関する論点に大別される。
このうち、競業避止義務契約の有効性を巡っては、在職中の競業行為が認められないことは当然として、退職後について競業避止義務を課すことについては、職業選択の自由を侵害し得ること等から、制限的に解されているところ、判例上は、「債権者の利益、債務者の不利益及び社会的利害に立って、制限期間、場所的職種的範囲、代償の有無を検討し、合理的範囲において有効」であるとされている[4]。経済産業省知的財産政策室では、平成28年2月に策定した「秘密情報の保護ハンドブック~企業価値向上に向けて~」(最終改訂令和6年2月)において、以下のとおり、判例における有効性判断のポイントを示している[5]。
| ■ 競業避止義務契約が労働契約として、適法に成立していることが必要。
■ 判例上、競業避止義務契約の有効性を判断する際にポイントとなるのは、①守るべき企業の利益があるかどうか、①を踏まえつつ、競業避止義務契約の内容が目的に照らして合理的な範囲に留まっているかという観点から、②従業員の地位、③地域的な限定があるか、④競業避止義務の存続期間や⑤禁止される競業行為の範囲について必要な制限が掛けられているか、⑥代償措置が講じられているか、といった項目である。 |
第3 競業避止義務と独占禁止法の関係
競業避止義務に関しては、このような競業避止義務契約の有効性の論点の他に、事業者同士において、競業避止義務を課すことが、独占禁止法との関係で問題になる場合がある。
この点、公正取引委員会は、フリーランス等の雇用契約会競争政策研究センターが平成30年2月15日に策定した「人材と競争政策に関する検討会報告書」において、以下のとおりポイントが整理され、競業避止義務が独占禁止法に抵触する場合について解説がなされており、優越的地位の濫用の問題となる可能性等について指摘されている。
| 【ポイント】
○ 自由競争減殺の観点からは、発注者(使用者)が、営業秘密等の漏洩防止の目的のために合理的に必要な(手段の相当性が認められる)範囲で秘密保持義務又は競業避止義務を課すことは、直ちに独占禁止法上問題となるものではない。 ○ 競争手段の不公正さの観点からは、発注者(使用者)が役務提供者に対して義務の内容について実際と異なる説明をし、又はあらかじめ十分に明らかにしないまま役務提供者が秘密保持義務又は競業避止義務を受け入れている場合には、独占禁止法上問題となり得る。 ○ 優越的地位の濫用の観点からは、優越的地位にある発注者(使用者)が課す秘密保持義務又は競業避止義務が不当に不利益を与えるものである場合には、独占禁止法上問題となり得る。 |
第4 「音楽・放送番組等の分野の実演家と芸能事務所との取引等に関する実態調査報告書」における競業避止義務違反の論点に関する指摘について
本報告書では、芸能事務所が実演家に対して競業避止義務を課すことについて、以下のとおり独占禁止法上の考え方を示している[6](下線部は筆者)。
| (2)独占禁止法上の考え方
競業避止義務等は、退所後の一定期間、実演家が一切の芸能活動を行わない、他の芸能事務所に対して役務提供を行わない等を内容とするものであり、実演家の実演という事業活動を直接に制約するものであり、実演家の自由かつ自主的な判断による取引を阻害するものとして、不利益の程度は相当に大きい。 芸能事務所等に対するヒアリング調査等では、競業避止義務等の活動制限を行う 理由としては、引き抜き防止又は育成費用の回収を目的としているとの回答がある のみである。単に引き抜きを防止することは、実演家を獲得する市場における芸能事務所間の競争を阻害すること以外の合理的な目的を有するものではないことから競業避止義務等を課す合理的な目的としては認められず、また、退所後の実演家の活動を制限することで育成費用を回収することはできないため、育成費用の回収という目的のために退所後の実演家の活動を制限することも認められないと考えられる。 競業避止義務は、一般的には、営業秘密等の漏えい防止の目的の達成のために合理的な必要性かつ手段の相当性が認められる範囲で課されるのであれば、実演家に対する営業秘密等に相当する情報の提供を可能とし、競争促進効果を有し得るものである。しかし、仮に営業秘密等の漏えい防止を目的として競業避止義務等の活動制限を課すとしても、芸能分野においては、基本的に実演のみを行い、芸能事務所の運営そのものには関わることがない実演家が営業秘密を知ることは例外的な場合であると考えられること、仮に保護すべき営業秘密があったとしても、実演の禁止といった事業活動そのものに制約を課すより競争制限的でない他の手段として、秘密保持契約を締結するというような手段も検討し得ることを踏まえると、そもそもこれらの活動制限を課すこと自体の必要性・相当性が認められない可能性が高いと考えられる。 そのため、例えば、実演家に対して取引上の地位が優越していると認められる芸能事務所が、その地位を利用して、実演家に対して競業避止義務等を課すことで実演家の移籍、独立を断念させることなどにより、実演家に正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える場合は、優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となる。 また、芸能事務所が、競業避止義務等を課すことで、他の芸能事務所が実演家を確保できなくなることなどにより、他の芸能事務所が排除される又はこれらの取引機会が減少するような状態をもたらすおそれが生じる場合には、排他条件付取引又は拘束条件付取引として独占禁止法上問題となる。 そして、競業避止義務等を課すことについて例外的に必要性・相当性が認められたとしても、芸能事務所が、実演家と契約するに当たり、競業避止義務等を課すことについて、十分な説明を行わず、又は虚偽若しくは誇大な説明をし、これにより、実際の契約内容よりも著しく優良又は有利であると誤認させ、他の芸能事務所と取引し得る実演家を自己と契約するように不当に誘引する場合には、欺瞞(ぎまん)的顧客誘引として独占禁止法上問題となる。 さらに、独占禁止法の違反行為を未然に防止するという競争政策上の観点からは、原則として、競業避止義務等を契約上規定すべきではなく、仮に、保護されるべき営業秘密を実演家が把握するような場合には、より競争制限的でない他の手段として、まずは秘密保持契約を検討すべきである。 |
上記の考え方で示された特徴的な点としては以下の点が挙げられる。第一に、本報告書では、単に引き抜きを防止することは、実演家を獲得する市場における芸能事務所間の競争を阻害すること以外の合理的な目的を有するものではないことから競業避止義務等を課す合理的な目的としては認められないこと、また、退所後の実演家の活動を制限することで育成費用を回収することはできないため、育成費用の回収という目的のために退所後の実演家の活動を制限することもまた、合理的な目的としては認められない旨示されている点が挙げられる。
競業避止義務を課す目的として、相手方に提供する秘密情報の流用や漏洩を防止することや、行為者が商品等を供給するのに必要な商品等の提供を受けるために自己との取引にさせること、行為者が相手方に一定のノウハウ、スキル等を身に着けるようにするための育成投資を行った上で、その育成に要する費用を回収することといった場合には、合理性が認められることがある[7]と考えられているところ、芸能事務所と実演家との間で競業避止義務等の活動制限を行う場面においては、「芸能分野においては、基本的に実演のみを行い、芸能事務所の運営そのものには関わることがない実演家が営業秘密を知ることは例外的な場合であると考えられること、仮に保護すべき営業秘密があったとしても、実演の禁止といった事業活動そのものに制約を課すより競争制限的でない他の手段として、秘密保持契約を締結するというような手段も検討し得る」ことから、このような目的の合理性が認められ、正当化される可能性は低いということが明確に指摘されている。
また、本報告書では、芸能事務所と実演家との間で競業避止義務等の活動制限を行う場合に当たって該当する可能性のある不公正な取引方法の行為類型のうち、複数の行為類型が示されている。
従来、芸能分野において、公正取引委員会は、令和元年9月25日に開催された公正取引委員会委員長と記者の懇談会において配布された資料である「人材分野における公正取引委員会の取組」の中で「芸能分野において独占禁止法上問題となり得る行為の想定例」と題して、芸能人と所属事務所との関係において、競業避止義務契約を締結した場合に、以下のように、優越的地位の濫用等に該当する可能性がある旨見解を示していた。
| <芸能人の移籍・独立に関するもの>
● 所属事務所が、契約終了後は⼀定期間芸能活動を行えない旨の義務を課し、又は移籍・独立した場合には芸能活動を妨害する旨示唆し、移籍・独立を諦めさせること (優越的地位の濫用等) |
他方、本報告書では、芸能事務所が実演家との間で競業避止義務等の活動制限を行う場合、優越的地位の濫用(独占禁止法2条9項5号)の他、排他条件付取引(一般指定11項)、拘束条件付取引(一般指定12項)に加えて、欺瞞的顧客誘引(一般指定8項)に該当する場合もあることが示されている。とりわけ欺瞞的顧客誘引については、対象となる行為についてはおおむね、景表法の不当表示規制において具体化され、機動的運用が図られているため、基本的に本類型の登場機会は少ないと考えられている従前の経緯があるため[8]、本報告書において、このような行為類型について該当する可能性がある点について明示的に指摘されている点は特徴的である。
なお、本件のような競業避止義務の論点を巡っては、独占禁止法と他の法分野との関係、特に、不正競争防止法、労働法、独占禁止法の間の適用関係について留意する必要がある場面が想定される点を指摘したい。競業避止義務を課す場合のような競業を妨げる行為の規制に関して、不正競争防止法、労働法上のルールとの関係において、独占禁止法がどこまで適用されるのかという点については、例えば、不正競争防止法で保護される営業秘密を利用させない行為については、独占禁止法21条により、原則として独占禁止法違反とはならないと考えられ、例外的に独占禁止法違反となるのは、不正競争防止法の趣旨目的に反する濫用行為がある場合であり、具体的にいかなる場合がこれに当たるかについては、特許等の知的財産について詳説する公正取引委員会の知財ガイドラインが参考になるといった指摘[9]がなされているなど、競業避止義務を巡る労働法、独占禁止法、知的財産法が交錯する場面も想定される点に留意する必要がある。
以 上
<注釈>
[1] 菅原裕人・岩崎啓太・松田誠司「知財を強みとする法務パーソンのための実務ポイント(第5回)知財×労働法 営業秘密の保護と競業避止義務・引き抜き行為」(NBL №1247(2023年))60頁
[2] 長澤哲也『優越的地位濫用規制と下請法の解説と分析〔第4版〕』(商事法務、2021年)315頁
[3] TMI総合法律事務所編『Q&A 営業秘密をめぐる実務論点』(中央経済社、2016年)134頁
[4] 経済産業省知的財産政策室「秘密情報の保護ハンドブック~企業価値向上に向けて~」(最終改訂令和6年2月)「参考資料5 競業避止義務契約の有効性について」221頁
[5] 前掲注4 221頁
[6] 公正取引委員会「音楽・放送番組等の分野の実演家と芸能事務所との取引等に関する実態調査報告書」(クリエイター支援のための取引適正化に向けた実態調査)(令和6年12月)38頁、39頁
[7] 前掲注2 315頁、316頁
[8] 白石忠志・多田敏明『論点体系 独占禁止法 第2版』(第一法規、2021年)159頁
[9] 和久井理子「競業・転職・独立開業を妨げる行為と競争政策 ―競業避止義務をめぐる労働法と独禁法の交錯」(NBL №1157(2019年))8頁、11頁、12頁