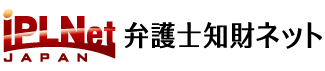弁護士知財ネットでは、知的財産に関するQ&Aを公開しています。
今回も特許法に関するよくある質問と回答をお届けします。
今回は、特許権侵害(権利者側)のうち間接侵害と損害に関する質問にお答えします。
- Q61 当社が特許権を有する製品の模倣品を発見しました。しかし、調査したところ、この業者は製品の主要部分を部品として販売し、購入者はこれを組み立てて使用するようです。この販売業者の行為は、当社の特許権を侵害しないのでしょうか。
- Q62 間接侵害の類型を簡単に教えてください。
- Q63 特許権が侵害された場合、どのように請求額を算出すればよいのでしょうか。
- Q64 特許法第102条1項とはどのような規定ですか。
- Q65 特許法第102条2項とはとはどのような規定ですか。
- Q66 特許法第102条3項とはどのような規定ですか。
- Q67 その他の費用は請求できないのでしょうか。
- Q68 不当利得構成の場合、特許法第102条1項ないし3項の規定は適用されないのでしょうか。
- Q69 間接侵害の場合も特許法第102条1項ないし3項の規定が適用されるのですか。
- Q70 補償金請求とは何ですか。
Q61 当社が特許権を有する製品の模倣品を発見しました。しかし、調査したところ、この業者は製品の主要部分を部品として販売し、購入者はこれを組み立てて使用するようです。この販売業者の行為は、当社の特許権を侵害しないのでしょうか。
A61 侵害製品の一部品のように、構成要件の一部しか充足しないものの製造等であっても、特許権侵害を誘発する可能性が高い一定の行為については侵害行為とみなすこととされています(特許法第101条)。これを「間接侵害」といいます(これに対し、特許発明の構成要件を全て充足した製品の製造販売行為等については、「直接侵害」といいます。Q54、57参照)。
特許法第101条は、同条第1号から第6号まで6つの行為態様を侵害行為とみなしています。このうち、第1号から第3号が物の発明について、第4号及び第5号が方法の発明について、第6号が物を生産する方法の発明についての規定です。
ご質問の場合ですと、このうち第1号又は第2号該当性が問題となります。販売業者が販売している部品が特許発明の実施品の生産にのみ用いられるものであれば第1号が、販売業者が販売している部品が特許発明の課題解決に不可欠であり、かつ、販売業者が特許権の存在及びその部品が特許発明の実施に用いられることを知りながら販売しているのであれば第2号が該当し、特許権侵害になります。
A62 間接侵害は、特許法第101条第1号から第6号に規定されています。
このうち、
第1号は、いわゆる「のみ品」についての規定です。この「のみ」要件とは、経済的、商業的又は実用的な他の用途が存在しないこととされています(大阪地判平12.10.24製パン機事件等)。
第2号は、いわゆる「課題解決不可欠品」についての規定です。この「課題解決不可欠品」要件とは、発明が新たに開示する、従来技術に見られない特徴的技術手段について、当該手段を特徴づけている特有の構成ないし成分を直接もたらす、特徴的な部材、原料、道具等とされています(東京地判平16.4.23プリント基板用治具に用いるクリップ事件等)。また、第1号では「のみ品」に該当すれば行為者の主観を問うことなく間接侵害となるのに対し、第2号では主観的要件が付加されています。
第3号は、譲渡等の目的がある所持を侵害とみなす規定です。譲渡によって侵害品は拡散してしまうので、その後に個々の権利者に対して個別に権利行使をすることは困難です。第3号は、その前段階である所持の段階で権利行使を認めるものです。
第4号は、方法の発明について、第1号と同様の間接侵害を定める規定です。
第5号は、方法の発明について、第2号と同様の間接侵害を定める規定です。
第6号は、物を生産する方法の発明について、第3号と同様の間接侵害を定める規定です。
A63 特許権侵害行為に対して金銭請求をする場合、大きく分けて不法行為構成と不当利得構成が有りえます。
不法行為構成とは、民法第709条に基づいて、侵害行為によって生じた損害の賠償を求める、というものです。
不当利得構成とは、民法第703条(又は民法第704条)に基づいて、侵害者が無許諾で発明を実施したことによって法律上の原因なく受けた利益の返還を求める、というものです。
これらの構成の違いによって、時効や請求できる損害の範囲が変わります。
時効の問題については、不法行為構成の場合には損害及び加害者を知ったときから3年であるのに対し、不当利得構成の場合には10年と大きな違いがあります。
請求できる損害の範囲については、不法行為構成の場合には損害額算出について特許法第102条1項ないし3項の規定を用いることが認められています。これらの規定は、損害額についてそれぞれ独自の算定方法を認めるものですので、1項ないし3項のいずれに基づいて請求を行うかによって算出される損害額が変わります。不当利得構成の場合にはこれらの規定を用いることは認められていません。
そのため、直近の3年間については不法行為構成によって損害賠償を請求し、それ以降10年前までの損害については不当利得構成によって請求を行う、という方法が一般的です。
A64 特許法第102条1項は、侵害行為によって特許権者が得ることができなくなった売上額を損害額とすることを認めています。
特許権者が実施品を販売している限り、侵害行為によって当該実施品の売り上げは低下することになります。特許法第102条1項は、その低下した売上額を損害額として請求できるとするものです。低下した売上額を損害額として請求するのですから、1項の適用が認められるためには、特許権者が「その侵害の行為がなければ販売することができた物」を販売している必要があります。
また、必ずしも侵害行為がなかった場合に侵害品の譲渡数量全てを特許権者が販売したとは限りません。そのため、特許法第102条1項は、損害の算定において、「特許権者の実施の能力」と「譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者が販売することができないとする事情」を考慮することとしています。
A65 特許法第102条2項は、侵害行為によって侵害者が得た利益を損害額と推定することを認めています。
必ずしも侵害行為が無かった場合に侵害行為によって侵害者が得た利益を特許権者が得ることができたとは限りませんが、特許法第102条2項は、当事者の公平という観点も踏まえてこのような推定を認めたとされています。
2項の適用が認められるためには、特許権者が特許発明を実施していることまでは必要ではないが、侵害者による特許権侵害行為が無ければ利益を得られていたであろうという事情が必要であるとされています(知財高裁大合議平成25年2月1日)。
A66 特許法第102条3項は、特許権者が侵害者による特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する学の金銭を損害額とすることを認めています。
第三者が特許発明を実施するためには特許権者に実施料を支払う必要があります。そこで、特許法第102条3項は、そのような実施料相当額を損害として請求することを認めています。3項については、特許権者が特許発明を実施している必要はありません。
A67 訴訟では、この他に弁護士費用の賠償が認められています。といっても、訴訟で認められた特許権侵害に基づく損害の一定割合しか認められないことが多く、実際に要した弁護士費用全額が認められることはほとんどありません。
なお、請求認容判決においては、「訴訟費用の負担」についても判断されますが、これは、訴訟印紙代や証人の出廷費用等であり、弁護士費用を含むものではありません。
A68 特許法第102条1項ないし3項は、不法行為構成における損害の額について定めたものと解されており、不当利得構成について各項は適用されません。そのため、不当利得構成ですと損害額について、侵害行為によって侵害者が得た利益と当該利益について特許権者の損失を主張・立証する必要があります。実施料相当額の請求が一般的です。
A69 間接侵害も特許権侵害とみなされますので、特許法第102条1項ないし3項を適用することができます。
A70 特許法第65条1項は、出願公開後特許権の設定登録までの間に特許発明を実施した第三者に対し、実施料相当額の補償金の支払を請求することを認めています。これを、補償金請求権といいます。
補償金請求権は特許権が成立していない期間について実施料相当額の支払を求めるものなので、特許権侵害に基づく損害賠償とは異なり、事前に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告を行うか、実施した第三者が出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知っていたことが要件とされています(特許法第65条1項)。
また、補償金請求権は特許権の設定の登録があった後でなければ行使することができませんし(特許法第65条2項)、出願公開後に特許権の設定の登録がない場合、初めから生じなかったものとみなされます(特許法第65条5項)。