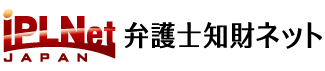弁護士知財ネットでは、知的財産に関するQ&Aを公開しています。
今回も特許法に関するよくある質問と回答をお届けします。
今回は、特許権侵害における被疑侵害者(特許権者等から権利行使を受けた者)の防御方法に関する質問にお答えします。
知的財産権に関するQ&A(9) 特許法(8)|被疑侵害者の防御方法
A71 まず、原告が主張する請求原因事実を積極否認すること(特許発明の技術的範囲に属さない、「にのみ」要件等の間接侵害の要件を充足しない等)が考えられます。
他には、実務上よくみられる被告の主張(抗弁)として次のようなものがあります。
①特許無効の抗弁(特許法第104条の3)、②試験研究のための実施(特許法第69条1項)、③実施権の存在(先使用による法定通常実施権、職務発明における使用者の法定通常実施権、約定実施権等)、④国内消尽、⑤並行輸入。
A72 特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるとき、特許権者等は、相手方に対し、特許権を行使することができません。これを特許無効の抗弁といいます(特許法第104条の3)。
「無効審判により無効にされるべきもの」とは、対象特許に新規性欠如や進歩性欠如といった無効理由がある場合をいいます(その他の無効理由について特許法第123条1項。新規性欠如、進歩性欠如についてはQ14~Q19を参照ください。)。
A73 特許権侵害の要件を形式上充足していても、特許発明の実施が試験又は研究のためにするものと評価される場合には、特許権侵害とはなりません(特許法第69条1項)。
特許制度は、発明者に一定期間の独占権(特許権)を与える代償として発明を公衆に開示させて、その開示された発明に基づいた技術を他の者がさらに発展させ、さらに公開させるという繰り返しによって産業の発達を目指すものです(特許法第1条)。公衆に公開された発明を用いてさらなる技術の開発をするために試験や研究をすることは、特許制度の根幹に基づく要請であり、この趣旨のあらわれとして特許法第69条1項が規定されています。
A74 Q73に記載した趣旨から、技術の向上を目指す試験・研究は、特許法第69条1項の「試験又は研究」に該当すると解されています。
また、無効審判制度(特許法第123条)の存在からして、特許発明の新規性、進歩性、実施可能性などを調査して資料を収集するためにする試験や研究も、69条1項の「試験又は研究」に該当すると解されています。
一方、市場調査をして売上げ予測をするために行われる試験や、特許権の期間満了後の実施に備えてデータを集積するための試験的実施等は、69条1項の「試験又は研究」に該当しないと考えられています。
但し、ジェネリック薬品の開発の関係で、特許存続期間満了後に販売するために行う薬事法14条所定の承認申請を行うための試験・製造は、「試験又は研究のためにする」にあたると解されています(最高裁平成11年4月16日判決)。
A75 日本の特許法は先願主義を採用しているので、これを徹底すると、特許権者とは別に偶然同一発明を完成したものの特許出願をしなかった者は、当該発明を実施することはできないこととなりそうです。しかし、出願が後れた者の発明の実施を一切禁止してしまうとそれまでの努力や投下資本を無にしてしまい不公平であると考えられます。そこで、このような出願に後れた発明者について一定の範囲内で実施権を認めるものとされており(特許法第79条)、これを先使用による法定通常実施権といいます。
A76 ① 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得したこと
② 特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしていること、又は、その事業の準備をしていること
A77 ウォーキングビーム事件判決(最高裁昭和61年10月3日民集40巻6号1068頁)によると、単に発明を実施する意図があるだけでは足りず、発明を即時に実施する意図があり、かつ、その意図が客観的に認識される程度に表明されていることを要するとされています。
A78 先使用による通常実施権は、「発明及び事業の目的の範囲内」に及びます。
この意義については諸説ありますが、実際に実施している実施形式のみに限定されるのではなく、「同一技術思想の範囲内」にまで及ぶとするのが多数説であり、裁判例上もほぼこの説により運用されています(ウォーキングビーム事件判決(最高裁昭和61年10月3日民集40巻6号1068頁)。
A79 Aが特許発明の実施品を生産してBに譲渡し、BがこれをCに再譲渡し、Cがこれを使用している場合、ABCの行為は、いずれも特許発明の実施(特許法第2条3項)に該当します。
ここで、Aが特許権者又は実施権者である場合、BやCの行為が特許権侵害になるとすると、商品の自由な流通を阻害し(商品の自由な流通の確保の要請)、また、AはBへの譲渡の際に一旦対価を得ておきながらさらにBやCに対して特許権を行使して利得を得ることが可能となってしまい(二重の利得論)、いかにも不都合です。
そこで、特許権者等の意思により商品が流通に置かれた場合、当該商品については、特許権は消尽し、当該商品の譲渡等は特許権侵害とならないとするのが消尽理論です。日本国内の消尽は、Q80で紹介するBBS事件最高裁平成9年7月1日判決でも認めています。
A80 ある商品が複数の国で販売されているときに、正規販売ルートとは別に、特定の国で販売している商品を購入して他の国へ輸入する行為を「並行輸入」といい、この並行輸入について輸入国における特許権を行使できるかどうかが問題となることがあります。
例えば、X社が日本とA国で特許権を有しており、Yが、A国で販売されているX社の製品(特許発明の実施品)を購入して日本に輸入する場合を考えます。X社が有する日本の特許権とA国の特許権は、相互に独立した関係にあり(特許独立の原則)、また、それぞれの国の法律によって定められ、当該国の領域内においてのみ認められます(属地主義)。そのため、A国でX社が販売したX社製品についてA国の特許権が消尽したとしても、当然に日本国の特許権の効力も消尽するとはいえないと解されています。
ただし、国際的な商品の流通が発展している現在において、並行輸入を全面的に特許権侵害とすると国際取引を阻害するおそれがあり、判例は、「我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が、国外において特許製品を譲渡した場合においては、特許権者は、譲受人に対しては、当該製品について販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合を除き、譲受人 から特許製品を譲り受けた第三者及びその後の転得者に対しては、譲受人との間で右の旨を合意した上特許製品にこれを明確に表示した場合を除いて、当該製品について我が国において特許権を行使することは許されないものと解するのが相当である。」として、一定の例外を除き、並行輸入に対する特許権行使は認められない旨の判断を示しました(BBS事件 最高裁平成9年7月1日判決・民集51巻6号2299頁)。
この考え方によれば、X社がA国で販売した際に、購入者との間で、日本を販売先から除外するとの合意をし、そのことを特許製品に明示していた場合のみ、X社はYの日本への輸入行為(並行輸入)に対して日本の特許権を行使することが認められます。なお、商標と並行輸入については、フレッドペリー事件最高裁平成15年2月27日判決が異なる基準を示しています。